障害者差別解消法について
障害者差別解消法(正式名称「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)」)は、国や市区町村といった行政機関や、会社やお店などの事業者の、障がいがある人に対する「障がいを理由とする差別」をなくすための決まりごとを定めた法律です。
障がいの有無にかかわらず、すべての人がお互いの人格と個性を尊重し合いながら共生できる社会をつくることを目的とした法律です。
障害者差別解消法の対象
「事業者」とは?
「事業者」とは、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問いません。一般的な企業やお店だけでなく、例えば個人事業者や対価を得ない無報酬の事業、非営利事業を行う社会福祉法人や特定非営利活動法人も対象となります。
「障がいのある人」とは?
「障がいのある人」とは、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいおよび高次脳機能障がいを含む)、難病等に起因する障がいその他心身の機能の障がいがある人で、障がいや社会的な障壁によって日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人です。障害者手帳を持っていない人も含まれます。
不当な差別的取扱い
企業や店舗などの事業者や国・都道府県・市町村などの行政機関等が、障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として差別することを禁止しています。
合理的配慮の提供
事業者や行政機関等に対して、障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することをいいます。障がいのある女性に対しては、障がいに加えて女性であることも踏まえた対応が求められています。
令和6年4月1日から、事業者による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務になりました。
 合理的配慮の提供が義務化されます(PDF) [1568KB pdfファイル]
合理的配慮の提供が義務化されます(PDF) [1568KB pdfファイル]- 合理的配慮の提供等事例集 (内閣府ホームページ)(外部リンク)
- 改正障害者差別解消法について(令和5年11月内閣府開催 改正障害者差別解消法に係る説明会動画)(外部リンク)
環境の整備
個別の場面において、個々の障がいのある人に対する合理的配慮が的確に行えるよう、事前の改善措置として行政機関等や事業者に係る施設のバリアフリー化などに努めることをいいます。
市の取り組み
市職員が適切に対応するため、「狛江市職員の障害を理由とする差別解消推進対応要領(平成28年3月15日市長決裁)」を制定し、障がいのある人およびその家族、関係者等からの障がいに係る差別等に関する相談窓口を次のとおり定めています。
- 当該事案に係る事務を所管する課
- 総務部職員課
- 福祉保健部福祉相談課
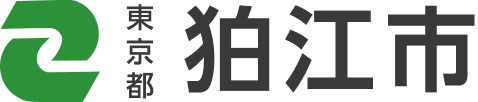
 印刷
印刷
 戻る
戻る
 ページの先頭
ページの先頭