令和7年度第2回障がい小委員会(令和7年6月10日)
|
1 日時 |
令和7年6月10日(火曜日) 午後6時~7時5分 |
|
2 会場 |
ハイブリット開催(防災センター4階会議室) |
|
3 出席者
|
委員長:眞保 智子 福祉政策課長(古内 洋一) |
| 4 欠席者 | 委員:阿部 利彦 |
|
5 議題 |
|
|
6 資料 |
|
|
7 会議の結果 |
(委員長)
本日はお忙しい中、令和7年度狛江市市民福祉推進委員会 第2回障がい小委員会に御参加いただきまして、ありがとうございます。防災センターの会場で開催させていただきます。
また、本委員会は会議録作成のため、音声認識システムを使い文字起こしをしています。音声を確実に拾うために、今回も引き続き各テーブルにマイクを設置しております。会場参加の方は御発言の際はマイクをオンにしていただき、マイクに向かってお話しください。オンライン参加の方は、大きな声でゆっくりとお話いただきますよう、御協力をお願いいたします。
では定刻になりましたので、議事を開始させていただきます。
欠席者・遅刻者の確認を事務局からお願いいたします。
(事務局)
欠席者ですが、阿部委員より御欠席の連絡をいただいております。
本委員会の委員総数は7人となっており、6人の委員が御出席されておりますので、狛江市福祉基本条例施行規則第29条で準用する第25条第1項の規定による「委員総数の半数以上の委員の出席」という会議開催の要件を満たしております。よって、本委員会は有効に成立しております。
(委員長)
それでは、本日の資料の確認をいたします。事務局から説明をお願いします。
(事務局)
本日の議題等を御説明させていただきます。
本日の小委員会の目的としては、市の実施計画の評価結果の評価について報告、実施計画の障がい小委員会における評価について審議、狛江市第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画サービス見込量(目標値)に対する令和6年度実績値について報告をさせていただきます。
では、資料について御説明をさせていただきます。
【資料1】市の実施計画の評価結果の評価について P.3~9
【資料2】狛江市第1次地域共生社会推進基本計画実施計画(狛江市市民福祉推進委員会による進捗状況評価) P.10~27
【資料3】狛江市第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画サービス見込量(目標値)に対する令和6年度実績値について P.28~34
【資料4】令和7年度障がい小委員会全体工程表 P.35
資料の説明は以上となります。
(委員長)
それでは議事に移ります。
議題1 報告 市の実施計画の評価結果の評価についてです。
事務局より説明をお願いします。
(事務局)
では3ページ目、資料1につきまして、市の実施計画の評価結果の評価について報告させていただきます。
1.当初の評価結果の評価について、委員の皆様に①推進会議の評価のとおりとする。②推進会議の評価のとおりとする。(目標数値には達しているが、取組に関して見直しが必要である。意見については「進捗状況評価報告書」のとおり。)③推進会議の評価のとおりとする。(目標数値には達していないが、取組に推進がみられる。意見については「進捗状況評価報告書」のとおり。)④推進会議の評価のとおりとする。(目標数値との乖離が大きく、取組に関して見直しが必要である。意見については「進捗状況評価報告書」のとおり。)⑤推進会議の評価と異なる評価とする。(意見については「進捗状況評価報告書」のとおり)の5段階で評価の依頼をさせていただきました。
2.評価結果の評価のとりまとめについて、5段階の評価ですが、同じような表現が多く評価が分かりづらい内容でありました。今までの評価区分を整理しますと、評価の見直しが必要なのか、不要なのか、意見がありなのか、なしなのかであり、これらを表にまとめさせていただきますと、見直しが不要で意見なしが①、見直しが不要で意見ありが②③④、見直しが必要で意見ありが⑤、となりました。こちらについて委員の皆様に御意見をいただいた結果を踏まえて、②から④について特に分かりづらい部分があったということで、3.評価結果の評価の整理について、当初は5段階での評価だったところを、3段階に変更できないか、ということを御提案させていただきますとともに、審議いただければと思います。
整理方法についてですが、「①を選択、意見なし」が①、「①を選択、意見あり」若しくは「②、③、④を選択、意見の中で目標数値への不達の表現なし」が②、「①~⑤を選択、意見の中で目標数値への不達の表現あり」が⑤、というように整理させていただき、障がい小委員会では②が16件、⑤が2件という結果になりました。
4.今後の評価結果の評価について、今回評価結果の評価を5段階で細分化させていただきましたが、②から④の差異の判断がつきにくいと判断し、今後は3段階で評価結果の評価を行いたいと考えます。イメージといたしましては、評価の見直しが要なのか不要なのか、意見の有無というところで3段階に整理をさせていただきたいと思います。
ただし、事前に委員長に相談させていただく中で、当初の評価結果の評価の②③④は、③と④で目標数値に達していないという面で、似通った部分がありますが、②の目標数値には達しているが、取組に関して見直しが必要である、③の目標数値には達していないが、取組に推進がみられる、というのは、ある程度の差異があるので、②と③は評価を分けたほうがいいのではないか、という意見をいただきました。
事務局といたしましては、意見をいただくというところが今回評価の評価で取り入れさせていただいているところですので、どのような評価も意見としていただけますことから、評価の方法について3段階で整理をさせていただければと思います。
現在各小委員会と市民福祉推進委員会に、評価を5段階で依頼しておりますため、今後、第2回を迎える各小委員会と市民福祉推進委員会でも同じように、審議をいただければと考えております。
続いて5ページ目、5.委員会等の意見の次期実施計画への反映について①、実際にどのような形で意見を反映させていただくのか、説明させていただきます。
地域共生社会推進会議及び全ての委員会・小委員会からの評価結果の評価が終わった段階で、各担当課に委員会等からの意見のとりまとめ結果を付して、次期実施計画の作成を依頼します。この際に、次ページ以降のように委員会等からの意見を受けて、対応の有無及び対応に対する考えを回答したチェックシートを作成したいと考えています。
参考として取組No.1-1-1について、重点取組として「福祉のつなぐシート登録システムの民間事業者等への拡大の推進」を掲げており、目標(値)を令和6年度が15事業者以上、令和7年度が25事業者以上、令和8年度が30事業者以上とさせていただいています。
これに対して実績(値)では登録事業者を17事業者に増やしたというところで、「A:進捗している」という評価をしております。こちらについて、6ページ目、5.委員会等の意見の次期実施計画への反映について②を御覧ください。
仮に評価は、「②推進会議の評価のとおりとする。(目標数値には達しているが、取組に関して見直しが必要である。意見については「進捗状況評価報告書」のとおり。)」とした場合、当取組No.に対する意見として、「目標(値)が単年度の数値目標なのか、累積での数値目標なのかを統一すべきではないか。」という意見をいただいたといたします。
こちらを受けまして、7ページ目、5.委員会等の意見の次期実施計画への反映について③では、先ほどの目標(値)は令和6年度は15事業者以上、令和7年度は25事業者以上、令和8年度は30事業者以上とさせていただいておりましたが、次期実施計画では、仮定で目標(値)を令和7年度は10事業者以上、令和8年度は10事業者以上、令和9年度は10事業者以上、と単年度での目標(値)に設定させていただくことで、他の取組No.と齟齬がないように変更をさせていただいたものとしております。
続きまして、8ページ目はチェックシートとなっております。先ほどの事業が進捗する中で、事業概要について追加で行う事業が出てきた場合に、①事業概要を変更した部分、目標(値)について変更した場合に、③目標(値)を変更した部分、というようにまず変更の有無をチェックをし、何に基づいて変更したのかという部分で、意見等有り・変更理由有り、意見等無くても、事務局として事業の進捗に伴って変更をした、というところで変更の有無とそれに関する理由をチェックシートの中で書いていければと思っております。
なお②に該当する事業(取組)内容や成果(活動)指標については、原則、経年での進捗を評価することから、追加は必要最低限としてください、と担当課に依頼をしたいと思っております。
9ページ目はどのような理由で変更をしたのかを記載するシートとなっています。例えば委員会等からの意見を受けて事業概要を変更した、事業(取組)の進捗により事業概要を変更した、今回でいうと③目標(値)を委員会等からの意見を受け、累積の目標(値)から、単年度の目標(値)に変更した、というように、いただいた意見を受けて変更しているというものを整理し、チェックシートとして取りまとめたいと思っております。
こちらにつきましては、第3回小委員会にて令和7年度の実施計画が完成したものを委員の皆様に報告させていただくときに、こちらのチェックシートも付して、皆様に回答させていただければと思います。
説明は以上となります。
(委員長)
事務局から市の実施計画の評価結果の評価について報告がありましたが、意見等ございますでしょうか。当初5段階の評価だったものが、3段階に整理したいというお話でした。
(委員)
資料4ページ目の(1)評価結果の評価区分の整理について、評価の見直し不要、見直し要、意見なし、意見ありで、マトリックスを組んでいるので、評価結果の評価は4種類出てくるのが普通の考えだと思いますが、見直し要で意見なしの部分を、斜線でなしとしているのは、いかがでしょうか。
今回に至っては、評価の見直し要で意見なしの部分を、令和6年度においては該当がなかったということだけであって、今後において、無条件に意見はないが見直しが必要ということはあり得るかと思います。見直し要で意見なしは出てくる率や数でいうと今後は少ないと思いますが、そもそも除外しているというのは、マトリックスを組んでる意味があるのか、と考えます。
(事務局)
評価を見直すか見直さないかについて、意見なく評価の見直しが要というのは、考えにくいのではないかと思います。こういう理由があるから評価を見直すべきではないか、というのがあるべきであろうと考えますので、評価の見直しが必要であれば、委員の皆様から御意見をいただけるものではないか、と考えております。
(委員)
明らかにこれは何も言うまでもなく評価の見直し要ということが可能性としてはあり得るので、評価の見直し要で意見なしを、あえてなしにするというのは、特にしなくてもいいのではないかと思います。
(事務局)
今回評価の項目が多すぎて、分かりにくいということがあったので、事務局としてはなるべく簡略化したいと思っております。仰るとおり、クロス表にあるものが、評価の段階としてないのは不自然だろうという意見はごもっともですが、評価の見直しが必要ということであれば、意見を付していただきたいと思いますので、御理解いただけますとありがたいです。
(委員長)
ありがとうございます。他に御意見等ありますでしょうか。
(委員)
当初5段階の評価だったものが、3段階の評価に変わるということで、3段階というのが早くて分からなかったのですが、今回5段階の①だったものが、①にあたり、②③④だったものが②にあたりますか。意見がなく、評価の見直しが不要というのが1つで、あと2つは何になりますか。
(事務局)
今回5段階だった①を選択し意見なしが①とし、①を選択し意見ありと、②③④を選択し意見の中で目標数値への不達の表現なしが②とし、①~⑤を選択し、意見の中で目標数値への不達表現があるものを⑤として整理しました。
今後の評価結果の評価については、②③④の差異の判断が付きにくいと判断し、次年度以降は3段階で評価をしたいと考え、①が評価の見直し不要で意見なし、②が評価の見直し不要で意見あり、③が評価の見直し要で意見ありの3段階となります。
(委員)
ありがとうございます。
(委員長)
他に御意見等ありますでしょうか。
それでは、次の議事に移ります。
議題2 審議 実施計画の障がい小委員会における評価についてです。事務局より説明をお願いします。
(事務局)
10ページ目、資料2につきまして、実施計画の障がい小委員会における評価について説明させていただきます。
障がい小委員会としては、皆様から57件という非常に多くの御意見をいただきまして、先ほど申し上げました3段階のうち、①の評価はなく、②と⑤の評価に整理をさせていただいております。
例えば1-4-2について、①が2件、②が1件、③が2件、⑤が1件というように、皆様には非常に細かく見ていただいており、このように評価に差がある中で、どのように整理をしようかと検討し、先ほど申し上げた3段階で整理させていただきました。
12ページ以降に、②と⑤がどのような形で整理をさせていただいたのか、皆様からいただいた意見を記載させていただいております。今後、報告書としてまとめさせていただく際に、委員会等からの評価という部分が当初の想定では入れておりませんでしたので、実際にこれが①なのか②なのか等々わからないということがございましたので、当初お示ししたものに追記をさせていただき、施策に対して委員会等からの評価ということで、何番の評価をいただいているのか、それについてどういった意見をいただいているのか、ということを整理させていただいたものとなります。
障がい小委員会では、57件の御意見をいただいておりまして、それぞれ基本目標ごとにシートを分け、12ページ目が基本目標1、13ページ目が基本目標2、14ページ目が基本目標3、15ページ目が基本目標4、4-11-2は「⑤推進会議の評価と異なる評価とする。」という評価をいただいています。
4-11-2ですが、推進会議の評価ではA評価とさせていただいておりました。委員会等からの意見では、「C評価が妥当ではないか。地域自立支援協議会では入浴以外にも地域課題が複数挙げられているため、そちらに対しての手立ても同時並行的に進めるべき進めるべきであると。」という御意見をいただいたため、⑤の評価とさせていただきました。
また16ページが基本目標5になりますが、5-6-2についても推進会議ではA評価とさせていただいておりましたが、委員会等からの意見では、「この手の異業種連携は成果が見えてくるまで時間が掛かるという傾向にあるため、なかなか評価が上がりにくいことは否めない。もし核となる人物への接触などを実績として行っているのならば、Cに変更ということでも良いのではないかと思われる。」という意見や、「交流機会の概念や内容にもよるが、地域自立支援協議会には主任介護支援専門員連絡会から委員が派遣されており、毎回地域課題について検討を行っているため、BからC評価でも良いのではないか。」という御意見をいただきましたので、⑤の評価とさせていただきました。このような形で、委員の皆様からいただいた御意見を整理させていただきました。
次のページから、実際の報告書の形式について、説明させていただきます。
20ページ目に障がい小委員会として実施計画の評価結果をどのように評価したかというのを整理させていただいております。
②の推進会議の評価のとおりとする。また⑤の推進会議の評価と異なる評価とする。という部分で、該当の取組No.を記載をさせていただいております。
先ほど5段階の評価を3段階に整理させていただきたいと申しましたが、資料の20ページ目の報告書の中で①から⑤の5段階で表現させていただいているところを、本日審議いただいた内容に基づいて、最終的には3段階の評価に整理させていただければと思っております。
21ページ目以降に、先ほど皆様に御確認いただいた意見を記載し、評価報告書ということで整理させていただければと思っております。
説明は以上となります。
(委員長)
事務局から実施計画の障がい小委員会における評価について説明がありましたが、異議はございませんでしょうか。
3段階の評価の記載方法としては、例えば推進会議の評価のとおりにする意見あり、意見なし、のような記載となりますでしょうか。
(事務局)
評価結果の評価区分の文言といたしましては、先ほどの資料1で説明をさせていただいた、「推進会議の評価のとおりとする」、「推進会議の評価のとおりとする・意見あり」、「推進会議の評価と異なる評価とする・意見あり」、の3つに整理をさせていただければと考えております。
(委員長)
わかりました。個人的には、「意見あり」という文言を、何かいい表現はないのかと思います。
(事務局)
例えばですが、当初示していたものに「意見については報告書のとおり」という表現がありましたので、ここをピックアップさせていただいて、報告書に使わせていただくという形でもよろしいでしょうか。
(委員長)
そうですね。意見あり、意見なしという表現よりも、「意見については報告書のとおり」というほうがいいと思います。
(事務局)
わかりました。それでは今後、表現方法も含めて各小委員会で諮らせていただいて、最終的に市民福祉推進委員会の中で、どちらが良いのか、諮らせていただければと思います。
(委員長)
事務局から実施計画の障がい小委員会における評価について説明がありましたが、異議はございませんでしょうか。
(異議無し)
(委員長)
異議無しと認められましたので、議題通り決定いたしました。
それでは、次の議事に移ります。
議題3 報告 狛江市第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画サービス見込量(目標値)に対する令和6年度実績値についてです。事務局より説明をお願いします。
(事務局)
資料の28ページ目、狛江市第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画サービス見込量(目標値)に対する、令和6年度実績値について報告いたします。
障がい福祉サービスの見込量の推計につきましては、令和6年度から令和8年度までの3年間について、令和5年度までの実績をもとに、今後の利用量や実人数を見込んだものです。
令和6年度の実績値をまとめましたので主なところを御説明いたします。
28ページのア 福祉施設の入所者の地域生活への移行についてです。こちらは令和4年度の施設入所者の6%以上という数値になりまして、令和4年度末の施設入所者数が40人となっておりますので、こちらの6%として、3人以上を目標値に掲げております。地域移行は現在取り組んでいるところではありますが、福祉施設の入所者に関する地域移行としては令和6年度の実績は0人となっております。
イ 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築につきましては、令和6年度は会議体の設置には至っておりません。ただ、会議体を設置していませんが関係者の皆様に御協力いただきまして、今後設置できるよう協議を進めているところでございます。
ウ 地域生活支援拠点の設置につきましては、計画策定時にはまだ設置まで至っておりませんので設置を目標に掲げております。令和6年11月に重度の方も住むことができるグループホームの設置が完了しましたので、結果としましては設置になっております。
ただ国から示されている機能については4つございますが、いずれもまだ整備は十分とは言えません。令和7年度においても、地域生活支援拠点の機能の整備に取り組んで参りたいと思っています。
エ 福祉施設から一般就労への移行等につきましては、目標が41人以上に対して令和6年度の実績としては50人となっており、達成できております。
オ 障がい児支援の提供体制の整備等につきましては、医療的コーディネーターの配置をしておりますので1人としております。
カ 相談支援体制の充実・強化等につきましても、先ほどの拠点と同じように、令和6年11月以降設置できております。
キ 障がい福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築につきまして、基幹相談支援センターについては研修を実施しておりますが、拠点については今後実施を検討して参りたいと思っています。
続いて、29ページ以降を御覧ください。
29ページ以降は実際の障がい福祉サービスのメニューごとの利用量の実績になります。
最初の訪問系サービスにつきましては、全体としては増加傾向となっております。特に重度訪問介護については大きく増加しており、こちらはお一人の方の利用状況によるところが大きいものですので、利用実人数としては減っていますが、延利用量としては増加となっております。
30ページの日中活動系のサービスにつきまして、主に通所されるサービスの利用量になり、全体的に若干減少傾向となっております。特に31ページの短期入所の福祉型は減少しており、医療型が増加しているという状況になっております。短期入所の医療型については、世田谷区の利用事業所の利用が大きいものと分析しております。
32ページの居住系サービスにつきましては、グループホームが年々増加傾向となっております。こちらは全国的な傾向としてグループホームの入居のニーズが高まっていると認識しております。また先ほどの拠点の位置付けを持ったグループホームの整備というところも一つの要因として考えております。
4の相談支援については、概ね横ばいとなっております。令和6年5月に相談支援事業所が一つ新たに追加しておりますが、件数としては、ほぼ横ばいという状況になっております。
33ページが地域生活支援事業の見込量になります。こちらも前年と同様に、事業を実施しております。移動支援事業が、表上では令和3年度から年々増加しておりますが、こちらは年々増加というよりは、コロナ禍前の令和元年の延利用量が9,820時間でしたので、コロナ禍以降徐々に利用が戻ってきている、という状況です。
34ページが障がい児のサービスになります。こちらも例年の狛江市の傾向では、児童発達支援が年々減少傾向になっております。逆に放課後等デイサービスについては年々増加傾向になっており、引き続き、放課後等デイサービスについては増加傾向が続くものと分析しております。2の障がい児の相談支援については、若干増加傾向となっております。
以上、簡単ではございますが、見込量の報告とさせていただきます。
(委員長)
事務局から狛江市第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画サービス見込量(目標値)に対する令和6年度実績値について報告がありましたが、御意見等ございますでしょうか。
(委員)
28ページ目のイ 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築ですが、長く未設置のままだと思いますが、未設置になっている一番の理由がありましたら、教えてください。
(事務局)
イ 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築については、ずっと未設置になっております。こちらは、なかなか市で取組みを進められなかった理由としましては、市の内部の調整や関係機関の方との調整をなかなか進めることができませんでした。
令和6年度の小委員会で御意見をいただて以降、現在、関係者の方にも御協力をいただき、設置に向けて調整をしております。今秋の令和8年度の予算要求時には、委員会の設置について庁内で整理をし、関係機関の皆様の御意見をいただきながら、設置に向けた具体的な取組みを進める予定でございます。
(委員長)
他に御意見等いかがでしょうか。
30ページ目の就労移行支援について、今は雇用率の上昇や、除外率が下がっている状況があるので増えていると思いますが、狛江市は事業所設置はないのでしょうか。
(事務局)
就労移行支援について実績としては、令和6年度は前年度比でいうと若干減っているところです。一般就労への人数は非常に増えていて、ニーズも非常に高い分野です。特に30ページの日中活動系サービスでいう、就労継続支援A型、B型、就労定着支援が就労のニーズに対応するサービスになっておりますので、感覚ではニーズ的にもっと数字が伸びているのかと感じていたのですが、今回集計してみると延利用量としてはそこまで伸びてはいないのですが、非常にニーズは高いメニューだと認識しております。
(委員長)
ニーズは高いけど利用量が少なかったのは、利用した人が就職するので、量としては減ってくるということですか。
(事務局)
そういう就労継続支援のB型を使っている方が一般就労につながる事例はあると思いますが、そこまでステップアップというよりは、市民の方と話をしていくと、就労に対する意欲は非常に高い方が多いのですが、給付費として見たときに、そこまで伸びがなかったので、今後も注視して動向はチェックしていきたいと思っています。
(委員長)
ありがとうございます。
就労選択支援が10月から始まると思いますが、延利用量は30人ですか。
(事務局)
こちらはあくまで想定となりまして、今後実際に始めてみないとなかなか見込みが難しいと思っています。
(委員長)
基本的には初年度特別支援学校の新卒と、B型を使っている人の希望者だけですよね。実質的には特別支援学校の、新規の卒業生しかいないと思いますが、狛江市としては30人くらいでしょうか。
(事務局)
そうなります。卒業生だけではそこまでの人数はいないと思いますが、それ以外にも希望される方はいると思いますので、プラスアルファの人数も含んでおります。
(委員長)
わかりました。ありがとうございます。
他に何か御質問等ございますでしょうか。
(委員)
意見になりますが、地域生活支援拠点ができたことが、よかったと思っています。緊急的にショートステイのようなところが、ハードウェア的になかなかなかったりする問題もありますが、もう一つはその拠点にコーディネーターを配置すると加算がつくというのが令和6年の報酬改定でできたのですが、それはどういう仕組みかというと計画相談対象や障がい児相談の対象の人が100人いると、その100人分が別の人に対するコーディネーターのお金に使えるという加算になっています。狛江は月で動いているケースが、ほぼ200人くらいというのがわかり、拠点コーディネーターがフルで、もし動けるとすれば、2人しか配置できないということが数字上わかったので、ハードウェア的になかなか動きが厳しければ、そのコーディネーターを複数人配置したりして、例えば緊急時の場合は使いましょうとか、親御さんの不安なところがあれば、事前にこういうふうに取り決めておきましょう、というふうに地域の中でいろいろ調整していくことがコーディネーターの役割になると思っています。相談支援の計画相談の月々の人数で平均利用者数と、障がい児の平均利用者数を足し込めば200人くらいということがわかったので、そうなると100人分の請求で1人のコーディネーターが置けるので、狛江市だと2人が上限ということがわかったのが、今回の改めての発見でした。拠点自体をどうやって地域に浸透していくのかとか、どう上手く活用していくのか、拠点コーディネーターにかかってくるのだと思っていたのですが、結構厳しいという印象で、2人は配置できないのではないか、1人くらいの配置になるのかと思いました。
以上です。
(委員長)
コーディネーターを配置する計画はあるのですか。
(事務局)
具体的に狛江市で何名という計画はございません。ただ国からその拠点の機能を整備していくにあたっては、中核的な存在としてコーディネーターが位置付けられています。狛江市ももちろん設置を否定するものではないのですが、以前も話題になった緊急時の対応や、体験の場の提供、この辺りが東委員がおっしゃったハード面の課題というのはまさにこの2つです。短期入所がないとやはり緊急時の対応が難しいですし、グループホームにも空きがなければ体験の利用は難しいというところが、狛江市の地域課題としてあり、その辺りのハード面の課題がなかなか見通せないと、コーディネーターの方を配置し、緊急時の対応や名簿の登録をしても、なかなか有効に機能できないと認識していて、現状は配置はしていないところです。
(委員長)
物理的なものに関しては、今後どうしていくのですか。
(事務局)
現在、重度の方を受け入れるグループホームに短期入所の開設も予定しており、まだ実際には開設はできていないのですが、短期入所の数が増えていかないとなかなか難しく、公設ということもなかなか現実的ではないです。特別区で直営公設で短期入所をやっているところもありますが、現状、狛江市では公設は難しいとなると、グループホームの空きを使った短期入所のお声掛けはしているのですが、現実的にはなかなか難しいところがあり、有効な解決策は打てておりません。
ただ、そうすると何もできないということになるので、ちょっと話が外れてしまうかもしれないのですが、入浴サービスを今、試行的に実施しているところがありますので、泊まれないけれどもお風呂に入れるだとか、泊まれないけれども食事の提供ができる、そういったところで補完していくのも、一つの拠点の機能としていえるのではないかと思っています。
そういった試行は取り組んでいきますが、根本的な解決ではやはり短期入所をもっと増やすことが必要になってくると思っています。
(委員長)
わかりました。ありがとうございました。
それでは、次の議事に移ります。
議題4 その他 次回の会議日程についてです。事務局より説明をお願いします。
(事務局)
資料4につきまして、令和7年度障がい小委員会全体工程表の説明をさせていただきます。
前回、計画策定のスケジュールを簡単に説明させていただきましたが、来週6月16日に計画改定の事業者選定審査会を実施させていただく予定となっておりまして、現在のところ2社から手上げがございました。そちらの選定審査会を実施させていただき、点数を満たせばいずれかの業者と委託契約を結んで、計画策定に取り組められればと思っております。
その後、10月17日に先ほど説明させていただいたとおり、進捗管理報告書を意見に対する各担当課からの回答も含めたものを報告させていただき、また今回いただいた御意見をもとに策定した令和7年度の実施計画の策定についても報告させていただければと思います。
また、市民意識調査の調査票にこのような質問が必要ではないか、というような形で御意見をいただければと思っております。次回10月17日原則会場参加で開催させていただければと思っております。
以上となります。
(委員長)
事務局よりその他について説明がありました。何か御意見等ございますでしょうか。
(特になし)
(委員長)
それでは、本日準備しておりました議題はすべて終了しましたが、その他各委員から、何かございますか。
(事務局)
1点失礼します。
議題2での「委員会等からの意見」において、御質問をいただいておりますので、御説明いたします。
14ページ、基本目標3:社会参加を進めるシステムづくり No.1施策3-1-1「聞こえが困難なこと等によりコミュニケーション障がいのある市民へのユニバーサルコミュニケーション支援の推進」について、ランニングコストについて御質問をいただきました。2社より資料をいただいておりましたので、説明させていただきます。2社とも透明ディスプレイを用いた機器であり、A社の料金体系といたしまして、年間レンタルの場合、初期費用が20万円で、年間費用が98万円、いずれも税抜き。購入の場合、初年度が145万円で、2年目以降が20万円、いずれも税抜きとなります。
機能といたしましては、透明ディスプレイ越しに言語翻訳をして表示ができ、翻訳言語としては13言語に対応しています。また、難聴の方などの対応のために、スタッフは音声で、難聴者の方はキーボードで入力をして会話ができる機能があるということでした。
続きましてB社について、こちらは初期費用が10万円で、月額のサービス基本料2万円、ライセンス料が2万円、端末レンタル料が6,250円で、1ライセンスに1台という限られた形で、最初のランニングコストですと46,250円が毎月かかり、行政用語に対応した機械通訳や、やさしい日本語対応、ビデオ通話や、ログ機能ということで、どのような会話をしたのかが記録できたり、対応言語は31言語になります。
これらの導入は令和7年度予算では実現しませんでした。
以上報告とさせていただきます。
(委員長)
ありがとうございました。2社のどちらがいい等ございますか。
(事務局)
多言語対応もしながら、難聴の方や言語障がいがある方も、iPadのようなタブレットを使用してキーボード入力を行い、ディスプレイで表示して会話ができるとのことです。
このディスプレイがある程度の費用が発生しますので、端末だけで事が足りるのではないかということもあり、今のところ結論が出ていないという状況になります。
(委員)
A社について、キーボードで入力とのことですが、タブレットの手書きモード等でも入力はできるのでしょうか。
キーボードの入力が苦手な人もいるので、手書きモードもあればいいと思いました。また難聴者だったら実際に発話される方もいるので、聞こえない人が声を出すモードや、それを拾うモードもあるのでしょうか。
(事務局)
資料ではキーボードで入力と記載されており、手書きモードに対応しているかどうか回答できませんので、こちらについては業者に問合わせをさせていただければと思います。
また、今年の10月から市役所の窓口で、遠隔手話サービスを始める予定です。現状水曜日の午前中のみ手話ができる方を配置していますが、その時間以外に耳の聞こえない方が市役所で手続きをするときは、御自身で手話通訳員を予約していただいているのですが、10月からQRコードを窓口に置くようにして、その利用者のスマートフォンでQRコード読み取ると、遠隔手話サービスにつながって、御自身で手話通訳員の配置をあらかじめしなくても、市役所にお越しいただければ、遠隔手話で窓口対応ができるようになります。市役所だけではなく、保育園や学童、特に学校は保護者の方が行くことが多いので、そういったところにもQRコードを置いて、対応できるように今準備していますので、また御報告できればと思います。
(委員)
その対応してくれる手話通訳の方は、市内で活動する通訳の方が、連絡が来たら出られる人が出る、というような形になるのでしょうか。
(事務局)
手話通訳の方は市内の方ではなく、事業所に所属している手話通訳員となります。事業者と契約する遠隔手話サービスはすでに東京都では取組みが進んでいて、狛江市でも法人と契約をして、遠隔手話サービスを始めたいと思っています。
(委員長)
手話はモニターに映すイメージでしょうか。
(事務局)
はい。テレビ電話と同じように、モニターに手話通訳の方が映り、市の職員が話していることは電話を通じて先方に都度聞こえていて、手話で窓口にいらっしゃっている方のスマートフォンから通訳していただくという形になります。
(委員)
電話リレーサービスとは若干違いますか。
(事務局)
電話リレーサービスは事前登録が必要になりますので、電話リレーサービスとは異なり、事前に登録の必要がないものとなります。
(委員長)
また導入されたら、報告をお願いします。
それでは、本日準備しておりました議題はすべて終了しましたが、その他各委員から、何かございますか。
(特になし)
(委員長)
他にないようでしたら、本日はこれにて閉会します。
本日はありがとうございました。
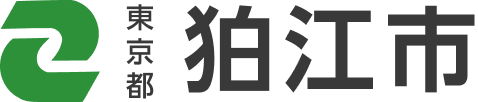
 印刷
印刷
 戻る
戻る
 ページの先頭
ページの先頭