令和7年度 第5回 狛江市子ども・若者・子育て会議(令和7年8月5日開催)
|
1 開催日時 |
令和7年8月5日(火曜日) 午後6時30分~午後8時20分 |
|
2 開催場所 |
防災センター302・303会議室 |
|
3 出席者 |
委員 加藤会長、市川副会長、馬場委員、梶川委員、富永委員、毛塚委員、平見委員、大塚(直)委員、大塚(隆)委員、稲葉委員、豊田委員、山本委員
事務局 冨田子ども家庭部長、山口子ども若者政策課長、岡本子ども家庭課長、中村子ども発達支援課長(兼)教育部教育支援課長、三宅児童育成課長、松倉教育部理事(兼)指導室長、西村企画政策係長、梶山企画政策係主事
|
|
4 欠席者 |
細谷委員、岸田委員、小西委員、藤具委員 |
|
5 傍聴者 |
3名 |
|
6 議事内容 |
|
|
7 配布資料 |
|
|
8 会議の結果 |
|
◆議題1 狛江市子どもの権利条例(案)について
〇事務局より資料1、資料2についての説明
【委員】
会議前に共有していただいた委員からの修正案を見て、同感できる部分が多数あった。それらについて補足をお願いしたい。
【委員】
前回の会議資料1-1で、業務委託報告書があったが、その中で提案されている内容を一件一件見ながら、条例案や逐条解説の中に反映されているかどうかの確認作業を行った次第である。
資料2の前文「他の子と比べることなく一人ひとりの子どもである『私』を見て尊重して欲しいです」という部分について、言及すべきだと報告書の24ページに書かれていたため、記載した。
先程事務局からも話があった資料2の第3条の解説に記載されている「子どもには大人と等しい権利があることを知ることが大切です」の文章の最後が「必要です」となっており、権利を保障することに対するバーターとして「あなたの義務を守りなさい」ということは私は反対で、本人が最終的には考えることだと思う。
ここの記載は以前から様々な意見がある中で、おそらく書きたいという希望もあるのだと思う。残す場合は、もう少し書き方を考えた方が良いと思った。
第4条の解説の「不当に比べられたり」という表現について、不当とは何かという話がワークショップ等、どこかで出た気がしており、どのような場合かについて定義付けられると良いと思う。比べることがまったくの悪だとは思っていないし、場合によっては必要だとも思っている。努力や頑張った成果を正当に評価することは必要である。かけっこで一等賞になったら、「一等賞です」とする場面はどうしても必要だと思っている。比べることがすべて悪だとは思っていないため、不当な場合とそうではない場合があるのではないかと思っている。できれば「不当に」という部分を、もう少しかみ砕いて書ければ良いと思う。
業務委託報告書の25ページにインクルーシブについて言及されており、私の個人的な考えでは、インクルーシブ教育が現時点でそんなに定評を得ていると思っておらず、逐条解説に入れるのは知識がないこともあり、できなかったため、若干触れる程度の記述となっている。
第7条の子どもの最善の利益については、業務委託報告書の20ページに、子どもにとって最も良いことと、大人が考える子どもにとって最も良いことは違い、子どもの最大の利益について言及すべきだということが書かれていた。条文本文に記載がなかったため、記載した。
第6条の解説の暴力については、業務委託報告書の23ページに、心理的暴力や社会的暴力が含まれることや、具体的に記載してしまうと暴力を受けた子どもへの二次被害につながってしまうことに注意し、配慮した記載が必要であると書いてある。心理的暴力、社会的暴力については、言葉の意味が若干揺れているのではないかと思い、心理的暴力については少し記載したが、どういうことが社会的暴力なのか定義付けたり、例を挙げたりすることが難しかった。
意見表明を保障するためのプロセスについて、業務委託報告書の17ページに記載されているユニセフの報告書の地方レベルでの包摂的な子ども参加の研究内容を読み、少し詳細に記載されていたが、全部記載するわけにもいかないため、①年齢・成長の度合いに応じた事前説明がなされること、②意見表明の機会が確保されること、③子どもの意見を正当に重視し、子どもの意見がどの程度重視されたかに関する情報を提供すること、という3つのプロセスを繰り返し行うことの必要性について記載した。
子どもの居場所については、小学生世代と中高生世代は違う面があり、ある程度ユース世代に特化した記述が必要であることが報告書の19ページに書いてあった。そのような記述があった方が良いと思い、資料2の第16条に記載した。
居場所については業務委託報告書の21ページに、子どもの視点で居場所の環境やルールについて検討すべきだということや、他方で地域から見れば、地域づくりそのものでもあり、様々な関係者がその場所を使用するため、大人も子どもも共に気持ち良く使えるよう、話し合いの場を仕組みとして設ける必要があるのではないかと書かれ、そうだと思った。公共の場の使用方法やルールとは地域づくりそのものだという指摘については、確かに子どもだけの空間ではなく、幅広い視点から考えていく必要があることや、子どもだけの視点に偏って考えられることではないのだと納得した。
第17条の解説の中に「権利には、相互尊重の原則があり」と書かれており、間違ってはいないと思うが、条例や逐条解説に入れる必要はないと思っている。現状で大人が十分に子どもの権利を保障していないという認識があるからこそ、条例を作ろうとしているため、逐条解説の中にそもそも子どもに義務を負わせるというような、義務を再確認させるといった記載を盛り込むことは、私としては反対である。
これを見ると狛江の子どもが他の人の意見を大切にしていないかのように見えるが、全般的には良い子が多いという認識であり、多数派に向けたメッセージとして修正して良いのではないかと思った。
第18条の相談体制の解説について「市では既に子どもに関する各種相談窓口を設置しています」と書かれているが、具体的なものを書き、相談窓口があることを広報することが権利救済につながると思う。また、解説の中で「相談窓口のみでは解決が困難なものについて」と書かれているが、相談窓口はあくまでも相談窓口であり、実行力がないと思う。助言のみでは解決が困難というのは、関係機関との連携強化に努めることなのだと思う。権利救済機関を設けない以上、具体的にどのように関係機関と連携を強化していくかの検討がないと、ただ言っているだけとなってしまうと思う。
第20条については、業務委託報告書の24ページに子どもの権利の普及啓発に努めるという記述を入れるべきだという話があった。また、付則の第2項に「この条例の運用の実績等を勘案し」と書いてあり、子どもの権利が実際に保障されているのかどうかがポイントと思ったため、子どもの権利の保障の状況は入れた方が良いのではないかと思った。
子どもの権利救済機関を設けないことについての説明が少ないと思い、解説に少し記載した。
【委員】
私も今の補足や意見にはとても賛成だが、相互の権利の部分は明文化しておいて良いと思った。狛江の子どもは良い子が多いというのはそうであるが、「人を殺してはいけません」や「人を殴ってはいけません」というごく当たり前のルールだが、原理原則の一番大部分の、相手の権利も守らなければならないということが分からない子どももいるかもしれないため、きちんとそのような部分を一文入れるのは良いと思う。
【委員】
先程の委員の説明に対してはすべて同意見である。今の子どもの相互の権利については、第3条の解説に「自分と同じように、他の人にも同様に権利があることを知り、その権利も同じように大切にすることが必要です」と書かれており、これで良い思う。
第17条の解説の一番最後にも同じようなことが書かれているが、第17条は意見表明権についてであるため、どのような意図で入れているのか教えて欲しい。
【事務局】
今までの会議での議論を踏まえて入れているものだが、消しても良いと思う。
【会長】
意見表明権のところにあるため、若干の違和感があるのかもしれない。
【委員】
「こういうことを念頭に置いて発言しなさい」という抑圧的なものを感じた。
【会長】
良い子の権利だけではなく、悪い子の権利も守らなければならないというところも念頭に入れ、ここの文章を残すのか、削除するか考える必要がある。
【委員】
第3条のところは「大切です」という言い切りの形で入れてあって良いと思う。また、第17条の意見表明のところは、外した方が良いと思う。
そして、人に対して悪いことを言ったら駄目なのかということだが、私は言っても良いと思う。言った後に、皆で「今のはどういうこと?」や「どうしてそう思うの?」ということを友人同士で話し合うということに発展していくと思う。表明ができないということは、これを念頭に置いて、これをクリアしないと表明できないという条件がつくように読み取れるため、ない方が良いと思った。
【会長】
書き方にもよると思う。「大切です」と言い切るのと、「○○しなければならない」という言葉で説教臭く言ってしまうと、縛りのようなニュアンスになると思う。
【委員】
「しなければならない」という書き方は、縛りのような印象があるのかもしれない。
【委員】
第17条はそもそも意見表明及び参加・参画の促進で、第2項で市及び施設関係者の役割を規定している。解説の一番最後の文章はそこと照らし合わせ、不要なのではないかと思う。
第3条の解説の最後の部分だが、「まずは、子どもには大人と等しい権利があることを知ることが大切です」の「知る」という主語が誰なのか、「他の人にも同様に権利があることを知り、その権利も同じように大切にすることが必要です」が、誰に向けられたメッセージなのかによって書き方が変わるのではないかと思う。
子どもに向けてというよりも、権利は相互に尊重となければいけないという一般原則としての書きぶりで良いのではないかと思った。
【会長】
主語はどのようにしたら良さそうか。
【委員】
「子どもが」ということが明記されたり、暗示されたりするのではなく、すべての人がそもそも、というところを書ければ良いのではないかと思う。
【委員】
ここの主語は子どもではないのか。
【会長】
「その上で」という部分を「すべての人が」に切り替えてはどうか。子どもだけに押し付けてしまうように読めてしまうことに抵抗があるのではないか。「すべての人は、自分と同じように、他の人にも同様に」という文にすると違和感はあるか。ニュアンス的には子どもだけではなく、一般原則としての確認がしたいということである。
【委員】
元々の原文の主旨は、子どもに向けたメッセージで「自分にも権利があり、他の人にもある」というものだと思う。主語を広げてしまうと、意味が変わってしまう。
【会長】
「自分の権利を主張するならば、他の人の権利も守ろう」と捉えられてしまうと意味が違うと思う。
【委員】
この「知る」の主語は子どもに知って欲しいだけではなく、大人も知って欲しいというところが入ってくると思っている。
【会長】
「すべての人が」という言葉が良いと思った。
【会長】
事務局としてはいかがか。
【事務局】
条例としても子どもだけではなく、大人にも知って欲しいという主旨もある。
【会長】
すべての人という捉え方ができるような文章にしてもらうのでいかがか。
【委員】
第4条の解説について、「年齢・性別・国籍・言語・発達・障がいの有無・家庭環境・個性及びそれぞれの特徴等により」という部分に狛江市内に外国にルーツがある方も増えてきているため、宗教や文化のことも入れた方が良いのではないかと思う。
他の自治体だが、宗教によって給食が用意できず、保育園に入れないということもあったため、それを避けるためにもはっきり書いた方が良いのではないかと思う。
【会長】
社会的暴力については何をイメージしているのか。
【委員】
インターネットで調べた限り、社会的行動や原因等によって特定の個人や団体が排除されることを指すと解説しているページと、皆で仲間外れにすることを指すと解説しているページがあり、言葉の定義がまだ定まっていないと思われた。知識があまりないため、もし他の方で分かれば教えて欲しい。
【会長】
イメージ的には差別や偏見ではないか。支配を避けるということが入った方が良いのかと思う。人をコントロールしようとすることが、虐待というか暴力なのだというイメージも出したいと思う。その辺りをどう表現するのかを相談したい。
【委員】
それが心理的暴力の中に組み込んでいる解説等もあったため、それが社会的暴力や社会的DVのように言うべきことなのか、特定の地域に住んでいる人が何かのサービスを受けにくいような制度設計をするとき等、社会的暴力という言葉を使っているものもあったようで、結論としてはよく分からなかった。
【委員】
AIによると、「社会的暴力とは、他者の社会的なつながりや行動を制限する暴力の一形態で、具体的には交友関係を制限したり、外出を制限したり、家族や友人との接触を妨げたりする行為が含まれる」ということである。安全を守るためには必要なときもあるが、親が子どもの交友関係に口を出したり、デートDV等、中高生で付き合っているから、他の男とは遊びに行くなということもすべて社会的暴力に入るのだと思うが、これは書いておいた方が良いと思った。
【委員】
私も調べた限り、社会的暴力とは仕組みを使って排除するようなことが書かれていた。
【会長】
DVの世界は割と社会的暴力という言葉を使うと思う。
【委員】
厚生労働省のページを見て、社会的DVというものがあるということは認識したが、社会的暴力と社会的DVを並べたときに本当に同一の意味なのかどうかも分からない。
【委員】
逆に、社会的暴力という言葉が分かりづらければ、交友関係の制限を不当にしたりする等、具体的に書いていけば良いのではないかと思う。
【会長】
ある意味、社会的暴力、心理的暴力にカッコ書きで例えばのように入れて、大きな項目として社会的暴力、心理的暴力が入っていても良いかと思うがいかがか。
【委員】
文章の中で社会的暴力という言葉を使うのであれば、「本文ではこう定義します」と打ち出した方が良いのではないか。
【委員】
受け取る人の立場によってもニュアンスが違ってしまうような言葉は、なるべく使わない方が良いと思うし、具体的に書いた方が読まれると思う。
【委員】
報告書の中でも、心理的暴力や社会的暴力についても、子どもに分かりやすい表現を記載する必要があることや、具体的に記載してしまうことで傷つけてしまったり、二次被害につながってしまうことに注意して、配慮した記載が必要であることが書かれており、とても難しい。
【会長】
そういうことをしてはいけない、気をつけなければいけないということを分かってもらうためには、具体例を入れておかないと難しい言葉ではうまく伝わらないと思う。
その辺りの書き方は事務局で検討してもらいたい。次に図も決めないといけない。
【委員】
図の補足としてフォントが変わった。また、図が決まり次第、調整して見やすい形にしたいと思う。また、帯が長いものと短いものとあるが、図のスペースが正方形だったため、あまり縦長ではない方が図を大きく配置できると思い、短い帯のものを作った。組み込まれている帯が長いものになると、下の図がとても小さくなってしまう。
【会長】
今の説明も踏まえて、どの図が良いのかをある程度具体的に決めておきたい。
【委員】
帯が長い方が全体的にしっくり来ているように思えるが、確かに図が小さくなるということも考えると捨てがたいと思う。必ずしも長くなくてもおかしくないと思う。
イラストが入ることにより、配置の仕方が変わってくるのかと思う。条例の構成だけを見ると、基本となる権利が中央に来た方が分かりやすいと思ったが、イラストありの方が良いのではないかと思う。
私としてはイラストありで、帯はどちらでも良いと思う。紙が小さければイラストを大きくするために帯を短くしても良いし、紙が大きいのであれば、多少小さくなっても構わないかと思う。
【委員】
私もイラストがあった方が分かりやすく、様々な子どもがいて、皆に当てはまるのだということが伝わり、良いと思う。帯の長さについては、短い方が良いと思う。なぜならば、資料2の9ページを見ると「条例の構成イメージ図」という緑の線が入っているため、帯は短くし、イラストが大きい方が良いと思った。
【会長】
緑の線の下に「以下の図は」と書いてあるため、どちらかで良いのではないかと思うし、色がしつこくなるため、緑は不要かと思う。
【会長】
イメージ図という説明は下でも良いのではないか。図の下に配置して、総則が上に来ると、分かりやすいのではないだろうか。
【委員】
私は一番初めの絵が好きなのだが、緑をなくしてもらうのが良いと思う。図を作成してどれが一押しであるか、ぜひ伺いたい。
【委員】
もともとイラストは様々な意見があると思い、ない前提で作成したが、様々なご意見をいただき、このようなものとなった。
画面で大きくすれば見えるが、A4サイズでここで見たときに、イラストが入ると見えづらく、文字も小さくなってしまうと思う。そのようなことにも配慮すると、シンプルに、イラストなしの方が構成としては分かると思う。ただ、イラストがある方が目を引くというメリットもあり、特にこだわりはない。
【委員】
イラストがあった方が良いと思うし、帯は小さい方が良いと思う。
【会長】
イラスト入りが共通認識でよろしいか。帯についてはいかがか。
【委員】
長い帯にすると、その分文字が小さくなる。図が入るスペース自体が四角形のような形をしている。
【会長】
図の上部にある帯と「以下の図は」から始まる文章をなくし、「この条例の『構成』について図式化したイメージ図です」を下に追加するのはいかがか。
【委員】
私としては初めは小さい旗のイメージだった。長いものであれば、よくある巻物風にした方が良いのかと思う。
【会長】
紫色の第1章の部分を、下の第5章のピンク色に合わせても良いかもしれない。
【委員】
旗にせずシンプルに四角にし、文字を真ん中に持ってきた方が綺麗かもしれない。
【委員】
旗が良いと思う。旗を子どもが持つのはいかがだろうか。
【委員】
第1章がイラストの一部であることを、もう少し分かりやすくした方が良いと思う。目的や定義を掲げているのが第1章であるため、旗にし、子どもが持っているのが良いと思った。
【委員】
子どもが持つのはともかく、棒がついている旗は良いと思う。
【委員】
旗にしないのであればシンプルに、ちょうど「子どもの権利」くらいの幅で、それほど太くなくても良いと思う。いくつか案を作成し、多数決で決定はいかがか。
【会長】
先程の委員の提案でいかがだろうか。事務局に判断をお願いしたい。
【委員】
旗を持つ新たな子どもを入れるのではなく、ここのイラストにいる子どもたちが持っているイメージである。
【委員】
会長が言った、緑の部分をなくし、「以下の図は」のところもなくして下に移動するのは良い案だと思った。緑の「条例の構成イメージ図」という説明と、「以下の図は」から始まる文章が同じことを言っており、第5章のピンク色の下に入れれば分かるため、それが良いのではないだろうか。また、全体の図を可能な限り大きく描けるように工夫することが良いと思った。
【会長】
イラストの案を後で投票する形にしたい。他の部分はいかがか。
【委員】
資料2の「はじめに」の2段落目の最後の方、「子どもの権利条約の認知度は高いとは言えず」と書いてあるが、国が令和5年度に実施した「児童の権利に関する条約の認知度等調査」で、大人の認知度は53%だと思うため、そこを明記しつつ、大人の調査で半数以上という書き方をするのが良いかもしれない。
11ページの前文の解説の一番最後の部分の、「子ども一人ひとりの権利が保障・尊重されるためにも他の人の権利も大切にできる地域づくり」について、「他の人の権利も」ではなく「地域づくり」と書いてあるため「すべての人の権利を大切にできる地域づくり」とする方が良いのではないかと思った。
第2条第5項の施設関係者について、「奉仕活動を行う者」とあるが「奉仕活動」ではなく「ボランティア活動等」でも良いのではないか。解説の方にはボランティア活動と書かれており、現代の書き方に合っているのではないかと思う。
また、解説の中に書かれている施設の定義の「社会教育に関する施設とは」の部分について、中高生の居場所の話が出ており、ティーンズルームを見据えて、図書館や体育施設だけではなく、公民館を入れても良いと思った。
第4条の解説の最後の一文のまとめ方が少し雑と思った。思想の自由についてはここで触れられておらず、冒頭では、「良いところも苦手なところも無理することなく」とある一方で、最後では「得意なことに取り組んだり」となっており、書き方を変えるか、この一文はなくても良いと思う。
第5条の解説の「選択することが難しい場合には、周りの大人等に相談することもできます」という書き方について、選択することが難しい場合に限らず、自己決定とは他者の関与や環境との相互作用によって、その都度行われるものだと思っている。「選択することが難しい場合には」というより、「子ども自身による主体的な選択のためには周りの大人に相談したり、それを実現できる環境の整備を求めることができます」というような書き方でも良いと思う。
【委員】
第4条第1項の「誰かと不当に比べられることなく」で始まっている文に違和感がある。先に個性や多様性が認められ、ありのままの自分でいられることがまず大事であり、比べられることが何かということが、成長の度合い等は個別で、その子なりに成長したらすごいし、だからそこを認めて欲しいということなのではないか。「誰かと不当に比べられることなく」という部分は、最初に来なくても良いと思う。個性や多様性が認められ、自分でいられ、こういう部分においては誰かと比べられない、というような表現になっても良いと思う。
第6条の生きる権利と成長・発達する権利があわせて規定されている部分について、私としては、第5項までは安心・安全にいる状態であり、発達する権利は、先程「なくても良いのでは」と言われていた「得意なことに取り組む」という文章を膨らませれば良いと思う。
自分のやりたいことに挑戦できることが、一つ独立していた方が私は良いと思う。逆に生きる権利の部分はこんなに必要なのか、子どもの権利条約で保障されている部分をどこまで書くのかと思う。
【会長】
第6項が第7条の方に入った方が良いのかもしれない。
【委員】
第7条は意見表明ではないか。
【会長】
第7条には参画も入っている。
【委員】
参加するということだから、参画は意思決定の中には入っていないのではないか。
【委員】
第6条第6項を独立させるのはどうか。
【委員】
自分で自分のことを決める権利と言った方がまだ自然だと思う。
【会長】
第5条に似たようなことが書いてあるため、少し整理していただきたい。
【委員】
第5条の解説には「子どもの成長・発達のためには、子どものやりたいことや興味のあること、学びたいことに挑戦することができ」と書かれている。第6条第6項に「自分のやりたいことに挑戦できる等」があるため、第5条に入れるとすっきりするのではないかと思う。
【会長】
第5条の方が良い気がする。
【委員】
自己決定と成長・発達していく権利は違うと思う。
【委員】
第6条の解説にある「健やかに成長・発達」と書かれている内容と、第6項の成長は違う種類だと思うが、一緒になっていると思う。
【会長】
事務局としてはいかがか。
【事務局】
どうしても被るところは多少あり、全部をしっかり分けることは難しいと考えている。先程話に出たが、自己決定と成長を別の立て付けにしているが、どちらも子どもの成長・発達のためには大事だと考えると被ってしまう。
【委員】
第6項はチャレンジということか。
【会長】
環境が保障されることという意味なのだと思う。こういうことができるような環境を子どもたちに与えましょうということだと思うため、ここも書きぶりだと思う。医療を受けること等と並列になってしまうと、先程意見があったように違和感がある。
「体験できる環境を持つことやそれが保障されること」としたら、同じような文言でも環境が整わないと子どもたちは力を発揮できないというところに落ち着くと思う。
【委員】
第5条とは少しニュアンスが異なると思う。遊びを通して学び合うことや気づき等は大切であり、第6項は挑戦よりも遊びと学び、気づきをできる環境を整えていくという文言で、子どもたちの成長・発達につなげていく方が良いと思う。
【委員】
下に「自由に遊び、学びたいことを学べ」とあるが、「学び」ではないだろうか。「遊び」、「学びたい」と来て、急に「学べ」というのはどうか。
【会長】
環境につなげるのであれば「学ぶ」であろうか。
【委員】
子どもが生きることは、ただ単に生存が保障されることだけでなく、少し情緒的かもしれないが、遊んだり、学ぶことが子どもにとって生きることそのものである。ここに第6項があるのは良いのではないかと思う。先程言っていたように、挑戦できるというよりも、自由に学ぶことに力点があるのが第6条第6項かと思う。
例えば、第6条と第5条が逆になると、少し見え方が変わるのではないか。この順番はどのように決めたのか。
【委員】
そうすると第4条も見直さなければならないのではないかと思う。
【事務局】
順番については命の問題が大事だから最初に持ってくる等、様々な視点があるかと思う。ここでは、アンケートや狛江市の子どもたちの意見が多かったところから、なるべく載せるようにしている。
【委員】
順番に関しては人気投票のランキングではないため、まず生命の安全があり、次にこれがあって、というように、きちんとピラミッドの底辺から積み上げていくような順番はあった方が良いのではないかと思う。
【会長】
子どもたちの意見で、ということは一般の人は見たときに分からない。分かりやすくするには、どこが上位なのかという視点で書いた方が読みやすいかもしれない。
【事務局】
そうすると第6条が一番最初となるのか。
【委員】
全部大事であるが、第6条、第4条、第5条の順番になると思う。安心して生きることができ、ありのままでいられ、自分で自分のことを決めることができるという心理的な状況から考えてみるとそのように思う。
【会長】
内容的に言えば、第6条、第4条、第5条の方が読み手は読みやすいかもしれない。
【委員】
前回か今回の議論で、成長・発達する権利の第5項が削除された。タイトルに「成長・発達する権利」と入っているため、削除したことにより、かなり第6項が薄くなったようなイメージはある。第6項の部分をもう少し厚く書けばバランスがとれるかもしれない。「自分のやりたいことに挑戦できる」ということと、「自由に遊び、学びたいことを学べ、体験できること」は別にした方が良いと思う。ジャストアイディアだが、「自分のやりたいことに挑戦できること」で分け、第7項に「自由に遊び、学びたいことを学べ、体験できること」にした方が分かりやすいかもれない。
【会長】
第6項をそのままとするのであれば、「成長・発達のためには」の後に「そういう環境を整えることが大切である」という書き方であればつながるのではないだろうか。
【委員】
本文が「次に掲げる権利が保障されなければなりません」と書かれているため、こういう権利と書いていかなければならないため、表現としてはいかがなものか。成長・発達が第6項だけになり、薄くなったため、もっと分厚く書けば良いのかもしれない。
【委員】
先程の第6項について、「次に掲げる権利が保障されなければなりません」とあるため、「成長・発達する環境を整えられること」とすれば良いのではないかと思う。
【会長】
「環境を保障されること」だとあまり違和感はないと思う。
【委員】
宗教と文化は入れた方が良いという意見が出たが、入園の面接等では一切確認していないし、他もそうだと思うが、禁句の内容である。国籍と書いてあるからこそ、宗教も含まれているので、宗教と書くと逆にすべてを入れなければならなくなり、ここに宗教を入れるのは、少し重い感じがする。
【委員】
信教の自由はすでに認められているため、わざわざ明文化しなくても良いと思う。
【委員】
それで差別が起こるということはあり得るのではないか。
【会長】
例えば、宗教上の理由でベールを外してはいけないため、体育でバレーボールをしてはいけない等、学校は配慮していることがある。
【委員】
学校側が拒否しているのではなく、家庭の方でやらせていないのではないかと思う。
【会長】
文化の中に宗教が入ってしまえば良いということか。他の自治体の状況を見て、入っているところが多いのか等、確認していただきたい。
◆議題2 狛江市子どもの権利条例制定に係る市民参加手続きについて
〇事務局より資料3についての説明
【委員】
市民説明会や対話タイムの時間がもう少し長い方が良いと思った。
【委員】
30分の市民説明会ではどのようなことを説明をするのかと思った。条例の一つひとつの説明をするとなると当然30分では足りないと思うし、その場での意見は全部パブリックコメントで寄せて欲しいということなのか。その場で言いたい人は多数いると思うし、その場で出た意見がそのままパブリックコメントとして扱われるなら良いなと思うと、時間は30分では到底足りないだろうと思った。
【事務局】
市民説明会は条例案自体を説明し、その後質疑応答を行う。
【委員】
資料3に子連れで参加可と書かれており、親子連れを想定すると、保育園や幼稚園の子どもだとこの時間が結構限界かと思い、そこまで見越しての時間だと思う。
【委員】
市民説明会の1回目はフォーラムの後に行うが、市民説明会だけ来る人もいる。フォーラムの後に行い、時間的に長いから、説明会を短くするというので良いのか。
【委員】
2回目の市民説明会の方は何分か。
【事務局】
特に時間は切ってはいないが、大体一時間程度と考えている。
【委員】
1回目と2回目は内容が違うのか。
【事務局】
1回目については12時終了にはしているが、時間で切ることは想定していない。
【副会長】
フォーラムやパブリックコメントというと、アクセスできる人たちの意見だけではなく、アクセスしにくい方々に届け、その方々の意見をぜひ吸い上げてもらいたいと、事前打ち合わせの際に依頼したが、その点はどうか。
【事務局】
資料の1枚目のパブリックコメントのところに、SNSを追加している。また、個別にアウトリーチヒアリングした団体に対しても周知する予定である。
【会長】
終わり時間が延びても良いと主催側が思っていても、伝えておいた方が良いと思う。終わり時間をお母さんたちが知っていないと、動きづらいと思うため、たとえば1時間の場合は、周知の際に「12時半終了予定」等、記載した方が良いと思う。
【委員】
狛江市の市民説明会は、これまでずっと型にはまった、市の職員が一方的に説明をして、それに対して質疑応答を受けるものがほとんどで、大きな計画でも参加者なしということがあった。そのような中で、今回このフォーラムと組み合わせることで、様々な人に参加してもらうきっかけにしようというのは画期的な取組と思う。
良い前例になって、他の計画でもこのように計画の設計に関わる人がより詳しく説明する、当事者の声が聴ける機会が増えていくと良いと思う。子どもも今回登壇するので難しいかと思うが、録画して狛江市のYouTubeで配信する等もアクセスの向上という点では考えられるのではないかと思う。
【会長】
チラシができるのであれば、できるだけ多くの人の目に触れるようにしていただきたい。
【委員】
子連れでの参加が可能ということであれば、途中退席可能な案内をしてもらえれば、もっと気軽に来てもらえるため、一文入れてもらいたい。
【会長】
出入り自由等、確かにそのような言い方ひとつで随分参加者が変わってくると思う。でき得る限り多くの人に届くよう注力していただきたい。
◆議題3 その他
○事務局より資料4、次回の日程についての説明
【会長】
その他意見等なければ、以上をもって会議を終了する。
-閉会-
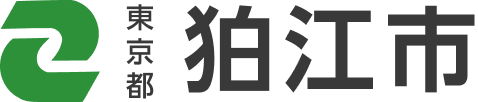
 印刷
印刷
 戻る
戻る
 ページの先頭
ページの先頭