令和7年度第1回狛江市市民参加と市民協働に関する審議会会議録(令和7年6月17日開催)
|
1 日時 |
令和7年6月17日(火曜日)午後6時30分~7時50分 |
|
2 場所 |
狛江市防災センター303会議室(オンライン含む) |
|
3 出席者 |
委員:重藤 さわ子、西 智子、深谷 慎子、麻宮 百、伊東 達夫、伊藤 秀親、遠藤 貴美子、鳥塚 鈴子、吉田 明広、千葉 尚政 政策室長 杉田 篤哉、政策室市民協働推進担当 白岩 亮、白鳥 美嘉 |
| 4 オンライン |
関谷 昇 |
|
5 欠席者 |
上野 良歌、松浪大輔 |
|
6 配布資料 |
|
|
7 議題 |
|
|
(1)今年度の審議会の進め方について -資料1に基づき、事務局から説明- ・審議会は会長が招集し、委員の過半数をもって会議が成立する。 ・審議会は非公開と決定した場合を除き原則公開とし、非公開と決定した場合はその理由を公表する。 ・会議録については要点筆記、発言者は会長、副会長、委員と表記することとし、全委員の確認をいただいた後、市ホームページで公表する。 ・今年度の主な議題については、例年審議していただくものが中心となっている。 (会長)昨年度との変更点としてはこまえくぼの評価がないという点と、市民参加と市民協働に関する総合的評価のやり方を変更している点であり、各委員に第2回までに評価いただく等のプロセスがあるので、御協力をお願いしたい。 -承認-
(2)市民参加と市民協働の実施状況に関する総合的評価について -資料2-1、参考資料1・2に基づき、事務局から説明- ・総合的評価の流れについて、①市民参加評価・市民協働事業評価の実施として、令和6年度に行われた事業について各委員に評価を行っていただく。その評価を受けて、②審議会での評価・検討を7~8月頃、③答申案の検討を8~10月頃に行い、④答申を12月頃に行うという流れを想定している。 ・資料2-2、参考資料1は市民参加実施結果シート(以下「結果シート」という。)となっており、令和6年度に実施した市民参加手続が必要な事業の結果を記載している。全部で9件の事業があるが、実際にこのやり方での評価を行うのが初めてであることから、今年度は政策室が所管する3事業を評価対象としたいと事務局としては考えている。 ・資料2-3は令和6年度に実施した市民提案型市民協働事業となっており、NPO法人こまえにほんごしえん・日本語スクールと政策室との協働となっている。市民協働事業の結果等を市、団体それぞれが記入しているので、その内容を基に評価をいただく。 ・資料2-4は市民参加の評価シートとなっており、先ほどの結果シートについて、それぞれの事業で選択した市民参加手続やスケジュール、情報提供などの市民参加のプロセスが適切だったかを評価いただく。市民協働の評価シートについても、協働に至る過程、協働体制、成果等について、資料2-5の評価シート記入要領を参考に評価いただきたい。 ・事業の内容や疑問に感じた点などがあれば、資料2-6質問票にて事務局にご質問いただきたい。後日質問の回答をとりまとめたものをメールにて送付するので、ご覧いただき評価シートを記入いただきたい。 ・資料2-7は令和6年度市民協働事業実施状況となっており、例年資料としている。質問等があれば後日事務局までご連絡いただきたい。 ・参考資料2は市民参加事前シート(以下「事前シート」という。)となっており、今年度実施予定の事業を記載している。年度終了後、これらの事業について同様に結果シートを担当課が作成するので、来年度に事前と結果を見ながら各委員に評価いただく予定である。 (会長)流れについて改めて説明させていただく。市民参加評価については資料2-2のとおり、3件の事業を評価シートによる評価を行っていただく。市民協働事業評価についても、どういうプロセスで市民協働に至り、市民協働してどうだったかを評価シートによる評価を行っていただく。作業期間は今日から7月4日までとなる。本来であれば事前シートと結果シートで評価を行うが、今回は初めてなので結果シートのみでの評価となる。しかし、これだけ見ても審議会での議論の内容やプロセス等分からない部分も出てくると思うので、市ホームページの会議録やパブコメ等のページのリンクを付けて確認できるようにしている。参照できる資料はたくさんあるが、行政の資料を見るのが初めてという方もいると思うので、まずはそれぞれの負荷の中で行っていただきたい。評価するにあたり教えてもらわないと判断できない、適正な評価ができないという点に関して、質問票を書いていただく。質問票は必ずというわけでなく、評価をする上で困ったら提出いただきたい。質問票はとりまとめたものを6月27日までに事務局から送付するので、質問しなかった場合でもとりまとめ結果を見てから評価していただきたい。評価は質問の有無に関わらず進めていただき、質問票の回答が来たらそれも見て最終的な評価を完成させていただき7月4日までに事務局まで回答してほしい。 評価のポイントは副会長から御説明いただく。 (副会長)事務局と会長の説明を踏まえ、ポイントとなる点を御説明させていただく。今回の評価については、事業の中身を評価するというよりも、事業の一連のプロセスを踏まえた上でどのように市民参加、市民協働が展開されたのかという視点から評価するというのが前提となっている。中身について意見もあると思うが、今回は市民参加はどれくらい確保されているか、どのように市民の声が反映されたか、もっと違った形で市民の声を聞くべきだったのではないか、ここはもっと市民参加手続が必要だったのではないかなど、これらの資料を通じて見えてくると思うので、それを各委員ごとに評価していただく。 評価の意味合いというのは、うまくいっている点、うまくいっていない点を炙り出しながら、結果として本審議会で各事業の評価を市に伝えていくことである。市民参加の手法が取り入れられているが、もっと実質化して、もっと様々な声をこういう形で聞くべきという提言を最終的に行っていくが、評価していく中で、市民参加の手法を取り入れて、市民の声を反映させながら事業を展開したという優良事例が出てくれば、審議会で良い評価をして共有していく。課題を出すにしても優良事例を共有するにしても市民参加と市民協働について反省したり学んだりする契機にしていくことが重要である。 その上で、市民参加と市民協働について毎年度いくつかの事業を絞り込んで評価していく。流山市では10から15の事業を毎年評価している。自治体によって事業の規模や数はそれぞれ異なり、事業を選ぶ方針もあると思うので、それは今後の運用の中で作っていくことになる。今年度は初年度なので事業を3つに絞って行うが、来年はもう少し増える可能性もある。毎年絞り込んだ事業を各委員が中身を理解して自分で判断し、それを評価シートに記入し提出する。そしてそれを審議会の場で合議で評価し、最終的な評価をする。まず自分なりにどのように評価できるのか考えていただいて、他の委員の評価も聞いて協議を重ねて最終評価を出していくことになる。 来年度以降は事前シートと結果シートの両方を基に評価するが、令和6年度は結果シートを基に評価することになる。結果シートをベースにその事業がどのような中身で展開されたのかを各委員が把握することが、各委員が行う最初の作業となる。例えば、基本計画の改定であれば、どんな根拠に基づく事業なのか、どれくらいの期間行われたのか、どういう中身の事業だったのかを会議録等を見て把握する。どれくらい資料を読み込むかというのは各委員によって異なる。流山市では議事録や説明資料を全部読んでから評価する委員もいれば評価シートを中心にイメージを作って自分なりの視点で評価していく委員もいる。レベル感や精度は各委員の判断で評価してよい。立ち位置や経験、考え方の違いによって評価の水準や評価のポイントも委員間で違いが出てくるかと思う。合議をするときはその違いが大事となる。評価は合議の中で変わってもよく、そのように評価を練り込んで最終評価に繋げていくというイメージになる。実際に評価して合議をしてみると、レベル感が違ってくるように思われる。プラスな評価をする人もいれば、そうでないと評価する人もいる。どの視点でどのように評価するかのレベル感はやっていきながら収束していくのではないかと思う。最初どの水準で評価すればよいか迷うこともあるかと思うが、最初は自分なりに評価をして、合議をしながら審議会としての評価を行い、毎年重ねながら水準を固めていけばよいのではないかと思う。 評価シート記入要領を見ていただきたい。各事業を評価するにあたっては、市民参加評価では①市民参加手続の選択についてとある。それぞれの事業をどういう視点から評価したらよいのかという一つの切り口になる。市民参加手続の手法がどんな形で選択されたのかということを見る視点である。審議会、パブコメ、市民説明会、アンケート、ワークショップなどの手法があるが、様々な形で市民の意見をもらう工夫をしたのかということをそれぞれの目線で見ていただき、様々な手法がとられてよいとなるのか、もっと様々な手法を多角的に用いて意見を聞くべきだったのではないか、ということを炙り出せるようになる。A、B、Cで評価することになるが、私だったら、市民参加手続の手法については大体見えてくる傾向があり、ほとんどの事業が審議会を開き、パブコメをやるという大体この2つに収れんしれている可能性が高いので、それぞれがどういう制度でなされているのかということを見ていく。しかし、審議会やパブコメだけだと十分に市民の意見を汲み取れないということが出てくるので、例えば男女共同参画推進計画であれば、それに関する様々な関係者や当事者の声をどれくらい聞いているのか、教育に関する計画であればPTAや先生、専門家の声を聴くというのが審議会を通じてよくあるパターンであるが、子どもたちの声をどれくらい聞いたのかという目線で捉えていくと、もっと幅広い手法を導入すべきだったという見方ができたりもする。皆さんなりの視点で①をどう評価できるかを考えていただけるとよい。 ②市民参加のスケジュールについて、結果シートでは審議会を事業期間中いつ何回開いたということが分かるようになっている。審議会も期間全体を通じて的確に開催されている場合もあれば、事業の最後に数回立て続けに開催しているという場合もあるので、それぞれ選択された手法が適切なスケジュール感で実施されたかという視点で評価していく。パブコメも直前に行われる傾向が強いが、本気で実質化していくのであればもっと早い段階で一度パブコメをやって色々な意見を聞いて、それを練り直して原案に反映させてもう一回まとめにかかるというプロセスを取ってもおかしくはない。しかし、どの担当部署も色々な意見が出てきてしまうと困るという思いもあってパブコメをギリギリのところにする傾向がある。このように、それぞれの委員の立場でどう考えるべきなのかというのも炙り出すのもよい。 ③事業内容や市民参加手続に関する市民等への情報提供については、市民参加を進める前提の話で、例えばパブコメを実施したが意見が数件しか出てこないパターンは結構あるが、それは市民参加が実質化していないことの表れであって、本気でパブコメを実質化していくのであれば、パブコメに付す資料について、どういう意見をもらおうとしているのかという資料の作り方、どんな資料を市民に提供しているのかという見方、子どもでも分かるような表現にしているのかという見方などができると思う。そのように、どのような情報提供、情報発信、共有の工夫をしたのかということは市民参加の前提となり、情報が豊かに提供されていれば市民の関心も高まる可能性があり、市民参加の裾野も開かれる。逆に資料の情報が十分に伝わっていなければ、市民がなかなか自分の問題として捉えようとしないという傾向がある。 ④総合評価については、①~③を踏まえて全体としてその事業をどう評価するかということでA、B、C、Dでの評価となる。コメントについては、評価するにあたり考えたことを織り交ぜながら記入していただき、審議会でまとめ、最終的に事務局で取りまとめて実施した部署にフィードバックしていく、そこまでが一連の評価の流れとなる。各部署がそれに基づきどのように考えるのかということになるが、幅広く共有して少しでも市民参加の裾野が広がるような形にしていくというのが評価の全体の枠組みとなる。 市民協働についても同じように評価を行っていただくが、協働までのプロセスについては、どんなプロセスを経て担当部署と該当団体が連携するようになったのかということが協働を強化する上ではすごく大事になる。どのような課題を共有し、課題共有ができたのかできなかったのか、できたならどのような役割分担で進められたのか、という一連のプロセスを炙り出すのが協働では重要なポイントとなる。そのあたりを踏まえて評価してほしい。 (会長)一般的に適切に実施されたものは3段階評価の場合にはB評価となり、A評価は他の事業の見本になるような優れた事例ということになる。総合評価の4段階評価でいうとA評価はやるべきことを実施して効果があり他の事業の見本になる工夫がある場合、B評価はやるべきことを「効果的に」やっている場合、C評価はやるべきことはやっている場合、D評価はやるべきことをやってない場合ということになる。今年度初めてやるものなのでこのやり方は狛江市に合うものなのかも探りながらということもあるので、まずは3つの事業の評価をやってみて、その中で出た意見も踏まえて今後評価プロセスや方法などもブラッシュアップしていければいいと思う。 (委員)プロセスを評価するということだが、資料2-2の⑨意見の反映について、「意見を反映した」としか書いていないがどのように評価すればよいのか。また、担当部署がなぜその市民参加を選んだかということや適切だと考える理由等が分からないないと、適切だった等の事業の評価はできないのではないか。 (会長)議事録やパブコメの結果を見ていただき、それでも分からない点については質問票を提出してもらいたい。例えばなぜアンケートをやらなかったのかといった質問はしてもよいと思う。ただ、市民参加の手続については、条例で示された方法の中から選択されていると思われ、担当としてはそれが適切だと思って選択しているという前提で考えてほしい。 (事務局)今回は初めてなので政策室で行った事業を選んでおり、計画の改定について市民参加の手続を取っているが、計画を作る過程から市民参加の手法を入れるのが適切であるという考えから策定に係る審議会、パブコメを選択している。条例上に定める手続きの中から選択することになるので、計画では主に審議会、パブコメ、市民説明会が参加のしやすさ、反映のしさすさという点で取り入れられている。 (会長)事前評価をやるのであれば事前になぜ選んだかということを入れられると思うが、今回は事後になっているので、今あるもので評価することになる。 (委員)今回は初めてなのでそのような双方向のやり方ではなくて、各課が作成した結果シート等で評価をすると理解している。 (委員)市民委員として、ホームページを見てもきちんと情報が伝わっていないから参加できなかったということも一つの評価だと思うし、議事録や公表されているものが伝わりにくい方法だと思えばプロセスとして問題があるので工夫が必要という評価をするということが、役割であると考えている。市民委員であるということで、市民としてこれが伝わっていなかったという大前提があるなら強くコメントして書くと伝わっていくと考える。ホームページで公開されている内容が見にくかったら関心を持ちにくいとか、どんなふうに参加しやすくしていく必要があるのかという視点で評価していけばよいと理解している。 (会長)市民参加のあり方について、本審議会と市とのコミュニケーションの始まりだと理解してほしい。結果シートのフォーマットも初めてなので、これでは評価できないということも貴重な意見だと思うので、それを翌年度に活かしていくことが重要である。 (副会長)御意見があったように資料を見るだけもこれだけの見方があったり色々な評価の仕方があるので、まずはそれを炙り出すことが重要である。意見がどのように反映されたかが与えられた資料だけでは分からない場合には、それを質問してもらいたい。結果シートの書き方は担当課によっても温度差があり丁寧に書く部署もあればそうない部署もあるので、そこは繰り返し重ねていくしかない。資料2-2に「市民参加の実施を踏まえた担当課の意見」の欄は担当課としてどう考えているのか、結果をどう見ているのかという意見が表れているこころであるし、⑩「工夫したこと」も規定上審議会やパブコメ等を入れないといけないという形式的な理由がある一方、審議会が一番色々な意見をもらいやすい手法だったなど担当部署の意見が表れる箇所である。担当課は⑩欄でなぜその方法を選択したのか、どのような声を拾い上げようとしていたのかを今後書いてもらうようにすると、各部署の狙いがより結果シートに反映してくるようになるので、今後運用の中で工夫していけるとよいと思う。 (委員)評価シートについて、ハイフンとなっている箇所の意味は何か。 (事務局)エクセルシートでプルダウンで選択する箇所になっている。 (会長)担当部署から情報を出してもらい評価するということを今まで審議会で行っていなかったので、実施する中でどのような情報を出すのがよいか、どのような情報を出してほしいか、などとやり取りが始まることが市民参加・市民協働の仕組みをより良くしていくことに繋がると思う。
(3)市民協働事業提案制度について -資料3に基づき、事務局から説明- ・市民協働事業提案制度については、令和7年5月1日~6月20日のスケジュールで募集を行っている。協働事業提案制度は例年募集が少ない状況が続いていたが、今年度についてはこまえくぼから登録団体へアンケートを送付し、制度の案内をはじめ、興味があるかどうかや募集しない場合にはその理由等確認等を行っている。その中で、興味があるという団体が複数あり、現在こまえくぼや主管課と打合せ等を行っており、複数の団体から応募がある予定となっている。次回の審議会にて、結果を改めて報告させていただく。
(4)狛江市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例の基本的な考え方について -資料4-1、4-2に基づき、事務局から説明- ・昨年度3月の審議会で報告した件になるが、見直しが完了したので対照表にまとめている。 ・主な修正箇所は1箇所で、8ページの第5条第1項第4号の解説を見直している。市民センターにあった図書館が一部機能を残して旧駄倉地区センターに移転する件が進んでいるが、移転することについて市民参加の手続が必要なのではないかということが議会でも議論になったところである。今回、前提となる地方自治法の規定を踏まえた考え方を補足することで明瞭な解説としたほか、現状に合わせた修正を行っている。 (委員)今回の修正箇所ではないが、5ページ「事業者が公共事業を行うことは営利活動であり、前述の趣旨と異なり市民協働にはあたらない。」という箇所について説明いただきたい。 (事務局)協働事業の対象が拡大されて営利企業も協働事業を行うことはある。ここで言う公共事業は市が発注する事業を事業者が委託や請負で行う場合等のことで、それは営利活動なので市民協働ではないということの注釈である。 (委員)7ページの第3条の2「事業者の責務」の条文について、行政が事業者に対し言うことに違和感を感じる。行政が事業者へ何を期待するかということに収めておいたほうがよいと考える。 (事務局)条例を見直す際には改めて審議会にて御審議いただきたい。
(5)分科会等の役割分担について -資料5に基づき、事務局から説明- ・市民協働事業提案制度については7月26日、市民公益活動事業補助金については2月14日にプレゼンテーションを予定している。審査委員を個別に御相談させていただいており、あとそれぞれ1名委員が決まっていない状況なので個別に御相談させていただく。
(6)その他 -当面の審議会の日程について、事務局から説明- ・次回は7月22日(火)を予定している。
-閉会-
|
|
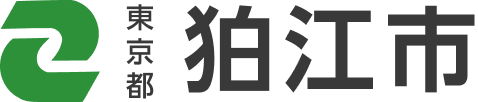
 印刷
印刷
 戻る
戻る
 ページの先頭
ページの先頭