後期高齢者医療保険(令和7年4月改訂)
後期高齢者医療制度は、75歳以上のすべての方と一定の障がいのある65歳から74歳までの方を対象とした医療保険制度です。
運営主体は、東京都内全市区町村が加入する東京都後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という)です。
・後期高齢者医療制度の対象となる方
1.対象となる方
2.保険証または資格確認書
3.マイナ保険証
・後期高齢者医療保険料
4.保険料の決め方
5.保険料の納め方
・医療を受けるとき
6.受診方法と一部負担金
7.医療費が高額になったとき
8.高額医療・高額介護合算制度
9.療養費の支給
10.葬祭費の支給
・よくある質問
①保険証・資格確認書の紛失
②75歳になる方の資格確認書
③マイナ保険証と資格確認書
④保険料の支払い
⑤入院時に必要な手続き
⑥医療費が高額になったとき
⑦コルセット(補装具)の払い戻し申請
⑧被保険者が亡くなったとき
⑨書類の送付先変更
⑩交通事故に遭ったとき
⑪委任状のひな型
⑫担当課(保険年金課医療年金係)の住所
1.対象となる方
75歳以上のすべての方と、一定の障がいのある65歳から74歳までの方(施設入所等で住所地特例の適用を受けている方を除く)は、現在加入中の国民健康保険または被用者保険(社保、共済)から脱退し、広域連合が運営する後期高齢者医療制度に加入することになります。
これまで健康保険組合や共済組合等の加入者に扶養されていた被扶養者の方も、後期高齢者医療制度では被保険者となります。
| 対象者 | 資格の開始日 |
備考 |
|
75歳以上の方 |
75歳の誕生日から |
誕生日前月までに資格確認書を郵送(特定記録郵便)等で交付します |
|
65歳以上で障がいのある方
|
広域連合の認定を受けた日から |
【申請に必要なもの】 |
2.保険証または資格確認書
後期高齢者医療制度では、一人に1枚「後期高齢者医療被保険者証(保険証)」または「後期高齢者医療資格確認書(資格確認書)」を交付します。
保険証または資格確認書には、医療機関で受診する際の一部負担金の割合が記載されていますので、受診するときは必ず提示してください。また、保険証または資格確認書は、なくさないよう大切に保管してください。
- 令和6年12月2日以降、従来の保険証の新規交付は終了しましたが、すでに交付されている保険証(青竹色)は、記載されている情報に変更があった場合を除き、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。
- 令和6年12月2日以降に発行する資格確認書は、オレンジ色のカードサイズのものです。有効期限は令和7年7月31日です。
- 令和7年8月1日から令和8年7月31日までは、マイナ保険証をお持ちの方にも資格確認書が交付されます。令和7年8月1日からお使いいただく資格確認書は7月中に特定記録郵便で送付します。
3.マイナ保険証
医療機関等の受付で、保険証の代わりにマイナンバーカードを提示することで、医療保険の適用を受けることができます。
マイナ保険証を利用するための必要な手続き
- マイナンバーカードを取得する。
取得方法については、「マイナンバーカードの申請・交付」をご覧ください。 - マイナンバーカードを健康保険被保険者証として登録する。
登録方法については、マイナポータル「マイナンバーカードが健康保険証等として利用できます!(外部リンク)」をご覧ください。
また、ご自身の保険証が正しく登録されているかを確認する方法については、デジタル庁「よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部リンク)」をご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除について
解除を希望する場合、申請により解除することができます。必ず「確認事項」をよくお読みいたただき、ご了承の上申請してください。
確認事項
- 利用登録を解除すると、マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことはできません。
- 利用登録解除後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで、1~2か月程度時間がかかる場合があります。
- 利用登録の解除を申請した方には、保険者(東京都後期高齢者医療広域連合)から資格確認書を交付します。解除後、医療機関・薬局を受診等される際には資格確認書の持参が必要です。
- 解除申請後から解除がなされるまでの間(1~2か月程度)に、他道府県へ転出された場合には、転出後の医療保険者(他道府県広域連合)に対し、自身が以前に加入していた医療保険者(東京都後期高齢者医療広域連合)に対して解除申請を行ったことを申し出るとともに、資格確認書の申請を行うようにしてください。
- 健康保険証の利用登録解除をした後も再度利用登録を行うことは可能です。
申請に必要なもの
本人が窓口で申請する場合
 マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書.pdf [ 106 KB pdfファイル]
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書.pdf [ 106 KB pdfファイル]
 マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(記入見本).pdf [ 312 KB pdfファイル]
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(記入見本).pdf [ 312 KB pdfファイル]- マイナンバーカードまたは顔写真付きの本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)
代理人が窓口で申請する場合
 マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書.pdf [ 106 KB pdfファイル]
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書.pdf [ 106 KB pdfファイル]- 代理人の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)
 後期高齢者医療に関する委任状.pdf[32KB pdfファイル]
後期高齢者医療に関する委任状.pdf[32KB pdfファイル]
※代理人が後見人の場合は、登記事項証明書が必要です。
※本人と同一世帯の方が代理で申請する場合は、委任状は不要です。
郵送で申請する場合
 マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書.pdf [ 106 KB pdfファイル]
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書.pdf [ 106 KB pdfファイル]- 解除を希望する方のマイナンバーカードのコピー(表面(顔写真の面)のみ)または顔写真付きの本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)のコピー
上記の書類を同封して郵送してください。
(送付先)
〒201-8585
狛江市和泉本町一丁目1番5号
狛江市 福祉保健部 保険年金課 医療年金係 後期高齢者医療担当
4. 保険料の決め方
被保険者の皆さんが病気やケガをしたときの医療費などの支払いに充てるため、被保険者全員に保険料を納めていただきます。医療費は、患者負担分を除き、約1割は被保険者からの保険料、約5割は公費、約4割は現役世代からの支援金で構成されています。
保険料額は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。
均等割額と所得割率は、東京都後期高齢者医療広域連合で2年ごとに見直されます。
保険料の決め方についてはこちら(東京都後期高齢者医療保険広域連合ホームページ(外部リンク))をご覧ください。
5. 保険料の納め方
保険料の納め方
特別徴収(公的年金からの引き落とし)
保険料は原則として公的年金からの引き落としになります。
ただし、公的年金の受給額が年額18万円未満の方や、介護保険料と後期高齢者医療制度の保険料の合算額が対象となる年金額の1回あたりの年金受給額の2分の1を超える方については、特別徴収の対象となりません。
普通徴収(口座振替、納付書払い)
特別徴収の対象とならない方は、原則として口座振替でお支払いいただきます。口座振替にしていただくと、納め忘れによる滞納がなくなり、健康保険制度の安定的な事業運営につながります。
口座振替をご利用いただけない方には納付書をお送りします。
※ 狛江市後期高齢者医療に関する条例施行規則の改正(令和7年4月1日施行)に伴い、普通徴収のお支払い方法は「口座振替」が原則になりました。
保険料の納期
特別徴収
年金支給月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)
普通徴収
令和7年度の納期は下表のとおりです。
納付書払いの方は7月中旬に納付書を発送しますので、各納期の納期限までに取扱金融機関にてお支払いください。
| 期別 | 納期限(口座振替日) |
| 第1期 | 令和7年7月31日(木曜日) |
| 第2期 | 令和7年9月1日(月曜日) |
| 第3期 | 令和7年9月30日(火曜日) |
| 第4期 | 令和7年10月31日(金曜日) |
| 第5期 | 令和7年12月1日(月曜日) |
| 第6期 | 令和7年12月25日(木曜日) |
| 第7期 | 令和8年2月2日(月曜日) |
| 第8期 | 令和8年3月2日(月曜日) |
保険料の支払い方法の変更
「納付書払い」から「口座振替」への変更
「特別徴収(年金からの引き落とし)」から「口座振替」への変更
以下のものを持参し、保険年金課で申請してください。
- 保険証または資格確認書
- 通帳など口座の確認ができるもの
- 金融機関届出印(口座を作ったときに使用した印鑑)
※ 国民健康保険の口座振替を引き継ぐことはできませんので、新たに口座振替の手続きをお願いします。
※ 口座名義人は、被保険者本人だけでなく、世帯主や配偶者等の名義のものも指定することができます。その際、保険料は口座名義人が支払ったことになります。
6.受診方法と一部負担金
広域連合から交付された保険証または資格確認書を医療機関等の窓口に提示してください。マイナ保険証でも受診することができます(一部医療機関を除く)。
窓口で支払う一部負担金
後期高齢者の方が、受診した時に自分で支払う費用(一部負担金)は、外来(在宅医療を含む)・入院ともにかかった医療費の1割(一定以上所得のある方は2割)です。ただし、現役並み所得者の負担割合は3割となります。
所得に応じた負担
一部負担金の割合は、毎年8月1日から翌年7月31日の期間について、前年の収入、所得の金額をもとに判定します。
所得に応じて自己負担割合や保険料(後述)などが決まりますので、忘れずに所得の申告をしてください。
所得区分・負担割合について
所得区分・自己負担割合についてはこちら(東京都後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク))をご覧ください。
自己負担限度額について
医療費の1か月の自己負担限度額についてはこちら(東京都後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク))をご覧ください。
入院時の食費の自己負担額についてはこちら(東京都後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク))をご覧ください。
7.医療費が高額になったとき
月の1日から末日までに支払った一部負担金の合計が自己負担限度額を超えた場合、払い戻しが受けられます。該当者の方に対して、受診から4~6か月後に「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」を送付しています。
申請書に、振込先の金融機関名、店舗名、口座番号、口座名義人などの必要事項を記入し、同封の返信用封筒で郵送申請してください。
一度申請すれば、再度申請する必要はありません。その後も支給対象になった場合は、継続して指定口座に入金されます。
※自己負担割合が2割の方で、高額療養費事前申請書にて事前に口座登録をされた方が支給対象となった場合は、申請する必要はありません。
※高額な診療を受ける際には、所得区分が区分I・IIまたは現役並み所得Ⅰ・IIの方については、所得区分の記載された資格確認書を発行することができます。保険証または資格確認書を持参の上、保険年金課での申請手続が必要です。
8.高額医療・高額介護合算療養費制度
後期高齢者医療制度の自己負担額と、介護保険の利用者負担額の世帯での合算額が、自己負担限度額を超えたときは、申請をすると限度額を超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。
高額介護合算療養費は、後期高齢者医療制度と介護保険制度から支払った自己負担額の割合で、それぞれ支払われます。算定期間は毎年8月1日から翌年7月31日までとなります。
算定基準額(1年間の自己負担限度額)についてはこちら(東京都後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク))をご覧ください。
9. 療養費の支給
次のような場合は、いったん全額自己負担になりますが、申請して認められた場合、自己負担分を除いた額が「療養費」としてあとから支給されます。
※申請から支給まで約3~4か月かかりますのでご了承ください。
保険証等を持たずに診療を受けたとき
以下の5点をお持ちのうえ、保険年金課窓口で申請してください。
 【一般】療養費支給申請書.pdf[166KB pdfファイル]※
【一般】療養費支給申請書.pdf[166KB pdfファイル]※- 診療報酬明細書(レセプト)※
- 領収書※
- 保険証または資格確認書
- 通帳など、口座の確認ができるもの
 【一般】療養費支給申請書(記入方法).pdf [104KB pdfファイル]を参考にしてください。
【一般】療養費支給申請書(記入方法).pdf [104KB pdfファイル]を参考にしてください。
郵送による申請ができます。
※印のついたものを下記郵送先へ送付してください。
〒201-8585 狛江市和泉本町一丁目1番5号
狛江市 福祉保健部 保険年金課 医療年金係 後期高齢者医療担当
医師の指示により、補装具(コルセット等)を作ったとき
以下の5点(靴型装具を作成した方は6点)をお持ちのうえ、保険年金課窓口で申請してください。
 【補装具】療養費支給申請書.pdf [167KB pdfファイル]※
【補装具】療養費支給申請書.pdf [167KB pdfファイル]※- 治療用装具製作指示装着証明書※
- 補装具の領収書※
- 保険証または資格確認書
- 通帳など、口座の確認ができるもの
- (靴型装具を作成した方のみ)靴型装具の写真(被保険者本人が実際に装着する現物であることが確認できるもの)※
 【補装具】療養費支給申請書(記入方法).pdf [103KB pdfファイル]を参考にしてください。
【補装具】療養費支給申請書(記入方法).pdf [103KB pdfファイル]を参考にしてください。
郵送による申請ができます。
※印のついたもの(6は靴型装具を作成した方のみ)を下記郵送先へ送付してください。
〒201-8585 狛江市和泉本町一丁目1番5号
狛江市 福祉保健部 保険年金課 医療年金係 後期高齢者医療担当
10. 葬祭費の支給
被保険者が亡くなったときは、葬祭を行った方に葬祭費(50,000円)を支給します。
変更依頼書(お亡くなりになったとき)の提出と保険証(資格確認書)のご返却もお願いいたします。
申請に必要なもの
 葬祭費支給申請書 [46KB pdfファイル]※
葬祭費支給申請書 [46KB pdfファイル]※- 葬祭の領収書の写し※
- お亡くなりになった方の保険証または資格確認書※
- 申請者の金融機関、口座番号、口座名義が確認ができるもの
- 委任状(葬祭を行った方以外の方への振込を希望する場合)※
![]() 葬祭費支給申請書(記入見本) [91KB pdfファイル]を参考にしてください。
葬祭費支給申請書(記入見本) [91KB pdfファイル]を参考にしてください。
郵送による申請ができます。
※印のついたものを下記郵送先へ送付してください。
〒201-8585 狛江市和泉本町一丁目1番5号
狛江市 福祉保健部 保険年金課 医療年金係 後期高齢者医療担当
変更依頼書(お亡くなりになったとき)と保険証(資格確認書)の返却
- 「後期高齢者医療に関する変更依頼書」の提出
今後の書類の送付先および高額療養費の振込先を変更するための申請書です。必要事項をご記入・ご捺印の上、ご提出ください。
 変更依頼書(お亡くなりになったとき) [162KB pdfファイル]
変更依頼書(お亡くなりになったとき) [162KB pdfファイル]
 変更依頼書(記入見本) [196KB pdfファイル]
変更依頼書(記入見本) [196KB pdfファイル]
- 保険証または資格確認書の返却
上記の書類をご提出いただく際に、今まで使用されていた保険証または資格確認書もご返却ください。
よくある質問
①保険証または資格確認書をなくしてしまったがどのような手続きをしたら良いか。
再発行の手続きをしてください。令和6年12月2日をもって従来の保険証の発行が終了したことから、保険証の代わりに「資格確認書」を発行します。
窓口で手続きする場合
ご本人または同じ世帯の方が、顔写真付きの公的な身分証明書をお持ちいただければ、再発行した資格確認書をその場でお渡しします。
ご本人確認ができない場合には、ご自宅(送付先を設定している場合はその送付先)へ特定記録郵便でお送りします。
郵送で手続きする場合
「再交付申請書」に必要事項を記入のうえ、保険年金課医療年金係まで郵送してください。申請書を受領後、資格確認書をご自宅(送付先を設定している場合はその送付先)へ特定記録郵便でお送りします。
②もうすぐ75歳になるが資格確認書はいつ届くのか。
75歳になる誕生月の前月末までに、特定記録郵便で送付します。
③マイナ保険証を持っているが、資格確認書が欲しい。
令和7年8月1日から令和8年7月31日までは、マイナ保険証をお持ちの方を含め、全被保険者の方に資格確認書が交付されます。
「マイナンバーカードを紛失した」、「マイナ保険証での受診が困難」等の理由がある方で令和8年8月以降も資格確認書の交付を希望する場合は、保険年金課へ申請が必要です。
※マイナ保険証をお持ちでない方は申請不要です。
④保険料はどのように支払うのか。
保険料の納付方法は、「特別徴収(公的年金からの天引き)」と「普通徴収(口座振替または納付書払い)」の2通りです。毎年7月下旬(年齢到達や転入等により新しく資格取得した方はその翌月)に1年間の保険料と支払方法をお知らせします。
納付書のつづりが届いた方は、金融機関の窓口にてお支払いが必要です。
なお、納付書払いの方は「口座振替」に変更することができますので、積極的にご利用ください。ご希望の方は、振替先金融機関の通帳、届出印、保険証または資格確認書をお持ちのうえ、保険年金課までお越しください。
⑤入院することになったが必要な手続きはあるか。
保険証または資格確認書の自己負担割合が「1割」かつ「区分I」または「区分II」に該当する方、「3割」かつ「現役並み所得I」または「現役並み所得II」に該当する方は、所得区分の記載された資格確認書を発行します。
ご家族様でもお手続きができます。窓口へ来庁する際には、入院する方の保険証または資格確認書(原本)をお持ちください。なお、入院する方がどの区分に該当するかわからない場合は、電話でのお問い合わせも可能です。
⑥医療費が高額になった(自己負担限度額を超えて支払った)が必要な手続きはあるか。
「高額療養費」として、自己負担限度額を超えて支払った分を診療月から3~4か月後に東京都後期高齢者医療広域連合から支給します。初めて高額療養費の支給対象となった場合には、広域連合から最短で4か月後に申請書が届きますので、必要事項を記入のうえご返送ください。2回目以降は、手続きは必要ありません。
⑦医者の指示によりコルセット(補装具)を作ったので申請したい。
窓口で手続きする場合
以下の4点をお持ちのうえ、保険年金課窓口で申請してください。
- 治療用装具製作指示装着証明書
- 補装具の領収書
- 保険証または資格確認書
- 通帳など口座の確認ができるもの
郵送で手続きする場合
「療養費支給申請書(補装具)」に必要事項を記入の上、上記1と2を同封して郵送してください。
※申請から支給まで約3~4か月かかりますのでご了承ください。
⑧被保険者が亡くなったのだが、必要な手続きはあるか。
「おくやみコーナー」において、市役所における各種手続のお手伝いやご案内をさせていただきます(予約制)。
詳しくは、「おくやみコーナー」のページをご覧ください。
後期高齢者医療保険に関する手続きは、以下の3点です。
- 「後期高齢者医療に関する変更依頼書」の提出
今後の書類の送付先および高額療養費の振込先を変更するための申請書です。必要事項をご記入・ご捺印の上、ご提出ください。
 変更依頼書(お亡くなりになったとき) [162KB pdfファイル]
変更依頼書(お亡くなりになったとき) [162KB pdfファイル]
 変更依頼書(記入見本) [196KB pdfファイル]
変更依頼書(記入見本) [196KB pdfファイル] - 「葬祭費支給申請書」の提出
喪主の方に葬祭費として5万円を支給します。必要事項をご記入いただき、葬儀代の領収書(コピー)を添付の上、ご提出ください。
お支払いは申請の翌月20日頃となります。
 葬祭費支給申請書 [46KB pdfファイル]
葬祭費支給申請書 [46KB pdfファイル]
 葬祭費支給申請書(記入見本) [91KB pdfファイル]
葬祭費支給申請書(記入見本) [91KB pdfファイル] - 保険証または資格確認書の返却
上記の書類をご提出いただく際に、今まで使用されていた保険証または資格確認書もご返却ください。
⑨施設入所や高齢等のため被保険者自身による書類の管理が難しいので、書類の送付先を変更したい。
ご本人およびご家族等で話し合いの上、「後期高齢者医療に関する変更依頼書」をご提出ください。
![]() 変更依頼書(送付先変更).pdf [ 144 KB pdfファイル]
変更依頼書(送付先変更).pdf [ 144 KB pdfファイル]
![]() 変更依頼書(記入見本)[154KB pdfファイル]
変更依頼書(記入見本)[154KB pdfファイル]
⑩交通事故に遭ったのだが健康保険を使っても良いか。
保険年金課医療年金係へ連絡・届出いただくことで、保険証または資格確認書を使用して診療を受けることができます。
診療を受ける際には、医療機関に「事故による受診である」ことを必ず申し出てください。
⑪委任状を添付したいのだが書式はあるか。
![]() 後期高齢者医療に関する委任状.pdf[32KB pdfファイル]をお使いください。
後期高齢者医療に関する委任状.pdf[32KB pdfファイル]をお使いください。
⑫書類の送付先
〒201-8585
狛江市和泉本町一丁目1番5号
狛江市 福祉保健部 保険年金課 医療年金係 後期高齢者医療担当
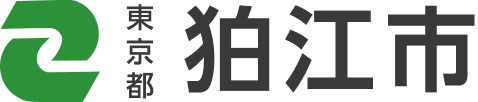
 印刷
印刷
 戻る
戻る
 ページの先頭
ページの先頭