国民年金
国民年金について
1.加入する方
国民年金保険料について
2.保険料の納め方
3.免除制度
4.納付猶予制度
5.学生納付特例制度
6.産前産後期間の免除制度
国民年金の受給種類
7.老齢基礎年金
8.障害基礎年金
9.遺族基礎年金
10.特別障害給付金
11.年金生活者支援給付金
12.第1号被保険者の独自給付
国民年金に関する届け出
13.国民年金の手続き
14.保険料の手続き
15.受け取る年金を増やす手続き
16.保険料の手続き
その他
17.都内年金事務所所在地
18.国民年金基金
国民年金について
1.加入する方
国内に住所がある20歳以上60歳未満の外国人を含めたすベての人が加入することになっています。
老齢になったときに老齢基礎年金、病気やけがで生活や仕事が制限されるようになったときに障害基礎年金、配偶者が亡くなったときに子のいる妻、子のいる夫、または子に遺族基礎年金が支給されます。
加入者は職業などによって次の3つのグループに分けられます。
<第1号被保険者>
自営業者、農林漁業者、学生、無職などの人
<第2号被保険者>
厚生年金に加入している会社員、公務員などの人(原則として65歳未満)
<第3号被保険者>
第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人
希望すれば加入できる人(任意加入者)
(1)次の1~4のすべての条件を満たす人
- 日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の人
- 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない人
- 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の人
- 厚生年金保険、共済組合等に加入していない人
※60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きをすることができます。
(2)外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の人
(3)高齢任意加入制度の特例措置
昭和40年4月1日以前に生まれた65歳以上70歳未満で老齢基礎年金の受給資格期間が不足する人は、65歳から70歳になるまでの間、特例として任意加入できます。
国民年金保険料について
2.保険料の納め方
保険料
| 定額保険料(令和7年度) |
月額17,510円 |
|---|---|
| 付加保険料 |
月額400円 |
保険料は、収入や年齢に関わらず、一律の金額です。
定額保険料に付加保険料を上乗せして納付することで、受給する年金額を増やせます。付加保険料の手続きは、「マイナポータル」からマイナンバーカードを利用して電子申請ができます。日本年金機構ホームページ(外部リンク)をご参照ください。電子申請以外の申請方法については、府中年金事務所または保険年金課へお問い合わせください。
※納めた保険料は、年末調整や確定申告の際に社会保険料控除の対象となります。
保険料の納付期限
保険料の納付期限は翌月末日(たとえば4月分は5月末日)です。
納付期限が過ぎた場合でも、納付期限か2年間は納付できます。ただし、納付期限までに納付されない場合は、「未納」として区分され、催促や督促の対象となりますのであらかじめご了承ください。
保険料の納付方法
(1)納付書で納付
日本年金機構から送付される納付書で、金融機関またはコンビニエンスストアの窓口でお支払いください。市役所では納付できません。
納付書を紛失された場合は、府中年金事務所へご連絡ください。
(2)口座振替で納付
翌月末にご希望の口座から自動的に引き落としされます。早割(当月末振替)にすると、1カ月あたり60円の割引になるほか、前納する場合、納付書やクレジットカードで納付するよりも割引が多くなります。府中年金事務所または保険年金課でお申し込みください。
また、「マイナポータル」からマイナンバーカードを利用して、電子申請ができます。日本年金機構ホームページ(外部リンク)をご参照ください。
(3)クレジットカード納付
クレジットカード納付を希望の方は、府中年金事務所または保険年金課でお申し込みください。
(4)Pay-easy(ペイジー)で納付
納付書に記載されている「収納機関番号」、「納付番号」、「確認番号」をPay-easy対応のATM、インターネットバンキングまたはモバイルバンキングの画面に入力します。詳細は、Pay-easyホームページ(外部リンク)でご案内しています。
(5)スマートフォンアプリで納付
スマートフォン決済の利用には納付書と対応する決済アプリが必要です。詳細は、日本年金機構ホームページ(外部リンク)でご案内しています。
※バーコードが印字されない納付書(30万円を超える金額の納付書および延滞金納付書)はスマートフォン決済ができません。
保険料の前納割引
保険料を前納すると割引が適用されます。
【令和7年度国民年金保険料】
| 納付方法 | 1カ月分 | 6カ月分 | 1年分 | 2年分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 月々支払 | 17,510円 | 105,060円 | 210,120円 |
425,160円 |
|
|
月々支払(早割※1) |
17,450円 |
104,700円 |
209,400円 |
423,720円 |
|
| 前納 ※2 |
納付書・クレジットカード納付 |
ー |
104,210円 |
206,390円 |
409,490円 |
|
口座振替 |
ー |
103,870円 |
205,720円 |
408,150円 |
(※1)口座振替は翌月末日振替ですが、当月末振替にすることで月々60円割引になります。
(※2)一定期間の保険料をまとめて前払いすると、保険料が割引されます。
国民年金保険料のお支払に関する詳細について
日本年金機構ホームページ(外部リンク)をご参照ください。
3.免除制度
国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、保険料の納付が免除になる「免除制度」があります。保険年金課または年金事務所に申請してください。後日、日本年金機構が申請した年度の前年所得などを審査して、結果(承認・却下)の通知書を送付します。
マイナポータルを利用して電子申請
「マイナポータル」からマイナンバーカードを利用して、簡単に電子申請ができます!
申請後の状況や審査結果は、マイナポータルの申請状況照会ページで確認できます。
マイナポータルのアカウント設定でメール通知を希望している方には、マイナポータルに審査結果が届くとメールでお知らせします。
日本年金機構ホームページ(外部リンク)をご参照ください。
申請免除の対象となる人
本人、世帯主、配偶者の前年の所得(1月から6月分までの保険料については、前々年の所得)に応じて、その期間の保険料の全額もしくは一部の納付が免除されます。
|
免除区分 |
支払保険料 |
免除の対象となる所得のめやす |
|
全額免除 |
0円 |
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 |
|
4分の3免除 |
4,380円 |
88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
|
半額免除 |
8,760円 |
128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
|
4分の1免除 |
13,130円 |
168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
免除を受けた期間の取り扱い
免除の申請をして承認されると、その期間は受給資格期間に算入されますが、免除区分に応じて将来の年金額が減額されます。
免除された保険料を納付できるようになったとき(追納)
減額された年金給付額を補うために、保険料の「追納制度」があります。免除の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であれば手続きをすることにより、過去10年にさかのぼって納付することができます。
※承認を受けた翌年度から起算して3年度目以降は当時の保険料に一定額の加算金がつきます。
※老齢基礎年金を受けとっている方は追納できません。
免除申請の詳細について
日本年金機構ホームページ(外部リンク)をご参照ください。
4.納付猶予制度
世帯主の所得状況により保険料免除に該当しない50歳未満の人は、保険料の納付が猶予される「納付猶予制度」があります。
マイナポータルを利用して電子申請
「マイナポータル」からマイナンバーカードを利用して、簡単に電子申請ができます!
申請後の状況や審査結果は、マイナポータルの申請状況照会ページで確認できます。
マイナポータルのアカウント設定でメール通知を希望している方には、マイナポータルに審査結果が届くとメールでお知らせします。
日本年金機構ホームページ(外部リンク)をご参照ください。
納付猶予の対象となる人
申請者が50歳未満の人で、本人、配偶者のそれぞれの所得(1月から6月分までの保険料については、前々年の所得)が基準以下であれば、納付が猶予されます。
納付猶予の対象となる本人および配偶者の所得基準
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
納付猶予を受けた期間の取扱い
納付猶予の申請をして承認されると、その期間は受給資格期間に算入されますが、年金額の計算上は含まれません。よって将来の老齢基礎年金の支給額は減額されます。
保険料を納付できるようになったとき(追納)
納付猶予の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であれば手続きをすることにより、過去10年にさかのぼって納付することができます。ただし、承認を受けた翌年度から起算して3年度目以降は当時の保険料に一定額の加算金がつきます。また、老齢基礎年金を受けとっている方は追納できません。
納付猶予制度に関する詳細について
日本年金機構ホームページ(外部リンク)をご参照ください。
5.学生納付特例制度
学生で保険料の納付が困難なときは、「学生納付特例制度」があります。在学期間中の保険料を社会人になってから納めることができる制度です。
マイナポータルを利用して電子申請
「マイナポータル」からマイナンバーカードを利用して、簡単に電子申請ができます!
申請後の状況や審査結果は、マイナポータルの申請状況照会ページで確認できます。
マイナポータルのアカウント設定でメール通知を希望している方には、マイナポータルに審査結果が届くとメールでお知らせします。
日本年金機構ホームページ(外部リンク)をご参照ください。
学生納付特例の対象となる人
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校および各種学校(※1)、一部の海外大学の日本分校(※2)などに在学する学生または生徒で、本人の前年所得(1月から3月までに申請される場合は前々年所得)が基準以下であれば、納付期間が猶予されます。
(※1)各種学校:修業年限が1年以上で、都道府県知事の許可を受けている学校
(※2)日本分校:文部科学大臣が個別に指定した課程に在籍する学生
学生納付特例の対象となる本人の所得基準
128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
学生納付特例の承認期間について
学生納付特例の承認期間は、4月から翌年の3月までです。申請手続きは毎年必要です。
学生納付特例の承認を受けた期間の取り扱い
学生納付特例の申請をして承認されると、その期間は受給資格期間に算入されますが、年金額の計算上は含まれません。よって将来の年金額は減額されます。
保険料を納付できるようになったとき(追納)
学生納付特例の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であれば手続きをすることにより、過去10年にさかのぼって納付することができます。ただし、承認を受けた翌年度から起算して3年度目以降は加算金がつきます。
学生納付特例制度に関する詳細
日本年金機構ホームページ(外部リンク)をご参照ください。
6.産前産後期間の免除制度
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産された方等を含みます)。
対象
国民年金第1号被保険者で平成31年2月1日以降に出産した人
※平成31年4月分以降の保険料が免除対象です。
申請方法
出産予定日の6カ月前から申請可能です。年金事務所または保険年金課で申請してください。
マイナポータルを利用して電子申請
「マイナポータル」からマイナンバーカードを利用して、簡単に電子申請ができます!
申請後の状況や審査結果は、マイナポータルの申請状況照会ページで確認できます。
マイナポータルのアカウント設定でメール通知を希望している方には、マイナポータルに審査結果が届くとメールでお知らせします。
日本年金機構ホームページ(外部リンク)をご参照ください。
産前産後期間の免除制度の詳細
日本年金機構ホームページ(外部リンク)をご参照ください。
国民年金の受給種類
7.老齢基礎年金
老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上である場合に、65歳から受給できます。なお、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年に満たない場合でも、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が10年以上である場合には、老齢基礎年金を受給できます。
受給資格期間とは
老齢基礎年金を受けるために必要な期間(受給資格期間)
| 国民年金の保険料を納めた期間 |
これらを合計して |
| 保険料の免除(全額、4分の3、半額、4分の1)を受けた期間 (免除の承認を受けても、それぞれ4分の1納付、半額納付、4分の3納付をしないと未納扱いとなります) |
|
| 昭和36年4月以後の厚生年金の被保険者期間または共済組合の組合員期間(20~60歳) | |
| 第3号被保険者であった期間 | |
| 合算対象期間(カラ期間)(※) |
※合算対象期間 (カラ期間) には、下記の事例などがあります。
・厚生年金や共済組合加入者の配偶者で昭和36年4月から昭和61年3月までの間で国民年金に任意加入していなかった期間
・昭和36年4月以降、厚生年金等の脱退手当金を受けた期間
・昭和36年4月以降の海外居住期間(20歳以上60歳未満)で任意加入していなかった期間
・平成3年3月以前に20歳以上の学生が任意加入していなかった期間
このほかにも合算対象期間となる期間がありますので、詳しくは府中年金事務所にご確認ください。
年金額(令和7年度)
40年間保険料を納めた場合、831,700円(昭和31年4月1日以前に生まれた人は829,300円)です。保険料を納めなかった期間があるとその期間に応じて減額されます。付加保険料を納めた期間がある人は、200円×付加保険料納付月数が上乗せで支給されます。
|
831,700円 |
納めた月数+A+B+C+D (免除された月数※) 480月 |
=年金額 | |
※【免除された月数と計算率】
保険料を免除された月数は下記の式で計算します。
| 免除された月数 | 保険料の免除割合 | 計算式 | 平成21年3月分までの計算式 |
|---|---|---|---|
| A |
全額 |
A=月数×1/2 |
A=月数×1/3 |
| B |
4分の3 |
B=月数×5/8 |
B=月数×1/2 |
| C |
半分 |
C=月数×3/4 |
C=月数×2/3 |
| D |
4分の1 |
D=月数×7/8 |
D=月数×5/6 |
繰り上げ支給と繰り下げ支給
繰り上げ支給
60歳から64歳の間に繰り上げて年金を請求できます。この場合、65歳で請求したときに支給される額から一定率で生涯減額支給されます。また、繰上げ支給を受けた後は障害基礎年金を受給できない点、65歳になるまでは遺族厚生年金と併給はできない点などにご注意ください。
繰り下げ支給
66歳から70歳の間に繰り下げて年金を請求できます。この場合、65歳で請求したときに支給される額から一定率で生涯増額支給されます。
老齢基礎年金の請求書の提出先
第1号被保険者期間のみの人
年金事務所または保険年金課
第2号または第3号被保険者期間のある人
年金事務所
老齢基礎年金の詳細について
日本年金機構ホームページ(外部リンク)をご参照ください。
8.障害基礎年金
国民年金加入中や20歳になる前に初診日のある病気やけがが原因で、生活や仕事が制限されるようになった場合は、一定の要件を満たすと年金が受けられます。また、60歳以上65歳未満で老齢基礎年金を受給していない国内在住の人も対象です。障害基礎年金の等級の基準は、障害者手帳の基準とは異なりますのでご注意ください。
障害基礎年金を受けるための要件と、保険料の納付要件の両方を満たす方に支給されます。
障害基礎年金を受けるための要件
下記の1~3のいずれかに該当する方
- 初診日が20歳前の方(本人の所得が一定の限度額を超える場合には、年金の一部または全部の支給が停止されます)
- 初診日が国民年金の被保険者であった方
- かつて国民年金に加入していて、初診日が60歳から65歳で日本国内に住所がある方
保険料の納付要件
初診日の前日において、次の保険料納付要件のいずれかを満たしていること
- 初診日の月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間(免除※・納付猶予の期間を含む)が3分の2以上あること
※一部免除の場合は、免除とならない保険料の支払いをしていることが条件です。 - 初診日において65歳未満であり、初診日の月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がないこと。
年金額(令和7年度)
障害等級1級
1,039,625円(昭和31年4月1日以前に生まれた人は1,036,625円)
障害等級2級
831,700円(昭和31年4月1日以前に生まれた人は829,300円)
子の加算
障害基礎年金の受給権を得たときや受給権を得たあとに、その方によって生計を維持されている子がいる場合に下記の金額が加算されます。
子は、「18歳到達年度末日までの子」または「20歳未満で国民年金法施行令に定める障害等級に該当する障害の状態にある子」に限られます。
| 子の数 | 加算額 |
|
1人 |
239,300円 |
|
2人 |
478,600円 |
|
3人以上 |
2人のときの額+3人目以降の1人につき |
障害基礎年金の請求書の提出先
初診日に第1号被保険者であった人
年金事務所または保険年金課
初診日に第2号または第3号被保険者であった人
年金事務所
障害基礎年金の詳細について
日本年金機構ホームページ(外部リンク)をご参照ください。
9.遺族基礎年金
国民年金加入中の被保険者や老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方が死亡したとき、その方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。
遺族基礎年金を受けるための要件
下記の1~4のいずれかに該当する方が死亡したときに、生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。
子は、「18歳到達年度末日までの子」または「20歳未満で国民年金法施行令に定める障害等級に該当する障害の状態にある子」に限られます。
- 国民年金の被保険者(※)
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有している方(※)
- 老齢基礎年金の受給権者(保険料納付期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限る)
- 保険料納付期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方
※1・2の場合は、下記の納付要件を満たしていることが必要です。
保険料の納付要件
死亡日の前日において、次の保険料納付要件のいずれかを満たしていること
- 死亡日が含まれる月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間(免除※・納付猶予の期間を含む)が3分の2以上あること
※一部免除の場合は、免除とならない保険料の支払いをしていることが条件です。 - 死亡日に65歳未満である場合は、死亡日の月の前々月までの直近1年に保険料の未納期間がないこと
年金額(令和7年度)
子のある妻(夫)に支給される年金額
| 子の数 | 年金額 |
|
1人 |
1,071,000円(昭和31年4月1日以前に生まれた人は1,068,600円) |
|
2人 |
1,310,300円(昭和31年4月1日以前に生まれた人は1,307,900円) |
|
3人以上 |
2人のときの額+3人目以降の1人につき |
子のみに支給される年金額
| 子の数 | 年金額 |
|
1人 |
831,700円 |
|
2人 |
1,071,000円 |
|
3人以上 |
2人のときの額+3人目以降の1人につき |
遺族基礎年金の請求書の提出先
死亡日に第1号被保険者であった人
年金事務所または保険年金課
死亡日に第2号または第3号被保険者であった人
年金事務所
遺族基礎年金の詳細について
日本年金機構ホームページ(外部リンク)をご参照ください。
10.特別障害給付金
国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障がい者の方に支給されます。
特別障害給付金を受給できる方
下記の1または2に該当する方で、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在障害基礎年金の1級・2級相当の障がいの状態にある方
- 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生(定時制、夜間部、通信を除く)
- 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった、厚生年金等に加入していた方の配偶者
支給額(令和7年度)
- 障害基礎年金1級相当に該当する方:月額56,850円
- 障害基礎年金2級相当に該当する方:月額45,480円
※支給額は、毎年度、物価の変動に応じて改定されます。
※ご本人に老齢基礎年金などが支給されている場合、または一定額以上の所得がある場合は、支給が調整または停止されることがあります。
ご注意いただきたいこと
- 給付金は、請求月の翌月分から支給されます。申請に必要な書類がすべて揃わない場合であっても、請求書の受け付けをいたします。後日、不足している書類等をご提出ください。
- 必要な書類を整えていただいた場合でも、審査の結果、支給の要件に該当しない場合は不支給となりますので、あらかじめご了承ください。
- 給付金の支給を受けた方は、申請により国民年金保険料の免除を受けることができます。
特別障害給付金の詳細について
日本年金機構ホームページ(外部リンク)をご参照ください。
11.年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入やその他の所得額が一定額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
年金生活者支援給付金の種類と給付額(令和7年度)
1.老齢年金生活者支援給付金
以下の要件をすべて満たしている方が対象者です。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受けている。
- 請求される方の世帯全員の市民税が非課税となっている。
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が878,900円以下である。
| 給付額 |
月額5,450円(令和7年度)を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次のAとBの合計額となります。 |
|
|
A |
保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,450円×保険料納付済期間/480月 |
|
|
B |
保険料免除期間に基づく額(月額)=11,551円×保険料納付済期間/480月 |
|
2.障害年金生活者支援給付金
以下の要件をすべて満たしている方が対象者です。
- 障害基礎年金を受けている。
- 前年の所得が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円」以下である。
| 給付額 |
障害年金1級の方 |
(月額)6,813円 |
|
障害年金2級の方 |
(月額)5,450円 |
3.遺族年金生活者支援給付金
以下の要件をすべて満たしている方が対象者です。
- 遺族基礎年金を受けている。
- 前年の所得が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円」以下である。
|
給付額 |
(月額)5,450円 |
ご注意いただきたいこと
- 給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。
- 支給要件を満たす場合、2年目以降のお手続きは原則不要です。
- 支給要件を満たさなくなった場合、「年金生活者支援給付金不該当通知書」をお送りします。
年金生活者支援給付金の詳細について
日本年金機構ホームページ(外部リンク)をご参照ください。
12.第1号被保険者の独自給付
付加年金
第1号被保険者・任意加入被保険者が付加保険料(月額400円)を納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。
付加保険料の手続きは、「マイナポータル」からマイナンバーカードを利用して電子申請ができます。日本年金機構ホームページ(外部リンク)をご参照ください。
年金額
200円×付加保険料納付月数
寡婦年金
第1号被保険者の期間(保険料納付済期間と免除期間)が10年以上(平成29年8月1日より前の死亡の場合は25年以上)ある夫が亡くなったときに、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。
年金額
夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3
※支給されない場合
・夫が、障害基礎年金の受給権者であった、または、老齢基礎年金を受給したことがある場合
・妻が、繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している場合
死亡一時金
第1号被保険者として保険料を納めた月数(一部納付の場合は月数が変わります)が36月以上ある方が、老齢基礎年金または障害基礎年金を受給せずに亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族に支給されます。
支給金額
| 保険料納付済期間 | 一時金の額 |
|
36月以上180月未満 |
120,000円 |
|
180月以上240月未満 |
145,000円 |
|
240月以上300月未満 |
170,000円 |
|
300月以上360月未満 |
220,000円 |
|
360月以上420月未満 |
270,000円 |
|
420月以上 |
320,000円 |
- 付加保険料を36月以上納めていたときは、8,500円が加算されます。
- 遺族が遺族基礎年金を受給できるときは、死亡一時金は支給されません。
- 寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択することになります。
- 死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。
第1号被保険者の独自給付の詳細について
日本年金機構ホームページ(外部リンク)をご参照ください。
国民年金に関する届け出
13.国民年金の手続き
| こんなとき | どうする | 届出先 |
|---|---|---|
|
20歳になった方 |
20歳の誕生月の前々月以降に海外から転入された方で、厚生年金加入者以外は国民年金に加入の手続きをする |
第1号被保険者:保険年金課 |
|
第3号被保険者:配偶者の勤務先 |
||
| 会社を退職したとき |
第1号被保険者への種別変更の手続きをする(被扶養配偶者も同様) |
保険年金課 |
|
結婚や退職などで配偶者の扶養になったとき |
第3号被保険者への種別変更の手続きをする |
配偶者の勤務先 |
|
配偶者の扶養から |
第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きをする |
保険年金課 |
|
配偶者が会社を |
引き続き第3号被保険者となる手続きをする |
配偶者の新しい勤務先 |
|
海外に居住するとき |
国民年金の資格喪失手続きをする |
保険年金課 |
|
任意加入の手続きをする |
||
|
海外から帰ったとき |
国民年金の加入手続きをする(任意加入者も手続きが必要) |
保険年金課 |
|
基礎年金番号通知書を |
再交付の手続きをする |
第1号被保険者:保険年金課・年金事務所 |
|
第3号被保険者:年金事務所 |
マイナポータルを利用して電子申請
国民年金被保険者の資格取得(種別変更)の届出は、「マイナポータル」からマイナンバーカードを利用して、簡単に電子申請ができます!
詳細は、日本年金機構ホームページ(外部リンク)をご参照ください。
14.保険料の手続き
| こんなとき | どうする | 届出先 | |
|---|---|---|---|
| 出産をする・したとき |
産前産後免除の申請をする |
保険年金課・年金事務所 |
|
| 口座振替を申し込む (変更する)とき |
国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書を提出する |
振替先金融機関・保険年金課・年金事務所 |
|
| クレジットカード納付を 申し込む(変更する)とき |
国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書を提出する |
保険年金課・年金事務所 |
|
| 納付書を紛失したとき |
納付書の再発行の手続きをする |
年金事務所 |
|
| 保険料を納めるのが困難なとき |
国民年金保険料免除(納付猶予)の申請をする |
保険年金課・年金事務所 |
|
| 学生で収入が少ないとき |
学生納付特例の申請をする |
||
マイナポータルを利用して電子申請
口座振替の手続きは、「マイナポータル」からマイナンバーカードを利用して、簡単に電子申請ができます!
詳細は、日本年金機構ホームページ(外部リンク)をご参照ください。
15.受け取る年金を増やす手続き
| こんなとき | どうする | 届出先 |
|---|---|---|
| 定額以上の保険料を納めたい |
付加保険料の手続きをする |
保険年金課 |
|
国民年金基金に加入する |
詳細は、全国国民年金基金ホームページ(外部リンク)をご覧ください。 |
|
| 60歳から65歳になるまで |
任意加入の手続きをする |
保険年金課 |
マイナポータルを利用して電子申請
付加保険料の手続きは、「マイナポータル」からマイナンバーカードを利用して、簡単に電子申請ができます!
詳細は、日本年金機構ホームページ(外部リンク)をご参照ください。
16.国民年金を受ける手続き
| こんなとき | どうする | 届出先 |
|
65歳になったとき |
老齢基礎年金の受給手続きをする |
【第1号被保険者期間のみ】年金事務所・保険年金課 |
|
【第3号被保険者期間を含む】年金事務所 |
||
|
病気やけがによって |
障害基礎年金の受給手続きをする |
【初診日が20歳前】保険年金課 |
|
【初診日が第1号被保険者期間】保険年金課 |
||
|
【初診日が第3号被保険者期間】年金事務所 |
||
|
国民年金加入中の人が |
遺族基礎年金の請求手続きをする |
【死亡日が第1号被保険者期間】保険年金課 |
|
【死亡日が第3号被保険者期間】年金事務所 |
||
|
寡婦年金・死亡一時金の請求手続きをする |
保険年金課 |
|
|
年金を受給中の人が |
死亡届(未支給年金)の手続きをする |
年金事務所 |
その他
17.都内年金事務所所在地
日本年金機構ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
18.国民年金基金
自営業などの方がゆとりある老後を過ごすことができるように、基礎年金に加え、2階建ての給付を行う公的な年金制度です。
詳細は、全国国民年金基金ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
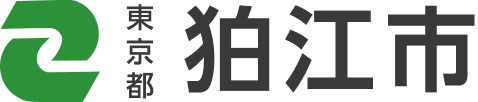
 印刷
印刷
 戻る
戻る
 ページの先頭
ページの先頭