|
【事務局】
皆様お揃いですので、狛江市介護保険推進市民協議会を始めさせていただきます。なお、物部委員と末田委員から事前に欠席の連絡を受けております。本協議会の委員総数は13名となっておりますが、本日11名の委員が御出席されており、狛江市介護保険条例第25条第2項に規定する委員の過半数の出席という会議開催の要件を満たしておりますので、本協議会は有効に成立しております。
本日は改選後初めての会議となりますので、皆様の机上には委嘱状を配布しております。御確認をお願いいたします。
また、会長・副会長の選出、諮問までは事務局の方で進行させていただきますので、よろしくお願いいたします。まず初めに、福祉保健部長より一言御挨拶をさせていただきます。
【委員】
皆さんこんばんは。福祉保健部長の宗像でございます。本日は忙しいところ、遅い時間に御参加いただきまして誠にありがとうございます。また、この度は狛江市介護保険推進協議会委員の方、お引き受けいただきまして誠にありがとうございます。
本協議会でございますが、狛江市における介護保険制度の円滑かつ適切な運営を図るため、介護保険制度の適切な運営に関することについて、調査・審議いただく機関となってございます。介護保険を取り巻く情勢では、生産年齢人口が減少し続ける一方、2050年までは高齢者人口が増加することが推定されており、超高齢社会に対処するべく、第9期介護保険事業計画の策定について、当協議会で審議をしていただきました。また、令和6年度は3年に一度の介護報酬改定があり、介護人材不足や物価高が進行する中で、「地域包括ケアシステムの深化・推進」「自立支援・重度化防止に向けた対応」、「良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり」等を図るとして、運営基準等の諸般の改正がされたところでございます。高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自分らしい生活を続けることができるよう、医療、介護、住まい、介護予防及び生活支援が切れ目なく提供される地域包括ケアシステムのさらなる深化・推進が課題と考えております。
令和7年度からは第10期の介護保険事業計画の策定に向けて準備作業が始まりますので、皆様のお力をお借りいただけますよう、よろしくお願い申し上げます。
【事務局】
ありがとうございました。
それでは、本日の配布資料の確認をさせていただきます。
本日の配布資料は、
- 令和6年度第1回介護保険推進市民協議会アジェンダ
- 資料1 狛江市介護保険推進市民協議会委員名簿
- 資料2 諮問書(狛江市における地域密着型サービスの基盤整備について)(写)
- 資料3 会議及び会議録の取り扱いについて(案)
- 資料4 狛江市介護保険推進市民協議会の設置に関する条文(狛江市介護保険条例より抜粋)
- 資料5 狛江市第1次地域共生社会推進基本計画~あいとぴあレインボープラン~(第9期狛江市介護保険事業計画)(介護保険関係について一部抜粋)
- 資料6 狛江市第1次地域共生社会推進基本計画~あいとぴあレインボープラン~実施計画(介護保険関係について一部抜粋)
- 資料7 狛江市第1次地域共生社会推進基本計画、実施計画における評価方法について(案)
- 資料8 中長期的な地域の人口動態やサービス需要を踏まえたサービス基盤の整備について
- 資料9 狛江市内地域密着型サービス事業所一覧(令和6年9月1日時点)
- 資料10 狛江市における多機能系サービスのニーズの将来見込みについて
- 資料11 狛江市周辺の小多機・看多機事業所一覧
- 資料12 令和6年度主任ケアマネ連絡会(小多機・看多機勉強会)アンケート
- 資料13 令和6年度第2回主任ケアマネ連絡会アンケート結果について
- 資料14 令和5年度第4回介護保険推進協議会議事録(案)
- 狛江市介護保険推進協議会委員名簿登録用紙
以上になります。不足等がございましたら、事務局までお申し付けください。
それでは、議題の1、委員の紹介についてでございます。資料1として、今回改選された委員の名簿を配付させていただきました。中村委員のところにマイクがございますので、お1人ずつ一言御挨拶お願いいたします。
【委員】
初めまして。中村と申します。神奈川県立保健福祉大学で専門は地域福祉を教えております。介護保険のことはあまり明るくないのですが、どうぞよろしくお願いいたします。
【委員】
こんばんは。公募委員の2号被保険者、片岡尚子です。いつもありがとうございます。
【委員】
第1号被保険者、関と申します。よろしくお願いいたします。
【委員】
皆さん、こんばんは。名前は田中崇と申します。こちらの推進協議会は二期目なのですが、20年位現場で介護の仕事をさせて頂いております。よろしくお願いします。
【委員】
福祉保健部長の宗像でございます。改めまして、よろしくお願いいたします。
【委員】
福祉政策課長の古内洋一と申します。前任の佐渡がですね、3月に退職をいたしまして、その後任でございます。引き続き狛江市の福祉施策をどうぞよろしくお願いいたします。
【委員】
こんばんは。菊地と申します。サービス従事者代表といたしまして、グループホームわらくを運営しております。よろしくお願いいたします。
【委員】
こまえ正吉苑二番館で施設長をしております岩坂大輔と申します。よろしくお願いします。
【委員】
狛江福祉会こまえ苑の事務局長をさせていただいております石黒と申します。また今期も、皆様と介護保険等々につきまして、狛江をより良くしていければと思っております。よろしくお願いいたします。
【委員】
狛江市社会福祉協議会の事務局長、小楠です。今期もよろしくお願いいたします。
【委員】
介護保険が始まってからずっと介護認定審査会の方に関わっております、歯科医師会の代表の長谷川と申します。よろしくお願いいたします。
【事務局】
ありがとうございました。
それでは続きまして、議題の2、会長と副会長の選任についてでございます。
本協議会の会長・副会長は、狛江市介護保険条例第24条第1項に基づき互選によることと定められております。選任の方法につきましては、御意見はございますでしょうか。
事務局一任でよろしいでしょうか。
【委員】
異議なし。
【事務局】
ありがとうございます。
それでは、会長は中村委員、副会長は前期と同様、長谷川委員にお願いできればと思いますが、いかがでしょうか。
【委員】
異議なし。
【事務局】
ありがとうございます。
それでは、お手数ですが、中村委員と長谷川委員は、席の御移動をお願いいたします。
会長・副会長の選任が終わりましたので、議題の3、地域密着型サービスの基盤整備に関する諮問を行います。皆様の机上には資料2として、諮問書の写しを配付させていただいております。諮問書につきましては、福祉保健部長より代理で授与させていただきます。恐れ入りますが、中村会長と福祉保健部長は、御起立をお願いいたします。
【委員】
令和6年11月14日、狛江市介護保険推進市民協議会会長様。狛江市長松原俊雄。狛江市における地域密着型サービスの基盤整備について諮問。狛江市介護保険条例第21条第1項第3号に定めるところにより、下記の事項について、貴協議会の意見を求めます。諮問事項、狛江市における地域密着型サービスの基盤整備に関する事項について。よろしくお願いいたします。
【事務局】
それでは、この後の議事の進行を中村会長よりお願いいたします。
【会長】
改めまして中村です。よろしくお願いいたします。先程自己紹介で告白しましたように、介護保険制度について、さして明るくございません。横浜市の介護保険運営協議会に委員として少し長く関わっておりますけれども、それはどちらかというと、地域福祉という横からの参加を期待されて、ということかなと考えております。狛江市さんとは社会福祉協議会のコミュニティソーシャルワーカーの取組みをいろいろ勉強させていただいておりまして、そのご縁がありまして、時々通わせていただいたり、御案内をいただいております。狛江市はコンパクトなまちで、いろいろな関係者の方々が市に愛着を持っていて、専門機関とか行政の方々への信頼感を持っているなと感じております。そういう意味で横浜市や横須賀市のような中核市で会議体をまとめるのが大変な自治体と比べますと、非常に密着していろんなことができるのかなと思いますし、また市民の方の意識も高いものがあるなと考えております。また、市の取組がCSWを配置する等、非常に先進的で、自らの頭で考えてことをなさっている自治体だなと感じております。狛江市の外からでございますし、介護保険のこともさして明るくありませんが、大役仰せつかりましたので、皆様方のお力をお借りして、進んでいければと思っております。それではよろしくお願いいたします。
では議事を進めていきたいと思います。議題の4、会議及び会議録の取り扱いについて、事務局から説明をお願いいたします。
【事務局】
それでは、議題4、会議及び会議録の取り扱いについて、事務局から御説明させていただきます。資料3をご覧ください。会議については、原則として公開となります。ただし、介護保険条例第6条に該当する場合や、審議事項が個人情報等に関する事項の場合等、会議を公開することがふさわしくないと認められるときは、会議の冒頭で、協議会にお諮りした上で非公開にすることができます。
会議録につきましては、原則として公開となりますが、内容については、要点筆記といたします。会議録における発言者の表記につきましては、会長、副会長、委員とし、委員の皆様の確認を経たうえで、正式決定といたします。また、決定後は、市ホームページに掲載いたします。会議及び会議録の取り扱いについての説明は以上となります。
【会長】
ただいまの議題、会議及び会議録の取り扱いについての説明でございますが、何か御質問、御意見ございますでしょうか。
それでは次の議題に移ります。議題5、狛江市介護保険推進市民協議会の概要について、事務局から御説明をよろしくお願いいたします。
【事務局】
それでは議題5、狛江市介護保険推進市民協議会の概要について、事務局から御説明させていただきます。資料4をご覧ください。本会議は、介護に関する施策の企画立案及びその実施にあたり、利用者等の意見が十分に反映され、市の介護保険制度の円滑かつ適切な運営を図るため、狛江市介護保険条例第20条に基づき設置しております。所掌事項は条例第21条に規定のとおり、第3号、介護保険サービスの基盤整備に関することや、第7号、地域密着型サービスに関すること等について審議をするものです。裏面の第23条の規定のとおり、委員の任期は3年となっております。第24条以降、会議の運営方法につきましては、先の議題で出てきておりますので、ここでは割愛させていただきます。狛江市市介護保険推進市民協議会の概要についての説明は以上となります。
【会長】
ただいまの御説明につきまして、何か御意見、御質問ある方いらっしゃいますでしょうか。それでは、議題6、第9期介護保険事業計画の概要と実施計画について、事務局より御説明
をお願いいたします。
【事務局】
それでは、議題の6、第9期介護保険事業計画の概要と実施計画について、資料5と資料6を用いて事務局から御説明させていただきます。まず、介護保険関係の事業について御説明いたします。
資料5、2ページをご覧ください。狛江市では、狛江市福祉基本条例を制定し、「全ての市民の『であい、ふれあい、ささえあい』を大切にし、人がやさしい、人にやさしい『あいとぴあ狛江』を合言葉に、ともに力を合わせ、お互いにやさしい、うるおいとやすらぎのある福祉のまちづくりを進め、地域共生社会を実現すること」を目指しております。
また、狛江市第4次基本構想を策定し、狛江市の将来都市像を「ともに創る文化育むまち~水と緑の狛江~」としております。
各分野のまちづくりに共通する視点として、お互いを認め支え合い、ともに創る・狛江らしさを活かすの二つの視点を核として、保健・福祉分野においては、複雑化・複合化した地域生活課題を解決し、福祉の「支え手側」と「受け手側」に分かれるのではなく、市民、団体、事業者がそれぞれの役割のもと、支え合いながら、自分らしく活躍できる地域づくりを推進するとともに、行政と連携・協働した包括的な支援体制を整備することで、いつまでも健やかに暮らせるまちを目指していきます。
3ページをご覧ください。第1次地域共生社会推進基本計画の計画期間は令和6年度から令和11年度までの6年間とし、構成計画のうち、介護保険事業計画については、法令の定めに従い、令和6年度から令和8年度までの3年間となっております。
4ページをお開きください。第1次地域共生社会推進基本計画では、基本的価値観として、(1)全ての市民が生涯にわたり、個人として尊重されること、(2)全ての市民が支え合うことの二つを掲げ、基本理念として、「全ての市民が、生涯にわたり個人として尊重され、支え合って、誰もが排除されない地域社会の実現を目指します。」としております。
5ページをご覧ください。この基本理念を実現するために、今後6年間の計画期間内で達成するべき目標として、基本目標1から5の5つの目標を掲げております。
基本目標1「一人ひとりの状況に合わせた切れ目のない相談支援体制の構築」では、支援を必要とする全ての人が、必要とする支援を受けられる仕組みづくりを進めます。
6ページをお開きください。基本目標2「『つながり』を実感できる地域づくり」では、市で生活する一人ひとりが地域生活課題に対し、自分自身の問題として受け止め、市、市民及び事業者が連携、協働して解決に向けてみんなで支え合う地域づくりを進めます。
基本目標3「社会参加を進めるシステムづくり」では、既存の社会参加に向けた取組では対応できない、狭間のニーズのある市民が地域社会に参加できるシステムを構築していきます。
基本目標4「総合的で切れ目のない生活支援システムづくり」では、全ての市民が地域で豊かに暮らせるようにするため、福祉サービスを必要とする市民や、その世代が抱える様々な課題を把握し、関係機関との連携により、フォーマル、インフォーマルなサービスを活用して、総合的で切れ目のない生活支援システムを構築していきます。
7ページをご覧ください。基本目標5「多機関で協働して支援に当たる体制の構築」では、既存の相談支援機関をサポートし、包括的な支援体制の構築を支援します。
次に8ページをお開きください。8ページから11ページまでは、先の五つの基本目標を踏まえた施策体系を表したものになります。このうち、介護保険関係の事業としましては、10ページから11ページにあります、
施策No4-4 多様な福祉人材の確保・育成に向けた支援体制を充実させます。
施策No4-8 地域密着型サービスの整備を推進します。
施策No4-9 介護サービスの給付の適正化を推進します。
施策No4-10 介護施設・事業所における適正な運営を支援します。
施策No5-6 年齢にかかわらず、サービスを適切に受けられるよう、介護保険サービスと障がい者福祉サービスの連携を推進します。
施策No5-7 介護保険サービスの質の向上を目的として、事業者間の連携を強化します。
の6本となります。
次に15ページをお開きください。施策No4-4では、重点取組の3点目、「介護人材確保対策の推進」を掲げております。
16ページをお開きください。施策No4-8では「小規模多機能型居宅介護または看護小規模多機能型居宅介護の整備の検討」を掲げております。こちらは、後の議題に繋がるものとなっております。
施策No4-9では、国が定める介護給付費適正化の3事業として、要介護認定の適正化、ケアプラン等の点検の実施、医療情報との突合・縦覧点検の実施の3事業を掲げております。
17ページをご覧ください。施策No4-10では、介護施設・事業所の指導検査の実施、施設・事業所の感染症対策の推進、介護人材確保対策の推進の3事業を掲げております。
18ページをお開きください。施策No5-6では介護保険事業として、主任介護支援専門員を対象とした障がい福祉制度の勉強会等の実施を掲げております。
19ページになります。施策No5-7につきましては、各種連絡会の開催、介護関係者サイト「ケア倶楽部」を通じた介護関係情報の共有、国等の介護情報基盤整備に伴う対応、介護事故情報の共有の4事業を掲げております。
続きまして資料6をご覧ください。1枚おめくりいただきまして、「狛江市第1次地域共生社会推進基本計画~あいとぴあレインボープラン~実施計画」につきましては、資料5のあいとぴあレインボープランの実施計画として、各事業の具体的な工程を示したものになります。計画書4-4「多様な福祉人材の確保、育成に向けた支援体制を充実させます。」に対応する事業として、4-4-3「介護人材確保対策の推進」を掲げており、「研修受講費の助成」と「新たな助成・支援対策の検討及び実施」を掲げております。
3ページに移ります。計画書の4-8「地域密着型サービスの整備を推進します」に対応する事業としましては、4-8-1「小規模多機能型居宅介護または看護小規模多機能型居宅介護の整備の検討」を掲げており、事業内容としては、「将来のニーズの動向を踏まえた施設整備の必要性を検討」としております。この点につきましては、後の議題8で御検討いただくことを予定しております。
次に4ページに移ります。4-9「介護サービスの給付の適正化を推進します」では、4-9-1、要介護認定の適正化と事務の効率化の推進、次のページに移りまして、4-9-2、ケアプラン等の点検の実施、4-9-3、医療情報との突合・縦覧点検の実施の3事業を掲げております。
次に6ページから7ページとなります。4-10「介護施設・事業所における適正な運営を支援します」では、4-10-1、介護施設・事業所の指導検査の実施、4-10-2、施設・事業所の感染症対策の推進、4-10-3、介護人材確保対策の推進の3事業を掲げております。
次に7ページから8ページになります。5-6「年齢にかかわらず、サービスを適切に受けられるよう、介護保険サービスと障がい者福祉サービスの連携を推進します。」では5-6-1、主任介護支援専門員を対象とした障がい福祉制度の勉強会等の実施を挙げております。
5-7「介護保険サービスの必要な向上を目的として、事業所間の連携を強化します。」では、5-7-1、各種連絡会の開催、5-7-2、介護関係者サイト「ケア倶楽部」を通じた介護関係情報の共有、次のページ、5-7-3、国等の介護情報基盤整備に伴う対応、11ページ、5-7-4、介護事故情報の共有の4事業を掲げております。
続きまして、介護保険サービスの3年間の推計について御説明をいたします。
再度、資料5、20ページをご覧ください。第9期計画の計画期間中の介護保険サービスの推計について御説明させていただきます。介護保険事業計画では、今後3年間の介護保険料を決定するため、計画期間中の介護保険サービスの給付費を推計しております。推計の流れとしましては、20ページに記載のとおりでございます。
まず1、被保険者数の推計としまして、コーホート変化率法で、計画期間中の被保険者数を推計いたします。
続いて2、要支援・要介護認定者数の推計としまして計画期間中の認定者数を推計し、3、サービス別の量の見込みとしまして、各介護保険サービスのサービス量を推計いたします。
続いて4、保険給付費、地域支援事業費の推計としまして、3年間の介護給付費を推計し、最後に5、保険料基準額の設定としまして、第9期の計画期間中の3年間の介護保険料基準額を設定いたします。
この推計は、介護保険事業計画を改定するために行うことになっており、次回の推計は、再来年度、令和8年度を予定しております。
続いて、推計結果について御説明いたします。資料の21ページをご覧ください。被保険者数と医療支援要介護認定者数の推計結果は、21ページと次の22ページの表のとおりでございます。こちらも中長期的な推計につきましては、後の議題8で、改めて御報告いたします。
続きまして23ページをご覧ください。介護保険サービスの推計の流れは、23ページの図のとおりでございます。先程の認定者数の推計結果をもとに、サービスごとに見込み量を推計し、各サービスの給付費を推計いたします。令和6年度から令和8年度までの3年間のサービス
給付費の総額は29ページの下の表、ケ、サービス給付費総額の表の中に第9期計画の合計というところにありますとおり、約231億7,518万5,000円と推計しております。
続きまして30ページをご覧ください。30ページに介護保険の財源構成を記載しております。居宅サービスと施設サービス、介護予防・日常生活支援事業と包括的支援事業、任意事業のそれぞれに財源構成が異なりますが、第1号被保険者の保険料については、いずれの事業も23%を負担していただくことになっております。
続いて31ページをご覧ください。保険料基準額の算出の流れとしましては、31ページの図のとおりとなります。先程の給付費総額に、第1号被保険者の負担割合である23%を掛けたうえで、過去の保険料の余剰分である準備基金の取崩額等を引いて保険料収納必要額を算出いたします。その後、予定保険料収納率や所得段階別の負担割合で補正したあとの被保険者数を用いて、保険料基準額を算出いたします。具体的な数字は32ページの表のとおりでございます。3年間の計画期間中の保険料収納必要額は、上の表の一番下にありますとおり、およそ49億90万8,304円となっております。これにより、第9期の介護保険料の保険料基準額は33ページにありますとおり、6,450円と設定させていただきまして、所得段階区分と各段階の保険料を表のとおり、設定いたしました。
第9期介護保険事業計画の概要と実施計画についての御説明は以上でございます。
【会長】
御説明ありがとうございました。第9期介護保険事業計画の概要と実施計画についてということで、今年の3月にとりまとめられた資料ということになりますが、御質問ある方いらっしゃいますでしょうか。
それでは、次の議題に移りまして、議題7、狛江市第1共生社会推進基本計画実施計画における評価方法について説明をお願いいたします。
【事務局】
では引き続き、事務局より説明をさせていただきます。資料7をお手元に御準備いただければと思います。こちら資料7の96ページ、第6章のこの計画の推進に向けてという部分についての御説明となっております。よろしくお願いいたします。こちらですが、先程基本計画の説明を資料5で、実施計画というものを資料6で御説明をさせていただきました。それで、こちらの基本計画と実施計画がそもそも何なのかということを簡単に御説明させていただければと思います。
まず基本計画でございますが、先程説明がございましたように、令和6年度から令和11年度までの計画を定めたものとなってございます。なお、介護保険推進事業計画につきましては、3ヵ年で見直しを行いますので、厳密には令和6年度から令和8年度までと、令和9年度から令和11年度までということで第9期と10期でそれぞれ分かれる形となっておりまして、この計画を通している期間として基本計画がございます。その基本計画を実施するためにということで、資料6にございますとおり、施策というものを先程御説明させていただきましたが、施策でどういうことをやっていくかということが記載されているものとなってございます。例えば、資料6の1ページ、2ページをご覧いただければと思いますが、こちらの4-4-3で介護人材確保の推進というものを掲げておりますが、この中に研修受講費の助成というのがございまして、下の方に事業取組内容として記載をさせていただいております。ここで目標を助成人数という形で定めまして、初任者研修が12人、実務者研修が5人というのを6年、7年、8年という形で確保していきますというような形で、研修の受講人数を確保することで介護人材確保対策を推進するという体裁となってございます。
続いて、こちらの立てられた計画について、実際に実施できているかどうかの評価を実際にしていくことになります。再度基本計画の96ページ、97ページに戻りますが、計画を単年度ごとに設定しておりますために、実際に計画を実施しまして、進捗がどうだったということをローリング方式ということで、その環境変化等考慮して、数字の見直しをさせていただく形をとらせていただいております。
また、基本計画及び実施計画の評価ということで、先程申し上げましたこの数字に対して、事務局の方でどう評価をしていくかという部分の説明として、今回、資料7を御用意させていただきました。基本計画の98ページとあわせて資料7をご覧いただきながら、御説明を聞いていただければと思っております。こちらの99ページと同じものを、資料7に記載させていただいておりますが、この図の中の①市の実施計画の策定というのが、今、説明をさせていただいたとおり、令和6年9月に実施計画を策定をさせていただきました。現在この②という段階、事業の推進を行っているというところになっております。
続きまして、③が年度末から来年の早々にかけて実施する内容となっておりまして、実施計画の進捗状況を各所管課の方で評価いたしまして、その結果を地域共生社会推進会議に報告いたします。
続きまして④ですが、市の実施計画の評価結果報告を受け、それを評価するということで市民福祉推進委員会等を記載させていただいております。介護保険推進市民協議会の皆様におかれましてはですね、少し馴染みのない言葉がそろっておりますので、御説明をさせていただければと思います。まず、地域共生社会推進会議というものは何かというところでございますが、この1、概要に記載をさせていただいておりますとおり、狛江市地域共生社会推進会議の設置及び運営に関する要綱の第1条の規定に基づきまして、設置した会議体でございます。所掌事務というところで、この(1)から(4)までに記載してございますが、地域包括ケアシステムの推進及び地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制の整備の検討に関すること、必要な連絡及び調整に関すること、計画の策定及び改定に関すること、その他必要な事項ということになっております。3番の構成をご覧いただければと思いますが、市役所の中の(1)から(19)までが市役所の内部の組織体となってございまして、福祉の部署に限らず、政策部門、児童関係の部署、まちづくり関係の部署、学校教育に関する部署等も構成いたしまして、様々な面でこの計画を評価するという形になっております。また、各地域包括支援センターから1名、社会福祉協議会からも1名選出をしていただいて、この地域共生社会推進会議というものを構成しておりまして、評価を行うという形となっております。
続きまして、この評価を受けまして④の市民福祉推進委員会のところですが、今回この基本計画を策定していただくにあたりまして、介護保険推進市民協議会の中で、介護保険推進事業計画の策定に携わっていただいておりますが、その他の部分につきまして、この市民福祉推進委員会及びその下にあります小委員会で、計画の策定に携わっていただきまして、計画の策定をしております。こちらの中で、策定に携わっていただいたというところと、それに基づきました評価をしていただくという形を考えてございます。
前置きが長くなりましたが、2ページ、3ページをそれぞれご覧いただければと思います。先程、実施計画ということで、主管課でどういう計画を立てるかいう設定をさせていただきました。計画の進行について、今年度末を予定しておりますが、目標とおり進行している場合、進行していない場合で、どういう評価をしていくかという案を仮に作らせていただきましたので、御紹介させていただきます。
こちら、実施計画の1-1で、介護保険の中ではなくて、地域福祉計画全般に関する部分となっておりますが、この中で、福祉のつなぐシート登録システムというものを、民間事業者への拡大推進という目標を掲げております。どういうものかといいますと、市役所以外に、支援が必要と思われる方または世帯が見つかりましたら、市の方につないでいただきたいということで福祉のつなぐシートというものを導入しております。
この事業ですが、市役所だけでなく、民間事業者、例えば金融機関、携帯電話販売業者やクリーニング事業者といった市内の様々な民間事業者にも御協力をいただきまして、支援が必要と思われる方を見かけられた、窓口で対応されたといった時に、それを市に、こういう方がいらっしゃったので、支援してくださいというような形で、早期発見・早期支援に取り組むために、福祉のつなぐシートというものを導入しております。
この事業の目標といたしまして、活用民間事業者として今年度は15事業者以上、令和7年度は25事業者以上、確保していきますという目標を掲げてございます。これに対しまして、令和6年度目標とおり進行してる場合ということでございますが、仮に18事業者確保できましたとなった場合につきましては、進捗状況評価としては、目標とおり進行しているため、A評価とさせていただきまして、評価の理由というところで、福祉のつなぐシート登録システムの活用民間事業者を確保できました、また、実際に何件、福祉のつなぐシートを使って市に案件をつないでいただきましたということで、質及び量の部分で評価をしていきたいと考えております。
また、目標とおりに進行した場合につきましても、計画を進行するうえで顕在化した課題を掲げていきたいと考えております。その課題について次年度以降どうやって対応していくかというものを記載する「次年度以降の取組方針」という項目を記載してございます。
続きまして目標とおり進行していない場合、3ページをご覧いただければと思います。狛江市では、現在重層的支援体制整備事業という制度を利用してございます。
事業の中で、重層的支援会議及び支援会議という会議を開催するということを掲げております。
重層的支援会議は、簡単に申し上げますと、支援対象の方の同意を経て開催する会議となってございます。
また、支援会議の方はですね、同意を経ずとも開催できる会議体となっております。
基本的に個人情報をやりとりする会議体ですので、本来であれば本人同意を得る必要がありますが、実際に支援をする場面になりますと、なかなか本人同意を得ることができない場合もございます。意思の確認ができない方もおりますので、社会福祉法第106条の規定に基づき、守秘義務を課した上で、支援会議という形で、本人の同意がなくても、会議体が開催できるということになっております。こちらは、今年度6回以上開催をしますという目標値を掲げさせていただいております。
また会議体を進行いたします相談支援包括化推進員という方がおりますが、こちらを4人確保しますという目標を掲げさせていただいております。
目標とおり執行していない場合ということで、例えば先程の重層的支援会議及び支援会議の開催の目標を6回以上開催としておりましたが、こちら右にございますとおり、実績値としては4回の開催と仮になったとします。進捗状況評価で見ますと取組の一部に遅れが見られるということになります。一方で相談支援包括化推進委員の方は目標4人のところ4人確保できているということで目標とおり進行しているとさせていただいております。また、その次の、この施策の評価という部分では、一部に遅れが見られるというところでございますので、B評価という評価を入れさせていただいてございます。
この評価の理由というところで、先程も出ておりましたが、質と量という部分で評価をすることになっております。目標値とおり相談支援包括推進委員は確保できましたが、会議の開催は、目標とおりできませんでした。ただ、扱った案件については、支援機関との連携により、適切な支援プランを作成を行って、支援を行うことができましたということを挙げさせていただいてございます。
課題としまして、なぜ4回だったかという部分については、会議の関係者との調整に時間を要しているということで、予定回数を下回る回数しかできなかったというものを仮に挙げさせていただきまして、次年度以降の取組ということで、支援関係者との調整をスムーズに行って、相談支援包括化推進員が動ける体制を構築する必要があるというようなものを掲げております。
このような形で、現在①を市の方で実施計画として策定いたしまして、今年度末に、②につきまして、年度末に記載をするという形で考えております。
続きまして4ページに移らせていただきます。
先程御説明させていただきました、地域共生社会推進会議の中で、実際にその重点取組ごと、1-1-1、1-1-2、1-1-3というように、それぞれどういう形で進行しているのかどうかという評価をいただきたいと思っております。
こちらを受けまして、④の外部評価シート、市民福祉推進委員会等作成という部分ですが、市のこの地域共生社会推進会議で評価したものにつきまして、その評価が妥当かどうかという評価をしていただきたいと考えております。また、評価につきましても、評価のとおりとするという、もしくは評価のとおりではないという判断もあるかもしれませんが、ただそれだけではなく、例えば施策1-1-2にございますとおり、意見についてはという2段目の部分で、狛江市第1次地域共生社会推進基本計画に関する市民福祉推進委員会、高齢小委員会、障がい小委員会及び権利擁護小委員会による進捗状況評価のとおりというようなことを記載しております。
これが何なのかというと、6ページに移らせていただきますが、このような形で、下段の(4)の部分でございますけれども、その評価が妥当かどうかというのを見ていただいて、主管課で作成いたします進捗管理と、この地域共生社会推進会議の評価をご覧いただきながら、もっとこうした方がいいのではないかという御意見をいただいて、まとめさせていただきたいと考えております。説明は以上となります。
【会長】
御説明ありがとうございました。基本計画・実施計画の評価方法についてということで、説明がありました。ただいまの内容につきまして、何か質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。所管課で細かく評価をしたものを、この地域共生社会推進会議でさらに評価をし、所管課の評価をこの連絡会といいますかネットワークの会議の中で、多角的な観点から評価をし、それを市民福祉推進委員会に、いわゆる市役所の事務局案という形で提出をして、市民が参加しています市民福祉推進委員会の方で、内容によっては小委員会で評価したものを市民推進委員会へ、最終的に市民福祉推進委員会の中で評価を取り付けていくということですね。つまり、評価の評価をして、さらにそれを市民の視点で評価をしていくということですね。丹念に評価をします、ということの御説明だったのかなと思うのですが、その理解で間違いないでしょうか。
【事務局】
はい。
【会長】
それではみなさん御意見・御質問いかがでしょうか。
今回の取組は報告書の説明にありましたように、目下の課題として、縦割りを包括化するということと、市民が参加してみんなで支えるまちを創るということを総合的に進めるために、いかにその縦割りを廃するかということで、まずは計画を一つにしてみたということかと思います。そしてその進捗をそれぞれ管理するのではなく、全体として評価することができるように地域共生社会推進会議という仕組みを作ることによって、総合的な評価ができないかというようなチャレンジかと思います。御意見いかがでしょうか。
【委員】
この推進会議というのは、毎回このような人数・部署で毎回やるのでしょうか。それとも、ケースによって、構成メンバーが変わるということでしょうか。
【事務局】
毎回この21部署、厳密に言いますと、地域包括支援センターが3か所ありますので、24部署のメンバーの方で計画の評価いただくということで考えております。
【会長】
他いかがでしょうか。
それでは次の議題に移ります。議題8、令和7年度以降の地域密着型サービスの整備の必要性について、これらは本協議会で必要性を検討するにあたり、検討材料となる現在の状況を事務局から説明をお願いいたします。
【事務局】
それでは、議題の8、令和7年度以降の地域密着型サービスの整備の必要性について、皆様に御議論いただくにあたりまして、事務局から状況を御説明させていただきます。
こちらは、先に事務局の方から御説明させていただいた第9期介護保険事業計画において、4-8-1「小規模多機能型居宅介護または看護小規模多機能型居宅介護整備の検討」として、「中長期的な地域の人口動態や介護ニーズの見込み等を踏まえて整備を検討する」と位置付けられていることから、事務局から現在の状況について御説明させていただいた上で、本日皆様に整備の必要性を御議論いただくものになります。
まず背景となる考え方について御説明させていただきます。資料の8をご覧ください。こちらは第9期計画の策定にあたりまして、厚生労働省から示された資料を抜粋したものになります。第9期計画においては、施設整備にあたりまして、中長期的な人口動態等を踏まえたサービス需要の見込みや、生産年齢人口の動向を踏まえ、バランス良く整備することが重要であるとされています。
具体的には資料の真ん中左側、傾向1としましてサービス需要が中長期的に増加し続ける地域においては四角囲みにありますとおり、特養などの施設の整備に加え、高齢者向けの住まいも含めた基盤整備、在宅生活を支える地域密着型サービスの充実等、地域の資源を効率的に活用しつつ、整備することが重要とされています。
続いて資料の真ん中、傾向2としまして、サービス需要が中長期的に見て、ピークアウトが見込まれる地域においては、下の四角囲みにありますとおりサービス需要のピークアウトを見据えた施設の整備等、地域の実情に応じた対応の検討が重要とされています。
続いて資料の右側、傾向3としまして、サービス需要が中長期的に見て減少する地域においては、介護人材の有効活用の観点から、既存施設の多機能化、共生型サービスの活用等、地域の実情に応じた対応の検討が重要とされています。
また共通の検討課題としまして、資料の一番下の四角囲みにありますとおり、黒丸の一つ目、医療・介護双方のニーズを有する高齢者のサービス需要や、在宅医療の整備状況を踏まえまして医療ニーズの高い居宅要介護者のニーズに柔軟に対応できる看護小規模多機能型居宅介護等の整備の検討や、医療・介護連携の強化も重要とされています。
また黒丸の二点目、中長期的なサービス需要の見込みについてサービス提供事業者を含め、地域の関係者と共有し、地域の実情に応じたサービス基盤の整備のあり方を検討することが重要とされています。
こうした考え方を背景として、この議題では、狛江市の中長期的なサービス需要の見込みを基に地域密着型サービスである小規模多機能型居宅介護、いわゆる小多機や、看護小規模多機能型居宅介護、いわゆる看多機の基盤整備の必要性について御議論いただきたいと考えております。
続きまして、狛江市の指定の状況を御説明いたします。資料9をご覧ください。こちらの資料9は令和6年9月1日時点で狛江市が指定している地域密着型サービス事業所の一覧になります。指定しているサービスの種類は表の一番左の欄に略称で記載しております。市内の指定事業所は1ページの表のとおりになります。地域密着型通所介護事業所につきましては、11事業所、認知症対応型通所介護事業所につきましては、4事業所、認知症対応型共同生活介護事業所、いわゆるグループホームが4事業所となっております。小多機と看多機の事業所はともに狛江市にはございません。
続きまして、狛江市における多機能系サービスのニーズの将来見込みについて御説明いたします。資料10をご覧ください。こちらの資料10は、狛江市における多機能系サービスのニーズの将来見込みについて、推計データを基に推計したものになります。推計の根拠としましては、1ページに記載のとおりでございます。総人口は、黒丸一つ目にありますとおり、各年10月1日時点の住民基本台帳の数字を基に、コーホート変化率法を用いて推計いたしました。
また、四つ目の黒丸にあります小多機と看多機のいずれのサービスも、令和5年度時点の利用者数がおりませんので、単純に推計すると、将来のニーズも無いことになってしまいます。
そのため、近隣市である調布市の平均利用率を基に、認定者数の増加分の平均利用率に相当する人数が新たに利用すると仮定して、将来のニーズを推計いたしました。
こういった背景をもとに推計した結果が、1ページの表のとおりでございます。
続いて2ページをご覧ください。
2ページの表は、平成20年度以降認定者数の対前年増加率を一覧にしたものになります。2ページの下のグラフにありますとおり、認定者数の対前年増加率は、軽度認定者、重度認定者共に、平成20年度以降、ほぼプラスで推移しておりますが、平成24年度をピークに減少傾向にあります。
また、3ページの真ん中のグラフにありますとおり今後の見込みとしましても、対前年増加率は令和20年度頃まで減少していき、そこでプラスマイナス0%で、一旦のピークアウトを迎えたあと、再び増加していくことが見込まれております。そのため認定者数をグラフにすると、3ページの上のグラフのとおり、令和17年度頃まで増加、そこから横ばいになった後、令和22年度頃から再び増加する推計になっております。
続いて4ページをご覧ください。多機能系サービスのニーズとしましても、先程の認定者数と同様の推計結果となっております。概ね令和17年度頃まで増加し、そこで一旦のピークアウトを迎えます。その後、令和27年度頃から再び増加し始めるという推計結果となっております。なお、一旦のピークアウトを迎える令和17年度時点のニーズとしましては、小多機が14名、看多機が17名、合計で31名となっております。
なお、こちらの資料には書かせていただいておりませんが、小多機と看多機は、運営基準 上、登録定員の上限が29名と定められております。
一方で、独立行政法人福祉医療機構が平成29年度に実施した調査では登録者の登録率別の黒字施設、赤字施設の分布を見ますと、登録率が70%から80%あたり、29名定員で、登録者数21名前後までは、赤字施設の割合が多いという調査結果が出ております。
続きまして、狛江市の周辺の事業所の整備状況について御説明いたします。資料11をご覧ください。資料9の事業所の一覧のところで御説明させていただいたとおり、小多機・看多機ともに、市内に事業所はございませんが、近隣の調布市、世田谷区、川崎市のそれぞれ狛江市に近い場所に複数の事業所がございます。
小多機や看多機のような地域密着型サービスは、基本的に事業所のある所在地の自治体の被保険者のみが利用できますが、事業所のある自治体の同意を得たうえで、狛江市がその事業所を指定することで、例外的に狛江市の被保険者が利用することができます。これを区域外指定と言います。
先程の資料9の2ページと3ページにありますとおり、小多機では2ページの一番下、調布市の仙川にある「ケアハウス絆」、こちらを狛江市の方で区域外指定させていただいております。
また、資料9の3ページの3行目、看多機では、世田谷区の喜多見中学の近くにある「優っくりデイサービス喜多見」を区域外指定しており、それぞれ狛江市の被保険者が利用しております。
最後に、市内の主任ケアマネを対象としたアンケートについて御説明いたします。資料12をご覧ください。狛江市では市内の主任ケアマネ同士の情報交換等を目的として、連絡会を定期的に開催しております。
この中で、主任ケアマネを対象とした小多機の勉強会を令和6年6月19日に開催し、資料12のアンケートを実施しました。このアンケートは主任ケアマネの目線から小多機や看多機の必要性を伺うものでありまして、主な設問を紹介しますと、
Q3と4 狛江市に小多機や看多機の事業所が必要だと思いますか、
Q5 今までに小多機または看多機のサービス利用につなげたことはありますか。
Q6 その人数はそれぞれ何人ですか。
Q8 小多機または看多機の利用が見込める利用者がいますか。
Q9 その人数はそれぞれ何人ですか。
Q10、11 小多機または看多機の利用が見込める利用者は、普段どのようなサービスの組み合わせを利用していますか。
といった質問をさせていただきました。こちらの回答結果を集計したものが資料13になります。資料13をご覧ください。表の一番上にありますとおり、アンケートの回答総数は24件になります。その下の①から④までは、それぞれ資料12の設問における回答の番号を表しています。例えば、表の左側のQ3狛江市に小多機が必要だと思うかという設問について資料12では、①が必要、②がどちらともいえない、③が要らないという回答でございますので、Q3の右のところを見ていただきますと、必要だと回答した方が13名、どちらとも言えないと回答した方が11名、不要だと回答した方はいらっしゃらないということになります。
小多機について、自由記述の欄にありますとおり、肯定的な意見としますと、選択肢が増えて良い、通い・宿泊・訪問を柔軟に使えるサービスが必要、という意見がある一方で、どちらとも言えない、という意見の人は、応募事業者によるという回答が多く見られました。
また、Q4の看多機につきましても同様で、必要だとの回答が14名に増加しており、自由記述として、かなりの困難ケースでも在宅で支えられる、医療の関わりが日常的に必要な人にとってありがたい、という肯定的な意見がある一方で、こちらも応募してきた事業者によるという意見も多く見られました。
続いてQ5、サービス利用につなげたことがあるかという設問に関しては②の小多機のみが10名、③の看多機のみが3名、合計13名がどちらか一方のサービス利用につなげたことがあるという回答でございます。
また、真ん中の表、Q6、具体的な人数を見ますと、真ん中の表のとおり、小多機が16名、看多機が3名となっております。
続いて上の表のQ8ですが、今後利用が見込める利用者がいるかという設問に関しては、①小多機と看多機の両方があるという回答が5名、②の小多機のみがあるという回答が5名、③の看多機のみがあるという回答が1名となっております。具体的な人数としましては、真ん中の表のQ9、二行目のところにございますとおり小多機が23名、看多機が7名、合計で30名の利用が見込まれるという結果になっております。
最後にQ10、小多機の利用見込み者の現在のサービス利用状況については、こちら資料13の一番下の表にありますとおり、③の通所介護のみが3名、⑤の訪問介護と訪問看護の組み合わせが1名、⑥の訪問介護と通所介護の組み合わせが3名、⑩通所介護と短期入所の組み合わせが1名、⑪訪問介護、訪問看護、通所介護の組み合わせが2名、⑫訪問介護、訪問看護、短期入所の組み合わせが1名、そして最後、⑮の四つのサービスの全ての組み合わせが6名となっております。
また、Q11看多機の利用見込み者の現在のサービス利用状況については、③通所介護のみが1名、⑤訪問介護と訪問看護の組み合わせが1名、⑫訪問介護、訪問看護、短期入所の組み合わせが1名、そして⑮四つのサービスの全ての組み合わせが5名となっております。
以上が令和7年度以降の地域密着型サービスの整備の必要性を御議論をいただくにあたりまして、議論の材料となる狛江市の施設整備の状況とニーズの将来推計等の御説明になります。
委員の皆様には、これまでに御説明させていただいた情報を御勘案の上、狛江市における小多機または看多機の新たな事業所の整備の必要性について御議論いただければ幸いでございます。議題8、令和7年度以降の地域密着型サービスの整備の必要性についてに関連する説明は以上となります。
【会長】
御説明ありがとうございました。ということで、今日のメインの議題になるんでしょうか。地域密着型サービスの整備の必要性について、皆様からの御意見を頂戴したいと思います。
【委員】
資料13を拝見して、小多機に移行した人数が意外と多いということに驚いていたところです。
本日の会議に先立って、私の事業所の中で少し小多機・看多機について聞いてみたところ、狛江市に転居されてきた方から1件、狛江市には小多機・看多機は無いのかと苦情のようなものがあって、喜多見の事業所を御紹介したという話がありました。
また、小多機・看多機の必要性について、事業所が狛江にないですし、利用したらケアマネジャーの手を離れてしまいますが、その後の追跡調査もしていないので、よくわからないというケアマネジャーも多いと聞きました。
ただ、必要性自体は感じておりまして、とうきょう福祉ナビゲーションのウェブサイトで調べたところ、小多機については、今日現在で都内で142事業所があって、世田谷が14事業所、調布が1事業所となっております。看多機は都内で55事業所、世田谷区が7事業所、調布に2事業所となっております。ちなみに訪問介護は2,247事業所あって、通所介護は735事業所となっており、小多機は思いのほか都内に多いのだなと感じました。
そちらの介護報酬ですが、定員29名で要介護度を仮に要介護3、食費等は考えないとすると、約9,000万円ぐらいの収入があることを考えると、施設運営の面では、人の配置さえ適正にできれば、運営は可能というところがあります。しかし、問題点としては、狛江市は面積が狭く、人口が少ないので、地域密着型サービスはなかなか事業者の方々が難しいというところがあります。
また、狛江市内で、御利用者の方々が現在のサービスで、何とかケアができている側面もあります。
特別養護老人ホームもかなり入所しやすい状況になってきておりますし、ショートステイも利用しやすくなってきています。
あとは看護の方は医療系の施設だったり、往診医も増えていますので、そちらの方でもやっぱりケアが手厚くなってきているなと感じております。
また、小多機の運営の面でやはり一番大きいのは、夜間は宿直者とケアの一名ということになり、ほぼワンオペになってしまうようなところです。今、介護職員がかなり集めにくい状況になっていまして、東京商工リサーチによれば、1月から10月で、全国平均ですが、145件が今事業所閉鎖をしているとのことです。訪問介護は72件で過去最多だとニュースになっており、どこの事業所も人がなかなか集めにくいということになっております。
加えて、物価高騰で建築コストがかなり上がっておりますので、介護報酬で運営している中で、なかなか事業所の方が手挙げをしにくいというところもあります。
とはいえ、小多機・看多機については、必要性のある地域密着型のサービスでもありますので、サテライト型で運営してる事業者であったり、例えばサ高住とセットでやるような事業所であったり、そういうところに積極的に声をかけていくのがよいのかなと思いました。
【会長】
ありがとうございました。他いかがでしょうか。
【委員】
経営については実際厳しいところもある、と感じております。
ただ、看多機に関しては、正吉苑は狛江市に二つありまして、私がいる二番館はショートステイと長期入所の二事業を運営している中で、短期入所の方で医療ニーズの高い方の申し込みが結構あります。ケアマネジャーさんがそこまで利用者の状態を重く受け止めずに申し込みをいただくようなところがあるのですが、受ける側としては、状態の安定している方が大前提でお受けしているところの中で、実際に入所されて情報が全然足りない、というような状況があります。この人たちは看多機に入所が必要ではないのかというのが、日常会話の中で出るところなので、在宅で医療ニーズが高い人を支えるという意味では、看多機っていうものはあっても良いのかなっていうのは個人的には思いました。
【会長】
ありがとうございます。どちらも必要だけれども、優先度は看多機の方が高いということですね。
【委員】
そうですね。実際にショートステイのところは、お話があった内容と同じです。施設入所のところも、御希望者される方が150~160人待機されているのですが、上位の方々は相当に医療的なケアが必要な方なので、なかなか特養の方に入所ができない方が多くなっています。ですので、Aランク、Bランク、Cランクっていう形で区分けをして特養入所につなげてはいるのですが、Aランクのほとんどの方が重度の医療的なケアを必要とされる方なので、医療的なケアをどうするというのが難しいというのは同じです。
【会長】
訪問介護の充実や医療依存度の高い人の在宅支援というところで何らかのサポートの担保が必要ということであれば、定期巡回・随時対応型訪問介護看護との関係はいかがでしょうか。ショートステイを運営するのはすごく大変で、施設の安定運営ということを踏まえても、狛江市としてトータルで考えたときに、小多機と看多機だけで必要性を議論するのは難しいと感じております。
ちなみに私の知っている事業者で小多機を運営している人に話を聞いたところ、小多機・看多機を利用する場合、ケアマネジャーの手を離れてしまう関係で、小多機・看多機をあまり紹介しないと思うので、調査をするのであれば、地域包括支援センターにした方が、どういう人が必要としていて、今利用ができずに困っているというようなことが、より中立的な意見として把握できるのではないか、というようなことも仰っておりました。
それから、既に御意見出ていますが、宿泊のところをどう担保するかという問題もあります。よくある例でいえば、施設長が夜間対応をして、職員には夜間の負担をできるだけさせずに、対応する例を聞いております。
それから、特別養護老人ホームは要介護3以上が入所の要件となっておりますが、空けておくよりはということで、要介護2、要介護1、要支援の方も入所していただいているケースがあり、そうすると小多機の方を利用する必要が無くなるといいますか、そういう形でニーズが解消されているっていうのが、現状としてはあるというお話でしたので、ニーズについても、全体を見ながら考えていかないといけないと感じました。
いかがでしょうか。事務局から何か聞きたいこと等ありますか。
【事務局】
委員の皆様にいろいろ御議論いただいてる中で、今回この計画上にも小多機・看多機の整備といったところで、市の方としてもここ2年、都度公募していたところではありますが、不調ということで、公募に至らないという経過があります。やはり先程お話もあったとおり、狛江市特有のものかは分からないのですが、土地というか場所が問題というか、ネックになっているのかと考えております。相談はありますが、場所が無いということがありましたので、市としても不動産等を取り扱う団体、全日本不動産協会や宅地建物取引業協会の方に御協力頂きながら周知依頼等もさせていただきました。そのような諸事情といったところと、医療と介護の連携小委員会からも、既存の事業者の連携で現状医療面は担保されているという御意見もあったことから、小多機と看多機の整備に関して、どう進めていくべきなのか検討しているといったところです。
【会長】
必要性は感じているが、事業者は経営が成り立たなければ参入しないし、狛江は家賃も高い。24時間動いている施設に併設する形で事業者が参入してくれるといいのだけど、という意見もありました。いかがでしょうか。
【委員】
今回の資料の中で、推計値を出していただいた資料10のところで、ある程度多機能型のニーズが出たというところと、資料13のところで、主任ケアマネジャーということで、ある程度知識や経験がある方を対象としたアンケートになりますが、その中でもある程度利用見込者数が出たということは、小多機・看多機共にある程度ニーズがあることは再確認できたと思います。
ただ、資料11の地図を見ると、明らかに狛江だけ空洞になっています。川崎市多摩区や川崎市麻生区は、同じ名前の事業者が多数あることからもわかるとおり、明らかに面展開されていて、多摩川を境界に、明らかに途切れてしまっています。ただ、これは地理的な要因から変えられないことなので、企業から見ると、どうしても難しい面があります。また、調布市も決して多いわけではないので、少ない中でなんとかしている状況です。
家賃の話も出ましたが、世田谷区は大きいので、また違うかもしれませんが、世田谷区で運営ができているのであれば、狛江市で考えた時に、家賃の部分はそれほど問題ではないのかなと思います。
【会長】
いかがでしょうか。狛江市周辺の小多機・看多機の事業所は定員に対して7割以上の利用が恒常的でないと赤字というところでは、今現在、狛江市の利用者が近隣の事業所に貢献をしているとも考えられます。今回の議題として挙げられた経緯として、狛江市周辺の小多機・看多機が定員超過している等の事情もあるのでしょうか。
事務局にお聞きしますが、本日はどのあたりまでの意見を求めていくのでしょうか。
【事務局】
本日の議題としましては、まずは小多機または看多機の公募を実施するかどうかというところについて、皆様の御意見を頂ければと考えております。そして、来年3月に介護保険推進市民協議会を開催させていただければと考えておりまして、その際には、仮に今回公募するというお話となれば、公募の具体的な内容についてお諮りさせていただければ、と考えております。
【会長】
決を採るというようなことになるのでしょうか。それとも、公募をする方向でよろしいか、という話でよろしいのでしょうか。
【事務局】
本日御説明した内容もかなりボリュームがありますので、本日だけでなく一週間程度、概ね令和6年11月22日までの間で、御意見があれば事務局の方まで募集させていただいて、そちらの肯定的な意見、否定的な意見を踏まえて、事務局と会長で調整をさせていただいて、来年3月の協議会で御報告させていただければと思います。
【会長】
ということですので、お考えのある方は個別に事務局に御意見をお送りください。
【委員】
「医療と介護の連携」とよく言いますが、狛江市内の慈恵医大第三病院が今改装中で、2026年1月から再開をされるそうです。重点的なエリアは狛江市・調布市・世田谷区ということで、その中で力を入れていることは、在宅医療と認知症です。実は、狛江団地の中でも、常にこういう講演会は開催していただいていて、また、狛江団地は20年5期の計画で入れ替わることにもなっています。東京都の物件ですので、狛江市でできることも限られるかもしれませんが、そこの土地を活用して、慈恵医大第三病院に協力してもらって事業を行うという案もあるかと思います。実際には、主導権や経営権をどうするかというと難しいでしょうけど、ただ、公募についても「諦める必要はないと思います」ということを言いたいと思います。
【会長】
是非公募を継続して欲しいという御意見でした。小多機、看多機の必要性は確認されたということで、改めまして御意見のある方は令和6年11月22日の金曜日までに事務局まで御意見をお送りください。事務局と調整のうえ、本協議会の最終的な意見として確定させていきたいと思います。
それではその他、ということで事務局から何かありますでしょうか。
【事務局】
資料14として、前回の議事録案をお配りさせていただいております。お忙しいところ恐縮ですが、内容を御確認いただきまして、修正点等がありましたら、令和6年11月22日金曜日までに事務局まで御連絡ください。
また、本日お配りした資料の最後に、狛江市介護保険推進協議会委員名簿登録用紙をお配りさせていただいております。今回以降、協議会の細かな御連絡については、メールにて御連絡させていただく可能性がございます。お手元の登録用紙にお名前と連絡先のメールアドレスを御記入の上、お帰りの際には、机上に置いていただくか、出入口に箱を用意しておりますので、そちらに御提出いただきますようよろしくお願いいたします。
最後に、次回の開催予定は令和7年3月頃を予定しております。詳細につきましては、決まり次第、委員の皆様に開催通知を御送付させていただきます。事務局からは以上となります。
【会長】
ただいまの内容につきまして、何か御質問ある方いらっしゃいますでしょうか。それでは本日の議題は以上になります。次回は来年3月ということでよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
|
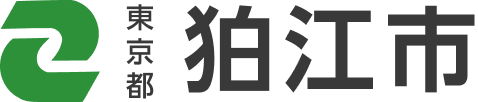
 印刷
印刷
 戻る
戻る
 ページの先頭
ページの先頭