|
【事務局】
それでは定刻になりましたので、狛江市介護保険推進市民協議会を始めさせていただきます。
本協議会の委員総数は13名となっており、本日、13名の委員が御出席されており、狛江市介護保険条例第25条第2項に規定する「委員の過半数の出席」という会議開催の要件を満たしておりますので、本協議会は有効に成立しております。
それでは、本日の配付資料の確認をさせていただきます。
本日の配布資料は、
- 令和6年度第2回介護保険推進市民協議会 アジェンダ
- 資料1 会議録確認の時期・方法等について
- 資料2 狛江市第1次地域共生社会推進基本計画 実施計画における評価方法について
- 資料3 令和7年度以降の地域密着型サービスの整備の必要性についてのご意見一覧
- 資料4 令和6年12月23日介護保険部会資料「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会(案)
- 資料5 令和7年度の公募要項案と審査表案の主な変更点について
- 資料6 令和7年度地域密着型サービス事業者選定スケジュール(案)
- 資料7 令和7年度狛江市地域密着型サービス事業者公募要項(案)
- 資料8 令和7年度狛江市地域密着型サービス事業者審査表(案)
- 資料9 第9期介護保険事業計画 令和6年度実績値の進捗(平成7年2月末実績)
- 資料10 令和6年度第1回介護保険推進市民協議会議事録(案)
- 参考資料1 狛江市における多機能系サービスのニーズの将来見込みについて
- 参考資料2 令和6年度第2回主任ケアマネ連絡会 アンケート結果について
以上になります。不足等がございましたら事務局までお申しつけください。
それでは、この後の議事の進行を、中村会長よりお願いいたします。
【会長】
それでは、今年度最後の協議会になります。
前回は、第9期介護保険事業計画の概要について、委員の皆様と認識を共有した上で、令和7年度以降の地域密着型サービスの整備の必要性について御意見をいただきました。
今回の会議では、いただいた御意見をもとに、令和7年度以降の地域密着型サービスの公募の内容について、主に議論をしていきたいと思います。
それでは、アジェンダに沿って議事を進めてさせていただきます。
議題内容・進行予定の「1 会議録確認の時期・方法等について」、事務局から説明をお願いします。
【事務局】
それでは、議題1、「会議録確認の時期・方法等について」、事務局から資料1を用いて御説明させていただきます。資料1を御覧ください。
会議録の確認の時期と方法につきまして、現行の流れは上の図のとおりです。協議会終了後に会議録を作成し、次回の協議会で委員の皆様に内容を御確認いただいた上で、公表する流れになっております。内容の確認に2週間程度の期間を設定しておりますが、次回の協議会を開催するまで会議録の公表ができず、長いと公表まで半年以上の期間がかかることがあります。
狛江市附属機関等の設置及び運営に関する規則第15条第2項において、会議録の公表は、原則として審議会等終了後4週間以内に市ホームページに掲載することにより行うものとする、とされています。そのため、現行の会議録の公表までの流れを見直し、2の変更案のとおりにさせていただきたいと考えております。具体的には、協議会開催後、2週間程度で会議録を作成いたします。その後、電子メールにて、委員の皆様に会議録の確認依頼をさせていただきます。そちらを1週間程度の期間で御確認いただき、その後1週間程度でホームページに公表するという流れになります。
委員の皆様には、協議会の開催日以外に追加で会議録の確認依頼をさせていただくこととなり、大変御手数をおかけいたしますが、御理解と御協力のほど、よろしくお願いいたします。
会議録確認の時期・方法等についての説明は、以上となります。
【会長】
ただいま、事務局から、会議録確認の時期・方法等についての説明がありました。
何か御意見・御質問は、ありますでしょうか。
それでは次の議題に移ります。議題2、「狛江市第1次地域共生社会推進基本計画 実施計画における評価方法(案)」について、事務局から説明をお願いします。
【事務局】
それでは、議題2、狛江市第1次地域共生社会推進基本計画実施計画における評価方法(案)について、福祉政策課の小嶋より御説明させていただきます。資料2を御覧ください。
前回御説明させていただいた内容ですが、変更となった部分、また、実際にどのような施策、重点取組、事業内容になるかという点を本日、御説明させていただきます。
現行の地域共生社会推進基本計画において、当計画をPDCAサイクルを回して評価・事業実施を行い、その評価を施策に生かしていくという形になっております。そのサイクルの中で、計画において、市民推進委員会と3つの小委員会で、事業の進捗の評価の評価を行うという形で掲載をしております。計画を策定するに当たり、介護保険推進市民協議会の委員の皆さまにも御審議いただいたものとなっていますが、介護保険事業計画の評価の評価を介護保険推進市民協議会ではなく、高齢小委員会において、評価の評価を行うとなっておりますため、その実施が困難であるという状況がありました。その状況を踏まえ、今回、事務局の方で整理した内容をまず御説明させていただきます。
先ほど申し上げたとおり、現行は、市民推進委員会と高齢小委員会を始めとした3つの小委員会において、事業の進捗の評価の評価を行うこととなっています。このうち、高齢小委員会においては、高齢者福祉の推進に関する事項の評価の評価を行うことになっていますが、当該委員会は、高齢者保健福祉計画を担当する小委員会となっており、介護保険事業計画についてまで、評価の評価を行うことが難しいものとなります。そのため、今回、高齢小委員会の方で、来年度の第1回委員会で審議をさせていただく予定ですが、関係人の意見聴取が狛江市福祉基本条例施行規則第25条第3項に規定されていますので、当該規定に基づき、介護保険推進市民協議会の会長をお呼びしたいと考えております。そして、審議の結果、高齢小委員会において会長をお呼びすることが決定した際は、会長に高齢小委員会に御出席いただき、介護保険事業計画に関する点について、御意見を頂きたいと投げかけさせていただきます。その後、会長が介護保険推進市民協議会にお持ち帰りいただき、委員の皆様に評価の評価をしていただいた上で、その結果を高齢小委員会に回答いただくというような形で介護保険推進市民協議会の皆様の評価の評価を踏まえた、高齢小委員会の評価の評価を行いたいと考えております。
実際に、どのような評価の評価を行うかについても御説明させていただきます。資料の2ページを御覧ください。(1)‐1となりますが、実施計画を昨年9月に策定し、今年度この事業を進めていく中で、(2)‐1の進捗管理というものを各課において作成するように福祉政策課から依頼しているところとなります。今回、評価の評価を頂くに当たり、具体的な内容を皆様に分かっていただけるよう説明することに取り組んでおり、この点、(2)‐1進捗管理の『「評価」の理由』という欄を御覧いただきたいのですが、例えばこちらに記載の事業取組み内容では、令和6年度に「15事業者以上」という定量的な指標を目標値としており、こういったものにつきましては、定量的な評価に加え、二段目の中盤以降に、定性的という表現をしていますが、実際に定量的にどう評価がされるのか、また、定性的にどう評価がされるのか、という点を記載する形で、より具体的にわかりやすく、評価を主管課で行うことを考えております。また、上手くいっている事業、上手くいっていない事業ともに、「課題等」や「令和7年度以降の取組や方針」というものを記載するという形で考えております。
こちらの2ページ目につきましては、定量的な評価のものになりますが、例えば、9ページ目を御覧ください。こちらは介護保険事業計画の内容に該当する部分となりますが、例えば(2)‐1の4‐8‐1、「地域密着型サービスの整備を推進します」という施策では、「小規模多機能型居宅介護または看護小規模多機能型居宅介護の整備の検討」という重点取組につきまして、事業(取組)内容としまして、「将来ニーズ動向を踏まえた施設整備の必要性を検討」いうことで目標(値)を「検討」としております。このような定量的な評価ができないものにつきましては、定性的な評価というものを記載をしていくということを考えております。
次に、4ページ目にお戻りください。主管課で評価をしたものについて、地域共生社会推進会議という会議体、こちらの会議体は庁内、社会福祉協議会及び地域包括支援センター3箇所に御出席いただくものですが、その中で評価を行います。そして、評価をしたものについて、5ページ目になりますが、市民福祉推進委員会等で作成します評価の評価を頂きます。この中で、先ほど申し上げましたとおり、介護保険事業計画の内容については、高齢小委員会から御依頼をさせていただき、評価の評価を頂きたいと考えております。
実際にどのような施策と事業取組内容があるかは、9ページ以降となります。全部を紹介すると時間が足りなくなってしまうのですが、全部で21個、事業取組内容に該当するものがあります。こちらについて、令和7年5月下旬以降に、開催を予定している、令和7年度第1回介護保険推進市民協議会の方に、目標値に対してどのような取り組みをしたのかまた、そちらを評価をしたものについて、評価の評価を頂きたいと考えております。
狛江市第1次地域共生社会推進基本計画実施計画における評価方法(案)についての説明は、以上となります。
【会長】
ただいま、事務局から、狛江市第1次地域共生社会推進基本計画実施計画における評価方法(案)についての説明がありました。
介護保険事業計画と高齢者保健福祉計画と一体に策定するが、中身は別であり、高齢者保健福祉計画の方は高齢小委員会の方で評価をし、介護保険事業計画の方はこの市民協議会で評価をする形に別れているため、市民福祉推進委員会がどのように統合的に評価をしていただくか、色々と考えていたものの、中々案が出せず、悩まれていたということで、今、説明を聞いた方も混乱している方がいらっしゃるのではないかと思いますが、何か御意見・御質問ある方はいらっしゃいますか。
いったんこの内容で試していただき、正解はわかりませんが、実際に運用しながら、きちんと評価ができる、できないを推進委員会の委員長の御意見も踏まえながら、見極めるということで、原案のまま進めていただいてよろしいでしょうか。
それでは、次の議題に移ります。本日のメインのテーマですが、議題3、令和7年度以降の地域密着型サービスの整備の必要性について、事務局から説明をお願いします。
【事務局】
それでは、議題3、令和7年度以降の地域密着型サービスの整備の必要性について御説明いたします。こちらは、前回の協議会で、将来のニーズや近隣の施設整備の状況等を踏まえまして、狛江市における施設整備の必要性について御議論いただいた件につきまして、今回、委員の皆様からいただいた御意見を御紹介した上で、会長と御調整させていただいた結論を事務局から御説明させていただくものです。資料3を御覧ください。
御意見の1つ目、小多機・看多機ともに必要性は認識しているが、①近隣と比べて人口が少ない、②既存のサービスも手厚くなっている、③人材確保が難しい、④物価高騰で建築コストが上がっている、等の理由で確保が難しい。サテライト等で広く事業展開している事業者に声をかけていく等をしてはどうか。
御意見の3つ目、特養待機者で優先順位が上位の方々は、相当に医療的ケアが必要な方が多く、施設入所時の医療的ケアをどうするかが難しい。医療的なケアが必要な方のためのサービスとして、看多機が必要だと思う。
御意見の4つ目、看多機のうちショートステイは確保するのが難しい側面がある。また、特養が軽度者を受け入れるようになって多機能系のニーズが解消している可能性もあり、小多機・看多機単体で考えるのではなく、全体との関連を踏まえて捉えることが必要だと思う。
御意見の7つ目、小多機は現行サービスの組み合わせで対応できるが、医療系の看多機に代わるものはないため、看多機を積極的に誘致していただきたい。しかしながら、何度も公募しても手挙げがないのであれば、どこかで一度立ち止まり、数年後の公募でも良いと思う。
御意見の8つ目、調布市の事業所はベースとなるセンターが自治体内にあり、そこから発展しているケースが多く、世田谷区の事業所は世田谷区内で面展開をしているため、近隣から応募してくる可能性は低い。また、市内の事業所から手が挙がらない状況では、市内からのエントリーも難しいため、市が公募したとして、事業者が応募してくる可能性は低い。こういった状況を踏まえて、最終的に公募を実施するかどうかは委員長と事務局の判断にお任せする。
これらの御意見を踏まえまして、会長と調整させていただいた結論を御紹介いたします。
まず、別紙にありますとおり、医療的ケアが必要だが通所や宿泊が不要な方向けの定期巡回・随時対応型訪問介護看護、医療的ケアが不要だが3サービスを組み合わせ、施設入所手前の重度な方が在宅で生活するためのサービスとして小多機、さらに医療的ケアが必要な方向けのサービスとして看多機があります。これらの対応関係としましては、定期巡回や小多機のニーズに対し、看多機で対応することは可能となっております。
小多機の将来のニーズとして、参考資料1の推計結果では、15名前後、参考資料2の主任ケアマネを対象としたアンケート結果では、20名強となっております。いずれも一定程度のニーズがあることは示されているものの、前回の協議会で御報告させていただいたとおり、登録定員の7割以上、概ね21名以上の登録者数が無いと赤字になる可能性が高いという調査結果も出ている状況では、小多機単体で事業を実施することは難しいと考えられます。
看多機を含めたニーズでは、参考資料1では31名、参考資料2では30名となっており、ある程度まとまったニーズが見込まれます。このことから、令和7年度以降において、看多機を1事業所公募することといたします。
なお、複数の御意見にありますとおり、公募により参入事業者を確保することが難しいという側面もありますので、その点については事前に皆様の共通理解として御認識いただけると幸いです。
また、資料4にありますとおり、第10期計画の策定に向けて、国の方で「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会(案)の設置に向けた動きがあり、「今後のスケジュール(案)」では、2025年度に検討結果が報告される流れが示されております。こちらにつきましても、新たな動きがありましたら、あらためてサービス提供体制について御議論いただく場合がございますので、あらかじめ御承知おきください。
令和7年度以降の地域密着型サービスの整備の必要性についての説明は、以上となります。
【会長】
ただいま事務局から、令和7年度以降の地域密着型サービスの整備の必要性についての説明がありました。小多機、看多機どちらも必要ですが、医療的ケアが必要な在宅者に対してのサポートがまだまだ薄く、また、ニーズの見込みも現実的には看多機の方が高いのではないかということで、令和7年度以降、看多機を1事業所公募するという原案となっております。何か御意見・御質問は、ありますでしょうか。前回、たくさんの御意見をいただいておりますので、この内容で実施するということでよろしいでしょうか。
それでは、次の議題に移ります。
議題の4、令和7年度の地域密着型サービス事業者の公募について、こちらは先ほど御説明のあった公募について、具体的な案をお示しするものです。
それでは、事務局から説明をお願いします。
【事務局】
それでは、議題の4、令和7年度の地域密着型サービス事業者の公募について、資料5から資料8までを用いて、事務局から御説明させていただきます。
まず、令和7年度の地域密着型サービス事業者の選定スケジュール案について御説明いたします。資料5を御覧ください。
令和7年度の介護保険推進市民協議会の公募関連以外の開催予定時期と議題につきましては、資料5の一番右に記載してございます。
令和7年度は、先の議題2で説明させていただきましたとおり、狛江市第1次地域共生社会推進基本計画の実施計画における評価の評価を実施していただく必要がございますので、5月中旬・下旬頃に第1回の開催を予定しております。
また、令和7年度は第9期介護保険事業計画の改定年の前年に当たりますので、第10期計画の策定に向けて、市民意識調査を実施いたします。こちらの御議論につきましては、例年8・9月頃に示される、厚生労働省のガイドラインを待ってから開始することになりますが、現在のところ10月・11月の2回で御議論いただくことを予定しております。
その後、令和8年3月下旬頃に、令和7年度の給付実績の評価と、令和7年度の公募が不調に終わった場合、次年度の公募についての御議論を予定しております。
令和7年度の当協議会の、公募以外の予定は以上となります。こちらを踏まえまして、令和7年度の公募のスケジュール案を作成させていただきました。令和7年度は2回の公募を予定しております。
まず、令和7年5月1日から8月29日までに第1回の公募を実施いたします。こちらで応募がありましたら、9月下旬頃にプレゼンテーションを実施しまして、事業者を選定していただくことになります。その際は、委員の皆様に通知させていただきますが、短期間での開催となることが予想されますので、あらかじめ御承知置きください。その後、庁議を経て、10月下旬に事業者を決定するという流れになります。
第1回の公募で不調に終わった場合、第2回の公募を11月4日から翌令和8年2月27日までに実施いたします。こちらに応募がありましたら、令和8年3月下旬頃に予定している協議会におきまして、プレゼンテーションを実施していただくことを予定しております。
令和7年度の地域密着型サービス事業者の公募のスケジュール案は以上となります。
続きまして、令和7年度の地域密着型サービス事業者の公募要項案と審査表案について御説明いたします。資料6を御覧ください。
資料6は、令和7年度の公募要項案と審査表案について、前回の公募要項との変更点を対比したものになります。また、資料7として令和7年度の公募要項案、資料8として令和7年度の審査表案を配布させていただいておりますので、あわせて御確認いただければと思います。
令和7年度は、先の議題3で説明させていただいたとおり、看多機1事業所の公募といたします。あわせて、公募の時期とその後のスケジュールとしましても、先のスケジュール案のとおり変更しております。
続きまして、資料6の変更番号2番、資料7は3ページになります。
応募要件の(5)、審査の際に考慮する指導検査の対象期間について明確化を図りました。また、資料6の2ページにありますとおり、公募要項5の「応募要件」という項目と、6の「応募条件」という項目の内容が近いため、項目を統合しております。
続きまして、資料6の3ページ、資料7の4ページ、補助金に関する記述につきまして、こちらは、対象事業を看多機のみに修正するとともに、文言を整理させていただきました。
続きまして、資料6の4ページを御覧ください。
変更点5番から7番につきましては、それぞれ細かな部分について明確化を図っております。
最後に、審査表案につきましては、変更点の8番にありますとおり、「看取りやターミナルケアに対応しているか」という視点を追加しております。
以上が、令和7年度の変更点になります。今回、新しい委員さんもおられますので、これを踏まえまして、あらためて令和7年度の公募要項の案の概略を御説明いたします。資料7を御覧ください。
資料7の1ページ目と2ページ目は、既に御説明させていただいたとおりです。看多機事業所を1事業所、年2回の公募を予定しております。
3ページを御覧ください。3ページに応募要件を掲載しております。主な要件としましては、(4)第三者評価等において総合的に高い評価を得ていること、(5)過去5年間の指導検査等において、その結果が良好であること、(6)事業の整備及び運営に充分な資力を有していること、(7)施設を整備する土地や建物が確保されていること、等があります。
続きまして、4ページと5ページは、東京都の補助金に関する記述となります。6の1行目にありますとおり、東京都では、「地域密着型サービス等整備推進事業補助金」と「東京都介護施設等の施設開設準備経費等支援事業補助金」の2種類がありまして、いずれも市を通じて補助する形をとっております。この公募で選定された事業者は、これらの補助金を活用して施設整備を進めていくことになるかと思いますが、基本的に東京都の補助金のルールに従いまして、市の補助金担当の方から御案内させていただく予定でおります。
続きまして、6ページは応募の必要書類、7ページは申込方法を掲載しております。応募される事業者は、6ページにある必要書類を揃えて御提出いただき、事業計画書を応募の際に14部、プレゼンテーションの実施予定日までに応募書類の写しを14部御用意いただくことになります。
続きまして、8ページが応募に当たっての留意事項となります。主な項目としましては、(1)と(2)、市の計画やまちづくり条例と整合を図ること、(3)利用者の費用負担は出来る限り抑えること、(4)利用は原則として狛江市民に限定すること、(5)事業所開設に当たっては、周辺住民に十分な説明を行い、要望や苦情等に対して誠実に対応するよう努めること、等でございます。
続きまして、9ページは事業者の選定についての記述になります。応募事業者の選考は、事業者から提出された書類の審査とプレゼンテーションにより実施します。公募期間に応募がありましたら、委員の皆様にプレゼンテーションの開催を通知させていただきますので、お忙しい中恐縮ではありますが、御足労いただき、事業者から提出された応募書類と、事業者のプレゼンテーションを元に、資料8にあります審査表を用いて選考していただくことになります。なお、提出された応募書類につきましては、プレゼンテーション終了後に事業者に返却いたします。また、選考結果につきましては、応募事業者に通知するとともに、ホームページにも掲載をいたします。
10ページには、その他留意事項としまして、選定後の辞退を原則として認めない点や、応募内容に虚偽があった場合等について記述しております。
続きまして、最後に、令和7年度の審査表の案の概略を御説明いたします。資料8を御覧ください。
こちらの審査表は、プレゼンテーションの際に、委員の皆様が応募事業者を評価していただくために用いるものになります。審査表は、各評価項目について、A・B・C・Dの4段階で評価していただき、合計点を算出するという設計になっております。評価項目の大きな分類としましては、表の一番左に掲載しておりますとおり、1法人運営、2事業所運営、1枚目裏面の3利用者サービス、4地域との連携、5事業所の設計、の5つの観点から評価いたします。最後に、総合評価としまして、2枚目の6(1)運営法人について、(2)事業所運営とインフラについて、(3)サービス・その他について、の3つの観点から総合評価をしていただきます。個別の審査項目は、各項目3点、合計105点となっております。また、総合評価につきましては、各項目15点、合計45点となっており、両方を合計して150点の配点を設定しております。プレゼンテーション当日は、応募事業者の発表が終わりましたら、この審査表を用いて採点していただき、事務局で集計させていただきます。委員の皆様には、その点数をもとに、事業者を選定していただきたいと考えております。
審査表案の1枚目表面に戻っていただきまして、各評価項目につきましては、それに対応する形で、評価基準を記載しております。実際に採点する際は、主に評価基準に書かれた観点から、各評価項目を評価していただきます。また、表の一番右の欄には、それぞれの評価基準について、どの様式にそのことが書かれているかを記載しております。こちらを上から順に御覧いただきますと、大半の評価基準の根拠資料が「(10)事業計画書」になっております。
応募の際に事業計画書を14部御提出いただくことになっておりますので、プレゼンテーションに先立ちまして、委員の皆様には事業計画書と審査表を事前に送付いたします。お忙しい中恐縮ですが、事前に事業計画書を御確認いただいた上で、プレゼンテーション当日は、忘れずに御持参くださいますよう、よろしくお願いいたします。なお、審査表の各評価項目の番号と、事業計画書の各設問の番号は、同じになるように設計しております。
最後に、それぞれの評価項目につきまして、順に御説明いたします。
まず、1の法人運営につきましては、法人の理念や、法人の組織運営、看多機等の運営実績や、法人の財務状況といった側面から、御評価をいただきたいと考えております。
次に、2の事業所運営につきましては、事業所を実際に開設した際の、財務状況や人員体制、各種運営体制等について、御評価いただきたいと考えております。
裏面に行っていただきまして、3の利用者サービスにつきましては、利用者の意向の把握や利用料等について、4の地域との連携につきましては、開設に向けた近隣住民への説明や、他の機関との連携を図るための工夫等について、5の事業所の設計につきましては、近隣環境への配慮やバリアフリー対応、災害時等の備え等、といった観点から、それぞれ御評価いただきたいと考えております。
最後に、総合評価としまして、先ほどの大きな5項目の評価項目に対応する形で、それぞれ総合評価をいただき、最終的に事業者としての評価を固めていただく形になっております。
令和7年度の審査表案の説明は以上です。
今回、お示ししたスケジュール案、公募要項案、審査表案について、委員の皆様に御議論いただき、本日の会議で令和7年度の公募の具体的な内容を確定させていただきたいと考えております。
令和7年度の地域密着型サービス事業者の公募についての説明は、以上となります。
【会長】
ただいま、令和7年度の地域密着型サービス事業者の公募について、事務局から説明がありました。
最初にこのスケジュール案について、二段構えで日程を組むということですが、何か御意見・御質問はありますでしょうか。
私の方からよろしいでしょうか。こちらの公募はどのように行うのでしょうか。どこにどう周知をするかなど、基本的な方法があると思いますが、いかがでしょうか。
【事務局】
公募に際しましては、広報こまえに掲載させていただくのと併せて市のホームページの方にも、看多機を1事業所、公募期間はいつからいつまでですと公表させていただく予定です。
【会長】
中々応募者が見つからない中、アンテナを立てて向こうが食いついてくることを待つという方法と、斜め向こうを見ている方々にこちらに振り向いてもらうという方法とがあると思いますが、例えば、大きな法人に周知文を撒くなど、そういった方法はないのでしょうか。
【事務局】
前回公募をした際に、宅地建物取引協会や日本不動産協会に公募の周知を依頼したという経過があるため、今回もそのような土地、物件を探すプロの方々に御依頼するという方法は検討の余地があると考えております。
また、近隣の看多機事業所を経営されている事業者さんに対しても、公募の通知を送らせていただくことを検討しております。
【会長】
やはりできる限り公募について知っていただき、市内じゃない事業所の人でも狛江でやってみようかと振り向いてもらえるくらい、広く周知いただければと思います。
【委員】
前回の看多機、小多機の公募はいつ行ったのでしょうか。
【事務局】
公募自体は令和5年度に実施しております。
【委員】
そこから公募の仕方がおそらく変わっていないと思うのですが、市の熱量としては、ぜひやってもらいたいというものなのか、なければないでしようがないというものなのか、どのような立ち位置なのでしょうか。例えば市の方から、このような土地があり、この程度のニーズがあるため、採算が取れそうであるというような情報を出すことはあるのでしょうか。
【事務局】
市の方で土地などを紹介するというところまでは現在、検討しておりません。
【会長】
他によろしいでしょうか。では、スケジュールについては、広報の部分をより広く積極的にということを要望したいと思います。
それでは続いて公募要項案と主な変更点について、資料6と資料7併せてになりますが、何か御意見・御質問はありますでしょうか。
それではこちらも私からよろしいでしょうか。要項案の8ページに、「利用者は原則として狛江市民のみとすること」とあります。一方で狛江市は、世田谷区の事業者を利用していたりすると思います。原則ということではありますが、こちらの記載は、応募者を狭めたりはしないのでしょうか。何か表現の工夫があってもよいかと思いますがいかがでしょうか。
【事務局】
制度上、地域密着型サービスとなりますので、狛江市の事業者を利用できるのは狛江市民というのが原則ではありますが、おっしゃるとおり市外利用もありますので、表現をどうするかというところは検討の余地があるかと思います。
【会長】
要項案の3ページの(4)において、「外部評価の結果において、継続して総合的に高い評価を受けており」といった記載もありますが、こちらの記載も一定の実績がある事業者でないと受け付けないと捉えられたりしないでしょうか。全体的に要件が厳しめに感じる部分は事務局に御相談くださいというような一文があるとよいのではないでしょうか。今回出来る限り応募してもらいたいという思いからするとこのような細かいところで応募者を狭めないように気を付けた方がよいと思います。
【事務局】
具体的な記載の変更は今のところ事務局では考えておりませんでしたが、今回このような御意見があったということで、表現の仕方について、検討したいと思います。
【会長】
他によろしいでしょうか。
それでは続いて、資料8の審査表についてです。応募があった場合は、こちらで審査いただくことになりますが、御意見、御質問はないでしょうか。
またしても私の方からよろしいでしょうか。「1法人運営」の「(3)実績」について、「本事業の運営実績があるか」の部分で、ない場合は「経験のある事業者等との連携及び支援があるか、経験のある従業員の採用があるか」とあります。こちらは公募要項の方には書かれていませんでしたが、記載しなくてもよいのでしょうか。隠れた評価項目になっていて、公募要項の方に記載がないとわかりにくいかもしれないと思ったのですがいかがでしょうか。
【事務局】
公募要項の要件においては、特に運営実績があることまでは求めないものとなります。
【会長】
先ほど少し御質問した、第三者評価についての記載止まりで、実績があるかどうかはそこで把握するという形で、直接は聞いていないのでしょうか。
【事務局】
公募要項については、あくまで応募できる条件となりますので、運営実績のない事業者でも応募できるという形にさせていただいております。審査表案の方は事業所を評価する際の加点方式となりますので、運営実績のある事業者の方がより高い点数になるように設計させていただいております。
【会長】
他によろしいでしょうか。複数の応募が来た際に対応できるか不安はありますが、恐らく事務局の方で色々な裏を取ったり、調べてくださったりしていただけるかと思いますので、その際はよろしくお願いいたします。
それでは、本日いただいた御意見をもとに、事務局等と調整の上、本協議会の最終的な意見として、確定させていきたいと思います
それでは、次の議題に移ります。
議題の5、第9期介護保険事業計画の令和6年度実績値の進捗状況について、事務局から説明をお願いします。
【事務局】
それでは、議題の5、第9期介護保険事業計画の令和6年度実績値の進捗状況について、事務局から御説明させていただきます。資料9を御覧ください。
資料9は、令和6年度の給付費の実績について、第9期介護保険事業計画の計画値と比較したものになります。2月末までの実績になりますので、実績値は11か月分のデータとなるため、計画値、実績値共に1月単位の額で記載しております。
また、実績値が計画値から15%以上離れているサービスについて、「実績値/計画値」のセルを色付きにしてあります。また、そのうち、例年実績と比べても大きな乖離が見られるものについては、その右の特記事項のセルも色付きにしてあります。
この議題5では、計画値からの乖離が見られるサービスについて、順に御説明させていただきますので、委員の皆様には、この資料の下にある「計画値からの乖離が見られる要因」や「サービス提供体制に関する現状と課題」について、御意見を賜れればと考えております。
それでは、計画値からの乖離が見られるサービスの1点目、訪問リハビリでございます。
こちらは、第8期の計画期間中の実績が計画値を下回っていたことから、第9期計画で下方修正されたものでございます。給付実績については、例年と比べて大きな増加が見られますが、過去5年間の推移を見ると、令和3年度から令和5年度までに給付費の落ち込みが見られ、令和6年度は令和2年度と同水準に戻っていることがわかっております。
続きまして、計画値からの乖離が見られるサービスの2点目と3点目、短期入所生活介護と短期入所療養介護でございます。こちらは、いずれも第8期の計画期間中の実績が計画値を上回っていたことから、第9期計画において上方修正されたものになります。実績値ベースでは、短期入所生活介護の方は前年度比96.60%、短期入所療養介護の方も前年度比92.55%と、いずれも大きな乖離は見られておりません。
続きまして、計画値からの乖離が見られるサービスの4点目、定期巡回・随時対応型訪問介護看護でございます。また、6点目の小規模多機能型居宅介護も同様ですので、あわせて御説明いたします。定期巡回、小多機共に、第8期の計画期間中の実績値が計画値を下回っていたことから、第9期計画で下方修正されたものになります。実績値ベースでは、定期巡回は前年度比87.88%、小多機は前年度比60.32%と大きく落ち込んでいますが、いずれも元々の利用者数が少ないために増減幅が大きく出ているものと考えられます。
続きまして、計画値からの乖離が見られるサービスの5点目、地域密着型通所介護でございます。こちらにつきましては、第8期の計画期間中の実績が計画値を上回っていたことから、第9期計画で上方修正されたものになります。実績値ベースでは、前年度比95.97%となり、大きな乖離は見られておりません。
計画値からの乖離が見られるサービスの最後、介護医療院でございます。
こちらにつきましては、第8期の計画期間中の実績が計画値を下回っていたことから、第9期計画で下方修正されたものになります。実績値ベースでは、前年度比113.80%ですが、令和5年度末に介護療養型医療施設から介護医療院へ制度移行があり、一人当たりの平均給付費等に変化が見られておりますので、利用者数ベースでは増加幅は8%前後に留まり、大きな乖離は見られておりません。
以上が、令和6年度実績値の進捗状況になります。今回、お示しさせていただいた計画値と実績値の対比をもとに、計画値からの乖離が見られるサービスを中心に、その要因として考えられるものについて御意見いただいた上で、必要に応じて、今後のサービス提供体制の見直しにつなげていければと考えております。
第9期介護保険事業計画の令和6年度実績値の進捗状況についての説明は、以上となります。
【会長】
ただいま、第9期介護保険事業計画の令和6年度実績値の進捗状況について、事務局から説明がありました。
何か御意見・御質問はありますでしょうか。
また私の方からよろしいでしょうか。実績値についてですが、こちらは人数ではなく金額だけなのでしょうか。人数で報告したことはあるでしょうか。
【事務局】
例年、金額ベースで報告させていただいております。
【会長】
金額ベースもよいのですが、充実しているのか、需要が伸びているのか、わかりにくいため、人数ベースでの資料も欲しいと思うのですが、皆さんいかがでしょうか。
なお、金額ベースだと大きな乖離が見られますが、利用者数が激増している又は激減しているということではなく、それなりにほぼ同じような利用者数となっているのでしょうか。
【事務局】
費用請求がベースになっているため、実際の利用者数というところを正確に把握することが難しいところではありますが、概ね給付費に変化が生じてるところは、利用者についても同様の動きをしてるものと思います。
【会長】
こちらは人数ベースで示せるか御検討いただいてもよろしいでしょうか。無理であればしようがないですが、他の市町村では実人数、延べ人数などでで示されていたものがあったと記憶しています。
それでは、他に御意見がある方は、令和7年4月4日(金)までに、事務局までお願いします。いただいた御意見をもとに、事務局等と調整の上、本協議会の最終的な意見として、確定させていきたいと思います。
それではその他、ということで事務局から何かありますでしょうか。
【事務局】
資料10として、前回の議事録案を配布させていただきました。お忙しいところ、恐縮ですが、内容を御確認いただきまして、修正点等がありましたら、令和7年4月4日(金)までに、事務局まで御連絡ください。
また、議題の1で説明させていただいたとおり、今回以降の議事録につきましては、会議後2週間を目途としまして、委員の皆様にメールにて案を送付させていただき、1週間程度で御確認いただく流れとなります。今回の協議会の議事録案につきましても、概ね2週間程度しましたら、皆様に御確認の依頼をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
また、次回の開催予定は、令和7年5月中旬・下旬頃を予定しております。
詳細につきましては、決まり次第、委員の皆様に開催通知を送付させていただきます。
最後に、今年度末で退任される委員の方が2名おられます。本日の協議会が最後の御出席となりますので、恐縮ですが一言、御挨拶を賜れればと思います。
まず、公募市民委員として、平成21年11月から約16年間、当協議会に御尽力いただきました、片岡委員です。よろしくお願いします。
【委員】
片岡です。16年も委員をさせていただいていたと今改めて実感し、びっくりしております。この度家族が転勤することになり、残念なのですが、退任させていただくことになりました。16年ほど前、小多機ができるということで、プレゼンなどを伺って、すごくよいものができると期待をしたのですが、それが続かなかったことが残念であり、いつ再開していただけるんだろうというドキドキ感もあったのですが、やはり狛江には中々そういう資源が育たなかったなと感じております。せっかく来ていただいた事業者をもっと委員の皆さんで評価したり、どのような感じで利用されているんですかなど進捗状況を管理したり、そういったことがあった方がよかったんだろうなという思いはあります。長い間、ありがとうございました。どうもお世話になりました。
【事務局】
ありがとうございます。
続きまして、平成22年8月から約15年間、当協議会に御尽力いただきました、小楠委員です。それでは、よろしくお願いします。
【委員】
狛江市社会福祉協議会の小楠です。今月末で社協の方を定年退職になりますので、それに伴いこちらの方もやめさせていただくことになりますが、後任の委員に関しましては、今後、選出を予定しておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。こちらの委員会の委員としては、地域密着型の事業所をぜひとも任期の中で見つけたいと思っていたのですが、見つけることができず、残念ではありますが、今後の公募に期待をしたいと思います。ありがとうございました。
【事務局】
ありがとうございます。
その他事項としましては、以上です。
【会長】
事務局より、その他事項について説明がありました。
それでは、本日予定の議題は以上になります。
次回の日程は、先ほど事務局から説明があったとおりですので、よろしくお願いします。
それでは、本日の協議会は、これで終了します。皆様お疲れ様でした。
|
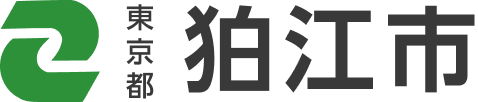
 印刷
印刷
 戻る
戻る
 ページの先頭
ページの先頭