|
7 会議の結果
議題1 会議の取扱いについて
【事務局より追加資料について説明】
会議及び会議録の取扱いについて【承認】
議題2 狛江市交通安全計画の進捗について
【事務局より資料3・4について説明】
-委員からの主な意見・質問等-
○会長
ここから、皆様からのご意見やご質問をいただく時間とさせていただきます。事務局より資料3と資料4の説明をしていただきました。資料3のタイトルに交通安全計画の進捗状況と書かれております。基本的な計画があって、その計画にのっとって目的を達成するために、狛江市交通安全計画を策定しております。交通事故という悲惨なことで、市民の命を失ってはなりません。究極の目標は交通事故ゼロですが、どうしても事故は起きてしまうので、それを1件でも少なくするための計画です。様々な視点から交通安全を進めるため、この会議は年に1回、交通安全に関係する私たちがこのように集まり、計画の進捗状況を確認し、意見交換をしながら、より良い交通安全施策を進めていくという趣旨でございます。まず副会長、ご発言をお願いします。
○副会長
狛江市は交通死亡事故が7年以上ないという話がありました。私が毎日見守りをしている中で危ないと思うのは、車がぎりぎり往来できる道路の横断歩道のないところで、子どもが後ろを確認せず、急に反対側に渡る場面です。そのたびにその子どもに対しては、「横断歩道までは同じ側を歩きましょう」、「反対側に渡るときは後方の車に気をつけて左右もちゃんと見ましょう」という話をしております。
また、最近大きく変わったことがありまして、今までは丸山通りを市民グラウンドの方から北にまっすぐ第五小学校の方に行くと、正門に向かって右に曲がるところに点滅信号がありました。昨年の調布警察署と狛江市との通学路合同点検において、点滅信号に対して黄色の点滅で徐行しない車があるとか、赤い点滅信号に対して一時停止しない車があるという話をしたところ、信号がない方が車は気をつけるのかもしれないと調布警察署の方から話がありました。2~3年前から、通学路合同点検の際にその話をしていたのですが、ここ数か月の間に点滅信号がなくなりました。車が気をつけているかと申しますと、そうでもありません。見守りをしている身からすると、点滅信号があれば道路交通法的に注意しやすかったのですが、信号がなくなったことで私が止めたことに対して、ドライバーが反論してくるのではないかという恐怖があります。信号はあろうがなかろうが歩行者優先というところを、しっかりとドライバーの方には意識をしていただきたいと思います。これからも狛江市は交通死亡事故ゼロであって欲しいので、黄色いビブスを着て見守りをしている人がもう少し増えればいいなと思います。
○会長
ありがとうございました。毎日見守りをされて非常にご尽力されている日々だと思いますが、子どもの振る舞いを見ているとやはり危ないことがあるので、見守りはやはり重要であり、交通安全教育を充実させるため、どのようにすべきなのかと思いました。点滅信号から一時停止規制に変えても、非優先側は一時停止には変わりませんが、信号というのは存在感がありますので、ドライバーとトラブルが起きにくいということは、確かにあるかもしれません。
他にご意見ありますでしょうか。
○H委員
春と秋の全国交通安全運動期間と毎月10日の決まった日に、交通安全協会として街角に立っているのですが、その他にボランティアで立たれている方が幾人もいらっしゃいます。安心安全ボランティアの黄色ビブスを着ていない、本当にお気持ちで立っていただいている方に何かあった場合に、例えばボランティア保険などが適用されないのではないかと心配しています。
また、資料についてですが、道路の整備のところで、八幡通りは、整備が終わったのでしょうか。車では運転しにくくなり、歩行者に対してすごくいいと思います。事故の発生件数等を把握されていると思いますので、今後も同様の道路を選んでいただき、整備の計画に乗せていただければ幸いです。
○D委員
安心安全パトロールというものを市民の皆さん、防犯協会の皆さんを中心に実施をしていただいており、その他に学校安全ボランティアとして、パトロール活動をしていただいております。この登録をしていただいている方はボランティア保険に加入していただいていますので、ボランティア活動の際にビブスを着ていなくても、活動中ということであれば、保険の対象となります。しかし、実際には市で把握できておらず、保険や登録もされていない方が、活動をされている場合、万が一の事故発生時の補償はありません。
○会長
ありがとうございます。八幡通りでいつ頃にどのような対策をなさっているか、C委員お願いします。
○C委員
八幡通りは地形的に隣接する調布市への抜け道になっており、大通りを走行しない車両が生活道路を通り抜けて調布方面へ通行するので、以前から問題視されていた路線でした。そういった中で平成29年に八幡通り整備計画を策定しました。きっかけというのは、そういったお声があったことと、かつて死亡事故もありましたので、地域の方も含め、どういう整備をしていくかという整備計画を平成29年3月に策定し、その中で要対策箇所を4か所定めまして、そこを重点的に整備していくことになりました。そのうち3か所は、用地買収も含め地域の方のご協力によって実現しました。1か所は実現が難しい状態で、昨年度の整備で、一区切りの段階でございます。それ以外に同様の路線があるかというところですが、計画に基づいて整備を行う整備課と、維持管理する道路交通課で連携し、今後どのように路線を指定していくか協議していきたいと思います。
○会長
ありがとうございます。基本的には用地買収をして、例えばその歩道空間を確保したとか、そういったことでしょうか。
○C委員
先ほどご説明した要対策箇所については、用地買収も含めて道路区域を広げたところで歩行空間を設け、人の滞留場所を設けたことと、ボラードを利用して狭さくにして、一般車両の走行速度を抑える対策です。
○会長
今後の計画は道路交通課と連携されるということでしたが、他の箇所について、今後の見通しはありますでしょうか。
○E委員
交通安全対策としては、ポイントで交差点に着目した点の対策と路線としての対策があり、先ほどの八幡通りは路線としての対策になります。更に面としての対策ということで狛江市内は3か所、ゾーン30を設けて交通安全対策を進めているところです。さらにゾーン30プラスも含めて小学校周辺の面的な交通安全対策をしていこうという方向性もあります。
○会長
ありがとうございました。ビブスを着ていなくても、登録していればその対象になるということですので、自主的になさっている方に、是非御確認いただきたいのですが、登録は難しい手続ではないですか。
○D委員
基本的には、安心安全パトロールのほとんどは、町会等の団体に加入していただいて、活動していただいています。学校安全ボランティアは、個人で登録できるかどうか確認が取れていないので何とも申し上げられないですが、安心安全パトロールは、基本としては団体で申し込みいただく形になっています。
○会長
狛江市から町会や学校を通じてなど、一番良い方法で、自主的にボランティアをされている方に伝えていただきたいと思います。今ゾーン30プラスの話がありましたが、皆様御存じですか。車の速度規制の多くは路線で指定されますので、例えば、この交差点から40キロ規制だったら40という丸い標識が立ち、地図で見ると線で40キロの規制がかかるイメージになります。道路と道路に囲まれた住宅街の中の生活道路は複雑に通っていて、全部30キロ規制にするためには、全ての生活道路に標識を立てる方法もなくはないのですが、コストもかかりますし、大型車が通ると接触するおそれもありますので、住宅街の入口全部に標識をたてて、この先このエリアは全部30キロ規制という規制の考え方がゾーン30というものになります。ゾーン30プラスのプラスはハード対策ということです。例えばハンプをエリアの入口につけることで住民の皆様に迷惑をかけずに、スピードを落とさせることができるといったようなものです。子どもたちのため対策、高齢者の方も含めた歩行者を守るための安全対策です。他にご意見ありますでしょうか。
○副会長
資料3の3ページに自転車免許証の配布、学校への自転車教室の実施があるのですが、第五小学校でいうと小学2年生の時に実施します。ただ、高学年になってきますと、スマホを持ち始めます。地域の方に聞くと、ながらスマホをしていて危ないという話も聞きますし、友達同士で横になって運転していたり、スピードを出していたり、危ない場面が見られるので、可能であれば高学年の時にもう1回、自転車の安全教室をしていただければいいのではないかという話を地域から聞きました。
○会長
ありがとうございます。小学2年生の時になさっていて、これをもう少し頻度を高め、高学年に対しても行った方がよろしいのではないかということで、F委員お願いします。
○F委員
交通安全については、学校全体で行う安全教育で三つの柱の一つということで、日常的に学校では交通安全に対する指導はしていただいていると認識しています。私も登下校の様子を時々見ていると、追いかけ合ったりして危ない場面を見ることもありますが、狛江市の教育委員会としては小学2年生の時にそういう状況が多くなるということで、2年時に行っていただくものです。また中学生になった時には道路交通課と連携して、スケアード・ストレートで交通安全の意識を学校全体で図っていくことを位置付けております。さらに、校長会等でも、交通安全については、ヘルメットの着用等々も含めて指導するように進めていきたいと思います。
○会長
ここに書かれている自転車教室というのは確かに2年生の時に1回ですが、それ以外の日常的な交通安全の指導は、それぞれの学校で状況に応じてなさっているということです。小学校の先生は教育指導要領が教育課程の基準となりますが、実はそこに交通安全という言葉がほぼ見当たらないので、指導要領外のところで、学校の先生方が臨機応変に対応しなければならないといった状況となります。皆様記憶されていると思いますが、千葉県八街市で飲酒したドライバーが運転していたトラックで児童が亡くなった事件です。私は千葉県の教育庁でアドバイザーをしているのですが、毎年千葉県の各地域をローテーションでモデル校というのが決められます。文部科学省の事業ですが、県教育委員会が事務局となって、モデル校の全児童に対して交通安全の指導を行う制度です。その中で事例を御紹介すると、交通ルールを高学年が低学年に教えます。例えば、5年生が2年生に対して、安全マップを作って教えたり、最後はタブレットを使って確認テストまで作ったりしています。これは実は役割演技法で5年生にとっても高い効果が期待される教育です。教えられる側もちろん、教える側も教育効果が高まります。子どもたちの文脈やボキャブラリーで伝えるので、大人からとは違う伝わり方がしますし、5年生も言った以上は守らないといけないということもあります。この資料の自転車教室というのは、市の交通安全の担当者が小学校を回っていくようなものですか。
●事務局
各学校単位で時間を設けて、授業の一つとしての交通安全教室、若しくはPTAが地区委員会の中で、交通安全教室のイベントで設けたりすることもあり、そういったご相談については、学校の先生やPTAの役員の方から、市に連絡が入り、警察と連携を取りながら、学校に赴いて指導させていただいていました。しかし、コロナ禍以降は、機会が減少しております。表を見ていただいてわかりますように令和2年度以降の運転免許証の0は、各学校から申請がない状況です。
○会長
令和2年からコロナ禍ですから明確ですね。ずっと減ったままなのはもったいないですね。ちなみに、小学校の話は結構出ていますが、園児のお立場で何かお話しできそうなこと、確認したいことございますか。
○G委員
三島保育園の取組みとしては、調布警察署の方に来ていただいて、4~5歳児を中心に、信号の渡り方など、学ぶ力を養う機会を毎年設けています。子どもたちがどこまでそれを覚えているかということもありますが、一度そういう話を聞いておくと、「そういえば話を聞いたな」となります。全然知らないよりは知っていることが大事だと思うので、取り組みを続けていきたいと思います。園児連の役員もしていますが、園児連の中で話があったことは、自転車のヘルメットです。子どもたちの着用率は高いのですが、保護者の方の着用率がかなり低いので、どのように啓発していくか、園児連で話題になっていますので、園としても被っていきましょうというお声をかけますが、なかなか難しいと感じています。
○会長
ありがとうございます。おっしゃる通り、「手を挙げて右見て左見て右見て」という指導は、人類全世界、未来永ごうやり続けるべきことです。おっしゃった中で印象的なのが、どこまで覚えているかというところです。それは恐らく最初の気づきを与えることを園で行うと思いますが、継続させるということは、家庭や地域などの子どもの日常に近い立場の大人たちの役割だと思います。家庭や地域をいかに巻き込んで、持続的に日常生活への浸透を図るのか、自転車のヘルメットの話題においてもそういうことが重要になってくると思います。そのことをいかに保護者の皆様に、認識していただけるのかというところが重要になってくるということです。その意識が高まると恐らくヘルメットの着用率が変わってくるのではないかと思います。狛江市でもヘルメット着用をかなり推進していただいていると思いますが、いかがでしょうか。
●事務局
ヘルメットを被っていないお子様も中には見受けられます。しかし、それは子どもが被る被らないではなくて、保護者の意識だと思います。コロナ禍前になりますが、いくつかの市内の幼稚園、それから保育園から依頼を受け、園児用の教室と、続けて、保護者に対する教室を適宜設けていた園がいくつかございます。調布警察署と協力をして、そこに赴いて、短時間ですが、保護者にも交通安全教室をさせていただいた経緯がございましたが、コロナ禍になり、そういった経緯や取組みがなくなり、若しくは、担当者が変わり、近年は実施できていない状況です。先ほども説明したとおり、25歳から64歳の方の事故が非常に多く、30代、40代で周囲を確認しない保護者の方もいるかと思いますので、そういった方々にはしっかりと機会を設けて、交通安全指導はしていきたいと感じているところです。
○会長
ありがとうございます。東京都生活文化スポーツ局がヘルメット着用のための啓発動画を作って配信しています。その中で「お父さんは被らなくていいんだよ」というセリフの後にお父さんが事故にあう流れでストーリーが作られていたり、ヘルメットに豆腐を入れて落下させる実験をしたりしています。他にご発言をいただける方はお願いします。
○J委員
一点目は、狛江市の施策については資料3と4はよく理解でき、安心安全の教室、スケアード・ストレイトやヘルメット着用の推進などは評価したいと思います。副会長からボランティアという話がありましたが、私も月2回、10年以上子どもの登下校の時に町内会の活動の一つとして、見守りをさせていただいています。狛江市に限ったことではありませんが、交通安全や防犯も含めてボランティアの活動とその効果に対して、自分で論文を探しましたが、ボランティアの見守りや防犯を含めた活動が、数が増えるとともに、事故や犯罪の数が減ってきているというのがわかりました。私自身のボランティア活動も、その一翼を担っていたのだと思い、すごくうれしかったです。しかし、ボランティア活動の限界として、どうしても人数が減ってきてしまったりしています。これは提案ですが、23区では、ホームページに気楽にボランティアしませんかという感じで、防犯や交通安全の見守りに限らず広報しています。例えばマラソンしながら見守ることなども、ボランティアになるのかなと思います。行政としてそのような活動を推進している地域もあるので、交通安全の一つの取組みに市民のボランティアを取り込んでいってほしいと思います。私は町内会活動の一つとしてやっていますが、町内会とかそういうことではなく一人一人の行動がボランティアになるという啓発を、何かやっていただけたら効果があるのではないかと思いました。最後に、前回の会議でも交通事故の話をさせていただきました。この資料の数値の中に含まれているのだと思ったのですが、死亡ではないのですが、いわゆる植物状態という状況です。100%加害者の責任で刑事裁判の判決が出て、これから民事裁判になるところです。警察へのお願いになってしまうかもしれないのですが、交通事故はこちらが幾ら気をつけていても駄目なこともあります。その加害者の人は、前方不注意でしたが、事故の前にもシートベルト未着用など多くの違反を繰り返し、その事故の後にも時速40キロオーバーで交通違反をしていたことが刑事裁判で出てきました。運転する側に対しての注意をしていただけるとありがたいと思いました。
○会長
ありがとうございました、貴重な内容も含めてお話しいただきました。道路交通法の取締りも関わってきますし、ボランティアをいかに増やすのかという、担い手不足の話はすごく話題にのぼるのですが、交通ボランティアでも全国的に言われているのですが、実はポテンシャルの高い人が潜在しているということです。そういう人たちをいかに実活動につなげていくかの後押しをどうしていくのかというところも、恐らくヒントをいただいたのではないかと思いますので、是非お考えいただければと思います。
○I委員
自転車に乗る際、スピードを出している訳ではありませんが、一時停止なのに止まらず交差点に進入してしまうことがあります。1日1回とまでは言いませんが、結構な頻度でヒヤッとすることがあり、実際、怒鳴られたり、注意を受けたりすることもあります。どうしても一時停止をゆっくり走ればいいかと甘えた気持ちがある中で、曲がったら危なかったケースが自分の中で散見しています。その都度気をつけようと思うのですが、「止まれ」が気づきにくいです。道路を見ればもちろん書いてありますが、ふだん生活しているところは当たり前のように自転車に乗っているので、意識をしていません。自分にとっての意識啓発は、嫌な気持ちにはなりますが、注意されたことと思います。つい先日、知り合いの若い40代の男性が自転車で転んで骨折する事故をしたのですが、ヘルメットを着用していたので頭は大丈夫だったという話を伺い、やはりヘルメットはすごく大事だと気づかせてもらいました。日常の中で、ヘルメットを付ける手間がなかなかできなかったりするのですが、意識啓発という部分では私自身この会議に参加させていただいて、気をつけなければいけないと学ばせていただいているところです。
○会長
ありがとうございました。自転車のお話でしたが、罰則の強化という話もあります。飲酒の話は当然ですが、ながら運転についてです。ながら運転はかなり罰則が強化され、14歳以上が検挙対象です。青切符制度も恐らくこの1年半以内には始まります。また、踏切が鳴り始めてから進入する行為も重罪です。自分がやっていることがどれだけ道路交通法的によろしくないことかを知らないといけないと思います。また、自転車の一時停止について、1回計算したのですが、信号のない交差点で起きた事故で、自転車の人が一時停止違反をしていた割合は80%です。東京都の自転車事故発生率から、東京都民が全員、自転車乗車時の一時停止を1年間守れば、東京都の交通事故は10%減です。みんな当たり前のように「自分は止まらなくても大丈夫」という確率の低いロシアンルーレットをやっている状態で、滑稽な状況です。それを自分ごとにいかに気づいてもらうのかということを考えなければいけないし、気づけば恐らくヘルメット着用率も高まるのであろうと、私もこの課題に向かいあっております。他にご発言いただていない方いらっしゃいますか。
○B委員
全体的な話になってしまいますが、警察としては環境面の対策、指導、安全教育、取締りといった総合的な面から、交通安全、事故防止を進めていきたいと思っております。お子さんの事故の話もそうですが、保育園や幼稚園から、年中・年長さんに対して、安全教育をして欲しいというご意見があり、保育園にお邪魔して模擬の横断歩道を作ったり、時には騎馬隊を呼んで、実際の横断歩道でどうやって渡るかといった訓練をしたりしています。そうしますと馬に会ったことの方が印象に残ってしまうかもしれないのですが、そういう機会を通じて、少しでも何かの時に思い出してくれればありがたいという思いを込めて安全教育に取り組んでいます。保護者の意識については、入学前の保護者に対し、小学校から要請を受けて保護者に安全教育や、短時間にはなりますが、こういった事故に気を付けてくださいなど、そういったことも行っております。年代別に応じた指導を何とか継続したいと考えております。また、運転する側や自転車に乗られる方にとっては、事故が起きていても自分ごととして、なかなかとらえにくいというところもあるかと思います。警察官が街角に立って、姿を見せて危ない時に警笛で注意をしたりですとか、そういったところでの気づきが一つ一つの事故防止に繋がると思っておりますので、指導や取締りというところにも力を入れて、少しでも大きな事故に繋がる前に何とか食い止めていきたいと思っています。
○会長
ありがとうございます。狛江市では昨日の時点で交通死亡事故ゼロが連続2598日ということですが、交通死亡事故ゼロをずっと続けて、日を重ねていきたいと思います。
○副会長
度々申し上げていますが、警察の方に、東野川地域の登校時間、7時半から8時半の通行禁止の時間帯に道路に立っていただくということが、今年度まだ来ていただいておりません。できれば4月、新入生も入って参りますので、可能でしたら、各校抜き打ちで来ていただければと思います。第五小学校の付近は成城への抜け道で、各校そういう道路もあるかと思いますので、お忙しいとは思いますが立っていただきたいと思います。よろしくお願いします。
○会長
ありがとうございました。皆様からいろいろと意見交換いただけたということでございますので、こちらの内容を踏まえてですね、今後の交通安全対策について、内容を更新し、またご報告をいただければと思います。
議 題③ その他
【事務局より次回会議の開催日程及び会議録の確認について説明】
○会長
それでは皆様お忙しい中ありがとうございました。これで令和6年度第1回狛江市交通安全対策会議を終了とさせていただきたいと思います。
|
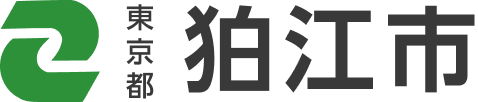
 印刷
印刷
 戻る
戻る
 ページの先頭
ページの先頭