|
議題1 狛江市環境基本計画及び第2期狛江市環境保全実施計画に基づく進捗状況報告書(2024年度実績)について
事務局より資料を説明。
(委員)
施策評価結果一覧を見たが、AとBばかりである。7ページ以降の各論は、具体的な内容や実施する年度が書かれており、内容はわかりやすいが、AとBばかりで進捗などがわかりづらい。
継続している事業は、例えばこまエコまつりなどは、ベースの部分は変わらないかと思うので、前年度どおりとの記載でもいいのではないか。また、新規の事業は、目立つようにしてはいかがか。事業評価はABCDの4段階の評価でいいと思うが、施策評価は点数評価にした方がわかりやすいと感じた。
(事務局)
昨年度に進捗状況報告書を作成し、評価の基準を変更した。前年度の比較というより、市民生活への影響、外部環境への影響を観点に評価している。
施策評価は、各事業の影響度を鑑み、全体を見て評価をしている。
新規事業は、実施年度や★印の実施計画を策定した際の新規拡充事業として標記をしている。
施策の点数評価は、今回はしていないが、AよりのB、CよりのBもあり、課題として検討する。
(委員)
予定の進捗を超えた事業は、A+にするなど細分化した方がわかりやすい。
(委員)
この議論は、前年度にも私が提起したこととほぼ同じことである。評価をする中身と評価軸がうまく合っていないことと、評価すべき事業と評価しなくてもいい事業が混ざっている。評価する目的は、次年度につなげるために評価を行っていることであり、評価軸を工夫する必要があると思う。施策評価を何に活かすかがわからない。
(事務局)
施策評価は、環境基本計画の評価とし、進捗の確認をしている。
(会長)
評価は、PDCAサイクルで回し、当年度や次年度の施策や事業に反映し、自己点検をしていくことである。その評価の妥当性をこの審議会で審議をしていく。事業評価は、達成度の評価であり、施策評価は、質の評価である。質的評価することは、見えづらい部分であり、事務局としては、施策評価は、事業評価の総合評価として行っていると理解している。委員からの提案があったように施策評価を数値評価にすると、より達成度が見えてくるとは思うが、ただ、数値化ができない事業もあることやこれまでの評価方法の継続性の観点もある。委員からの評価についての指摘事項は、次の実施計画を策定する際に参考にしてほしい。
第2期実施計画は、2023年度から2025年度までの3カ年計画で進捗してきているため、この段階で途中変更することは、継続性の面から難しい。
(委員)
実施計画の最大の目標が2030年度における温室効果ガス排出量を2013年度比で54%削減であると思う。目標に対する進捗が果たして順調であるのか、実施計画を強化していかなければならないかという視点で6ページの総括を見ると、「さらなる脱炭素の推進が求められる」部分の記述が総括のポイントであると思うが、数字的に出すのは難しいのであれば、順調か加速化すべきなどの踏み込んだ書き方をした方がいいと思う。
(会長)
環境の施策や事業の評価は1年間で効果がでにくく、単年度評価はなじみにくい部分があり、施策の効果を評価するには、長い目で見ないといけない。3年間の実施計画の総括や環境基本計画全体の総括で、市の環境面への影響や改善の状況等を総括的にまとめてはどうか。
(委員)
7ページの緑のまち推進補助制度の運用について、補助制度に至らなかったとあるが、Cで終わりではなく、今後への改善(検討)策・方向性を示した方がいい。
(事務局)
評価がCのものについては、記述を検討する。
(委員)
22ページの3D都市モデルを活用した太陽光発電の導入ポテンシャルは、市民や事業者にPRしているか。
(事務局)
前年度末にHP上に掲載し、今年度5月号のこまeco通信に記事の掲載や夏に向けてポテンシャルが高い戸建住宅や集合住宅に、参考情報として案内をしていくところである。
(委員)
23ページの2-2-2の再エネ電気切替キャンペーン、2-2-3和泉小学童クラブの太陽光発電の設置について予定どおりであれば、A評価でもいいと思う。これについても市民にPRしていくと啓発になると思う。
(事務局)
容量の問題やこれまでの件数との比較でB評価としている。
(会長)
24ページのカーボンニュートラルガスの導入をC評価とした理由を伺いたい。
(事務局)
導入の方向性で、事業者とのヒアリングや資料を集めていたところではあるが、2025年度に実施できなかったため、導入検討と言うところで、Cと評価した。
(委員)
35ページの4-2-1の新設改良する道路への雨水浸透施設の設置は、評価の対象外であっていいと思う。イベントについても雨天で実施できなかったから、評価がCであることもおかしいと思う。
(事務局)
担当課と調整して、表記の仕方を検討する。
(会長)
イベントも荒天でできない場合は、市の責任に及ばないことなので、評価の対象外とすることも1つの考え方だと思う。
(委員)
34ページのPFOSのことは、68ページに地下水水質調査結果の記載があるが、地下水に限定した調査でいいのか。住民の健康維持であれば、水道や土壌、河川でも測定できるものは測定して公表してはいかがか。
(事務局)
PFOSは、地下水から検出されたことで、調査している。河川での検出などの明確な情報は、出ていないところである。上水道は、東京都で調査を行っており、公表しているが、狛江でも2025年度に地下水について調査をする。
(会長)
委員の意見を踏まえると、水道水の調査結果について掲載した方がいいと思う。
(委員)
53ページのグラフを電気、ガス、全体の使用量の推移で出した方がいい。
(委員)
今や省エネのために空調の使用を抑える事業者も少なく、空調の利用はやむを得ない。恐らく、猛暑によって空調を使用したことが要因だと思うが、電気使用量が増えていることについての分析を総括に記載するべきである。
(委員)
現状、温室効果ガス排出量が2013年度比で29.2%であり、2030年度には、50%削減の数値目標であり、分析を踏まえて、今年度の計画を考えるべきである。
(会長)
都市ガスからの温室効果ガスの排出量が全体の6割を占めており、ガス対策を考えるべきである。カーボンニュートラルガスの導入に踏み込まないと目標値の達成は難しい。
(委員)
2030年度の目標を達成するためには、省エネをすることは当然であるが、カーボンニュートラルガスの導入も検討してほしい。
(委員)
ガスの使用量は、基礎排出係数と調整後排出係数のどちらで計算しているか。
(事務局)
2024年度、2023年度ともに調整後排出係数で計算している。53ページの右の欄に100%再生可能エネルギー電気を除き、最も使用電力量が多い電気の排出係数を掲載している。
(会長)
主な排出係数は、一般的な排出係数が変動するものか確認して欲しい。また、53ページのグラフにガスの使用量も入れてほしい。進捗状況報告書の取りまとめについて、今後のスケジュールを教えてほしい。
(事務局)
委員の意見を反映し、7月15日に庁内の推進本部、その後に庁議に諮る予定である。7月中に完成予定である。
(会長)
今年度の進捗状況報告書に関して、委員から評価の軸やあり方について意見が寄せられた。これは、実施計画の途中で直ちに対応が難しい部分であるが、課題として受け止めて、次の計画の策定時に検討していただきたい。また、今回の報告書について、本日の審議会の意見を受けて、事務局で整理して表記や追記、修正を行うことになるが、委員意見を整理して取りまとめの内容については、会長と事務局に一任していただきたい。
議題3 その他
(委員)
環境に関する会議で資料が多いことが気になる。資料は、紙ベースでなくてもいい。
(会長)
委員によっては紙の資料が適している場合もあるので、次回以降は、委員の選択方式にしてもいいと思う。
(事務局)
今年度は、下水道総合計画や第3期狛江市環境保全実施計画の策定を予定しており、第2回狛江市環境保全審議会以降の予定は、後日案内をする。
|
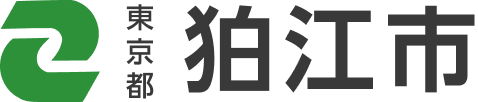
 印刷
印刷
 戻る
戻る
 ページの先頭
ページの先頭