第2回狛江市総合基本計画審議会(平成31年1月21日開催)
|
1 日時
|
平成31年1月21日(月曜日)午後7時~9時18分
|
|
2 場所
|
特別会議室
|
|
3 出席者
|
委員長 福島 康仁 委員長職務代理者 上田 英司
委員 五十嵐 太一 委員 太田 ひろみ
委員 佐藤 正志 委員 杉浦 浩
委員 髙橋 信幸 委員 冨永 和身
委員 馬場 健司 委員 五十嵐 秀司
委員 周東 三和子 委員 都築 完
委員 成井 篤 委員 松本 すみ子
委員 水野 穰
事務局 髙橋企画財政部長 田部井政策室長
池田企画調整担当主任 佐々木企画調整担当主任
西村企画調整担当主事
|
| 4 欠席者 |
委員 平谷 英明 |
| 5 議題 |
- 指標の推移について
- 狛江市総合基本計画策定庁内プロジェクトチームまとめについて
- 総合基本計画策定にあたっての視点について
- 狛江市第4次基本構想の構成(素案)について
- 狛江市基本計画策定分科会について
- その他
|
| 6 会議の結果 |
|
議題1 指標の推移について
-事務局より資料の説明-
議題2 狛江市総合基本計画策定庁内プロジェクトチームまとめについて
-事務局より資料の説明-
議題3 総合基本計画策定にあたっての視点について
-事務局より資料の説明-
- 委員長
事務局からの説明について、意見や質問等はあるか。
- 水野委員
現在、庁内において市の10年・20年先を考える未来戦略会議という市長と概ね49歳以下の係長職及び課長補佐相当職で構成される会議体を設置し、検討を進めているが、今後、そこでの検討資料も本審議会の資料として提示させていただき、総合基本計画策定の参考資料とさせていただきたいと考えている。
議題4 狛江市第4次基本構想の構成(素案)について
-事務局より資料の説明-
- 委員長
事務局からの説明について、意見や質問等はあるか。
- 髙橋委員
第3次基本構想にある「狛江市の将来都市像」及び「まちの姿を構成する3つの要素」について、第4次基本構想の構成素案にはどのような形で関連付けられているのか。
- 事務局
第3次基本構想では、7つの政策を要約する形で「まちの姿を構成する3つの要素」が位置づけられているが、第4次基本構想の構成素案では、すべての政策に関わる要素として現段階では3つ表現させていただいている。
- 髙橋委員
新たに掲げる3つの要素が関わり合いながら新しい将来都市像の表現を考えていくという理解でよろしいか。
- 事務局
その通りである。
- 周東委員
オール狛江という表現について、今までの議論には出てこなかったと思うが、説明をお願いする。
- 事務局
市民参加・市民協働のさらなる推進等のイメージをつかんでいただくために言葉を補足させていただいた。市民がまちづくりに関わることが必要だという視点を盛り込むために記載したものである。
- 杉浦委員
「オール狛江」、「すべての人」、「誰一人」という言葉は、耳当たりは非常に良いが副作用がある。今後、議論すると思うが、すべての市民に対するサービスを表現する言葉は慎重に選ぶ必要がある。
- 事務局
次回の審議会で3つの要素と7つの政策について、100字~200字程度の説明文を提示する予定である。
- 上田委員
資料でSDGsのマークが使用されているが、今後、議論進めていく上で、総合基本計画で使用する指標をSDGsに基づく指標と連動させたものとして設定しないのであれば、SDGsウォッシュといわれる可能性がある。資料のSDGsに関する説明も積極的に記載されているものなのか消極的に記載されているものなのか読み取れない。市民にはSDGsに初めて触れる方もいると思うため、慎重な議論が必要である。
また、市民参加・市民協働について、「7 持続可能な自治体経営」にも記載されているのは違和感がある。市民が行政と協働するというよりも行政コストの削減のためだと誤解される恐れがあるため、整理する必要があると思う。
- 委員長
市民参加・市民協働は、3つの要素には引き続き盛り込むということで良いか。
- 髙橋委員
一番大切な要素として市民参加・市民協働がある一方、「7 持続可能な自治体経営」に、市民参加・市民協働を位置づけることには私も違和感がある。行政コストの削減のために、市民を活用すると捉えられるため、3つの要素の理念と大きな差が出てしまうと思う。市民参加・市民協働は一番の基礎であるため、「7 持続可能な自治体経営」に記載のある行財政運営や行政評価、情報公開等とは別項目として記載しても良いと思う。
- 委員長
市民参加・市民協働は、「7 持続可能な自治体経営」から削除し、3つの要素には盛り込むということで良いか。
- 周東委員
市民参加・市民協働はまちづくりの基礎となるものであるため、それが7つの各項目で謳われないといけない。また、「2 地域で支え合う安心・安全なまち」が防災及び防犯に限られているのは違和感がある。市民生活の面から考えたら、様々なことがまちづくり全体に関係してくるため、整理をお願いする。
- 委員長
「2 地域で支え合う安心・安全なまち」を構成する要素については、次回もご議論いただきたいと思う。防災・防犯をイメージしてしまうが、ここには他も入ることを前提として、広い意味で使うことを考えてはどうか。
- 髙橋委員
「思いやりを大切に」、「地域で支え合う」、「いきいきとのびやかに」、「いつまでも健康で」、は福祉分野で使用する用語であるため、今後、各施策の分野を切り分けることを考えると適切な表現を考えた方が良いと思う。
「1 思いやりを大切にするまち」について言えば、人権や国際交流のみが、思いやりを大切にすることにはならないのではないか。様々な分野に関係してくるため、表現については整理が必要である。
また、「4 子どもも大人もいきいきとのびやかに暮らすまち」は、範囲が広すぎるのではないかと思う。資料3においても、少子高齢化等が課題として挙げられているが、「4 子どもも大人もいきいきとのびやかに暮らすまち」は、子育て支援等に絞った方が良いのではないか。子育て、学校教育、青少年の3つを子どもの視点としてまとめ、生涯学習、文化・スポーツは、「5 いつまでも健康で暮らし続けるまち」に入れるべきではないか。「5 いつまでも健康で暮らし続けるまち」は、属性別の福祉施策ではなく、地域で暮らす住民皆が幸せに暮らしていける地域社会をつくっていくという視点で良いのではないか。福祉と社会教育が切り分けられているが、歴史的な観点でみると、本来は社会教育、戦後でいうと公民館活動は、戦前の社会事業活動の1つの分野であった。その後公民館活動は、地域福祉と切り分けられ、地域課題の研究はするが、課題の解決を行うのは福祉であるという形になった。本来は、生涯学習、文化・スポーツは地域住民が地域の課題を発見して、皆で幸せに暮らしていくために、提案し実践していくという考えであるため、子育てに含めると範囲が広くなり過ぎて、主旨が変わってしまう恐れがあるため、「4 子どもも大人もいきいきとのびやかに暮らすまち」を整理する必要がある。
- 委員長
「4 子どもも大人もいきいきとのびやかに暮らすまち」については、子どもに焦点を絞ることで良いか。庁内プロジェクトチームにおいても子育ての問題について言及されていることから、良いのではないかと思う。その他の生涯学習、文化・スポーツは、「5 いつまでも健康で暮らし続けるまち」に整理するということで良いか。
- 周東委員
「5 いつまでも健康で暮らし続けるまち」に記載のある生活福祉とは何か。
- 髙橋委員
ここでいう生活福祉とは、生活保護や困窮者自立支援等の生活していく上での経済的困難を解決することを指している。市民にはあまり馴染みのない言葉かもしれない。
また、本構成素案には「就労」の視点が抜けていると思うため、「3 活気にあふれ、にぎわいのあるまち」又は「5 いつまでも健康で暮らし続けるまち」に含めるのが良いと思う。障がい者の働く場や市民生活を安定させるという観点から、商業や農業を含めて、皆が働ける場をどのように作り出していくのか、という視点が必要ではないか。
- 事務局
「3 活気にあふれ、にぎわいのあるまち」は、現在の商業や農業の振興を想定しているため、就労支援は「5 いつまでも健康で暮らし続けるまち」でも良いかと考えている。
- 髙橋委員
商業や農業では、後継者の問題等で働く人がいなくなってしまえば成り立たないことであるため、働く場の確保も視野に入れた方が良いのではないか。一般的に市の就労支援であると障がい者のみを考えてしまうが、全体的に雇用が不安定になっているため、そのことが将来的には市税を納める担税能力のある市民が減っていくということに関係してくる。働くことを狭い意味で捉えないで、市民の経済生活の基盤を市として整備していくという視点で考えていくべきだと思う。
- 水野委員
「3 活気にあふれ、にぎわいのあるまち」は、あくまで市内の産業振興を考えていると思う。就労については、「5 いつまでも健康で暮らし続けるまち」に含め、表題については、健康ではなく、すこやか等の表現に変えてはどうか。
- 周東委員
「3 活気にあふれ、にぎわいのあるまち」には若者等が起業をする支援等も含めるべきではないかと思う。庁内プロジェクトチームからも昼間人口が少なく増やしていくべきとあり、シャッター商店等があるのを見ると、やる気があるがお金がない若者を呼び込む施策についても考えていく必要があると思う。
- 委員長
「5 いつまでも健康で暮らし続けるまち」は、高齢者や障がい者等の属性別ではなく就労を幅広く捉えることとし、また、起業支援については、「3 活気にあふれ、にぎわいのあるまち」に含めるということで良いか。
- 五十嵐(秀)委員
3つの要素についてだが、簡単にいうと、一番上は市民参加・市民協働として政策を推進していく手法、左は市が向かうべきブランド、右は将来の市民の姿をイメージしたものと理解して良いか。
- 事務局
イメージとして、左は、狛江のコンパクトさの活用は安心安全分野や教育分野等、すべての政策に活きてくるということで全体にかかるものとして記載させていただいた。市民参加・市民協働はすべてを推進していく上で重要な要素ということで記載させていただいた。右は、すべての人が安心して暮らせるまちをイメージするものとして、7つの政策を進めていく上で、子どもも若者の高齢者も障がい者も外国人についても、すべての人を考えなくてはならないということで記載させていただいた。
それらをまとめたフレーズについては、改めて議論していただきたいと思う。
- 佐藤委員
構成素案は詳細に記載してあり、1つ1つは理解できるが、市民にとっては分かりづらいのではないか。3つの要素と7つの政策で重複しているものがあるため、1つの文章ですぐに分かるように、政策との区別が明確になり、市民にとって分かりやすい表現にした方が良い。
また、「2 地域で支え合う安心・安全なまち」の言葉には、方法論も含まれている。どのようなまちにしていくかの政策ではなく、方法論も含まれているため、整理した方が良い。
- 事務局
「2 地域で支え合う安心・安全なまち」は、地域コミュニティについても表現したいことから、事務案としてこのような記載としている。
- 都築委員
「1 思いやりを大切にするまち」の人権・平和は、「2 地域で支え合う安心・安全なまち」に含めても良いのではないか。また、国際交流・多文化共生は「5 いつまでも健康で暮らし続けるまち」と類似する考え方で良いのではないか。項目を減らして分かりやすくしても良いと思う。
- 杉浦委員
これからは、ある事業が特定の政策の視点に収まって、その視点でしか捉えない、ということはない。これからは、多様な視点でみる必要があることから、政策の体系のどこに含めるかという議論は厳密にやる必要はないと思う。現段階では仮置きとして、まずは欠落しているものを議論していく方が良いのではないか。
具体的には、商業振興とまちづくりに駅周辺の振興の視点、商業振興に都市基盤の視点があるべきである。「2 地域で支え合う安心・安全なまち」では、防災・防犯のみではなく、水害や直下型地震、木造の不燃管理等の視点も盛り込んでいただきたい。
- 委員長
「2 地域で支え合う安心・安全なまち」及び「3 活気にあふれ、にぎわいのあるまち」は、都市基盤の視点があるため、そのイメージも追加し説明文の作成をお願いする。また、「2 地域で支え合う安心・安全なまち」については、地域で支え合うということについて方法論が含まれているので、膨らませた形で作成をお願いする。
意見があった「1 思いやりを大切にするまち」を7つの政策に残しておくべきかどうかについて、他に意見等はあるか。
- 上田委員
残した方が良いのではないかと思う。SDGsを大きな看板として掲げるのであれば、人権は一番大きな要素になってくるので、それが欠落した施策であれば、なぜわざわざSDGsを取り入れたのかということになってしまう。また、多文化共生は、人権という視点からも必要であると考える。
- 髙橋委員
仮置きで「1 思いやりを大切にするまち」は置いておくべきだと思う。表現は議論の中で決めていくと思うが、男女共同参画が理念的であることからも、市民参加・市民協働も「7 持続可能な自治体経営」から「1 思いやりを大切にするまち」に移動しても良いのではないか。それも含めて仮置きとして、中身は今後議論していく中で決めていけば良いのではないか。
- 委員長
仮置きでそのままで残しておくという意見も出たが、3つの要素に持っていくというのも1つの案であるが、いかがか。「1 思いやりを大切にするまち」は、全体に関係してくることもあると思う。
- 五十嵐(秀)委員
思いやりは、すべてにかかる幅広い理念なので、3つの要素に持っていき、すべての政策にかかる方が分かりやすくて良いと思う。
- 周東委員
3つの要素に持っていくのは賛成である。また、第3次基本構想で「まちの姿を構成する3つの要素」を定めたが、今回の3つの要素がこれに類するものとして整理できていると思う。
- 委員長
「すべての人が安心して暮らせるまち」というところに「思いやりを大切に」を含めても良いかもしれない。
- 成井委員
「1 思いやりを大切にするまち」というのは、3つの要素の1つであるすべての人が安心して暮らせるまちにあてはまるのではないかと思う。
- 上田委員
SDGsを入れるとしたら、思いやりではなく、人権を保障するとしなければならない。人権は大事な要素であり、SDGsを入れるとしたら、今後より具体化していく必要がある。
- 事務局
SDGsについては、現段階では、市として取り組んだ政策の結果がSDGsの目標に資するものもある、という位置づけで記載しており、SDGsの17の目標について、1つ1つ指標を設けようとは考えていない。SDGsについては、その視点を取り込みながら計画作りを行っていきたいとは思っているが、計画の柱として考えているものではない。
- 上田委員
SDGsウォッシュという言葉があるように、そのような位置づけであればSDGsは入れない方が良いと思う。例えば、ジェンダー平等という観点では、女性の管理職の割合や女性議員の割合、各種委員会の女性の割合等が指標として今後出てこないと、SDGsウォッシュとなってしまう。
- 髙橋委員
3つの要素に含めることは意見としては良いと思うが、その場合、例えば男女共同参画や市民参加・市民協働の仕組みをどのように構築し推進していくのか等について、具体的に施策化しないと意味がないと思う。3つの要素で謳っただけでは何も前進しないため、具体的な指標を掲げて毎年度進捗管理を行うことで実現していくことが大切である。3つの要素に含めるとともに具体的な施策化も図らなければならないという位置づけが適していると思う。
- 委員長
「1 思いやりを大切にするまち」については、3つの要素のすべての人が安心して暮らせるまちに含めるとともに、男女共同参画等を具体化するための枠組みについては残しておくということで良いか。
「2 地域で支え合う安心・安全なまち」については、地域コミュニティを含めた形となるよう文章の整理をお願いする。
「3 活気にあふれ、にぎわいのあるまち」については、都市基盤を含めた形となるよう文章の整理をお願いする。
「4 子どもも大人もいきいきとのびやかに暮らすまち」については、子どもの視点に特化することとする。
「5 いつまでも健康で暮らし続けるまち」については、すこやかで暮らし続けられるまちという視点で、高齢者や就労支援等も含めた形となるよう整理をお願いする。
「6 自然と共生し、快適に暮らせるまち」について、意見等はあるか。
- 馬場委員
構成素案はイメージであるため、現在使用している言葉に引っ張られる必要はあまりないと思っている。例えば、自然環境、循環型社会、環境保全等は第3次基本構想でも使用している言葉である。また、本構成素案は資料3とあまりリンクしていないようにも感じる。資料3には、新しい文言も出てきており、例えば、環境への配慮の項目では、「生息する多種多様な生物にも暗い影を落とすことになる。」とあるが、これは環境政策課で生物多様性地域戦略を策定することを想定して記載されているものだと推測できる。そのような文言は積極的に記載していくべきである。また、低炭素社会というものは、これまでも狛江市としてしっかりと取り組んできていることであるため、これについても記載するべきである。更に、資料3から十分に反映されていないと感じたことは、気候変動による適応の考え方について、環境基本計画の一部として位置づけていく可能性があり、そのような気候変動の影響が今後生じてくる中で、どのように適応していくのかという考え方も入れた方が先駆的なものになると思う。構成素案で示されているキーワードは、今現在進行しているものとずれているのではないかと思う。
- 委員長
「6 自然と共生し、快適に暮らせるまち」については、意見のあったキーワードを含めた形で整理をお願いする。
- 事務局
構成素案のキーワードは第3次基本構想のキーワードを入れたものであり、資料3とずれているため、整理させていただく。
- 髙橋委員
ごみ処理についてだが、最近ではごみの分別が課題になっているが、狛江市では店舗等に袋の削減指導等はしているのか。
- 水野委員
ごみ処理については多摩川衛生組合で行っている。プラスティックや可燃ごみの分別回収は行っていない。
- 髙橋委員
混在して回収することで大気汚染につながる可能性はないのか。
- 水野委員
むしろ、混在して回収して高熱処理することで大気汚染を防いでいると聞いている。
- 委員長
「7 持続可能な自治体経営」については、市民参加・市民協働を「1 思いやりを大切にするまち」に移動することとするが、他に意見等はあるか。
- 松本委員
市民参加・市民協働についてだが、高齢者の能力はまだまだ活用できると思う。今は75歳まで働ける時代であり、地元の高齢者の活用を考えた方が良い。働く場の創造として、コミュニティビジネスのような、行政で手が回らないようなところで活躍してもらう等の発想が必要だと思う。就労支援なのか市民参加なのか、どこに入るかは今後の議論でも良いと思うが、その視点を取り入れたいと思う。
- 委員長
コミュニティビジネス等の視点について、市民参加・市民協働等の項目に入れられるかどうか事務局で案の提示をお願いする。「3 活気にあふれ、にぎわいのあるまち」について、「にぎわい」が商業的なイメージを連想することもあると思うので、その視点も踏まえて案の提示をお願いする。
- 五十嵐(秀)委員
「7 持続可能な自治体経営」に含めるべきか分からないが、最近では自治体の財政運営において様々な手法がある。例えば、民間企業の活用や他自治体との連携、資産の活用、シニア世代の活用、クラウドファンディング等もある。今後、人口が減少していく中で自治体経営にそのような活用の視点も必要だと思う。
- 周東委員
「5 いつまでも健康で暮らし続けるまち」について、「4 子どもも大人もいきいきとのびやかに暮らすまち」から生涯学習、文化・スポーツを移動したが、就労も含めると、整理しきれなくなってしまうのではないか。健康や福祉とは別に、地域にどのように貢献していけるかのような、公民館の理念に沿うような学んだものを地域に戻すことや様々な人の力を発揮させるような考えと、保健・医療・福祉分野を切り分けられると良いと思う。
- 松本委員
就労は「3 活気にあふれ、にぎわいのあるまち」でも良いかと思う。
- 委員長
高齢者がずっと働き続けるというのは「5 いつまでも健康で暮らし続けるまち」にも含まれるかもしれない。「3 活気にあふれ、にぎわいのあるまち」は、若者等が就労してまちが活気づいていくというようなイメージかと思う。どのように切り分けられるかは事務局で案の提示をお願いする。次回その案について議論したいと思う。
構成としては、位置づけや文言の修正等はあるが、7つの政策の枠組みで次回からも議論を進めていきたいと思う。この7つの枠組みを前提として、3つの要素、1つ目は市民協働・市民参加、2つ目は思いやりを大切にするということ、3つ目は狛江らしさとしてコンパクトなまちであり、コンパクトさの強みを活かすということ、の3つでまとめることで良いか。
- 五十嵐(秀)委員
3つ目について、3つの文章があるが、これを「コンパクトさの活用」に絞るということか。
- 委員長
全国的にはコンパクトシティの政策はあるが、狛江市は元々コンパクトなまちであり、合併もなく大きくならなかったことが、現在では市の強みとなっており、その要素が前提としてある、というイメージである。
- 五十嵐(秀)委員
強みということであれば、コンパクトさもあると思うが、水と緑や農業、自然、都心から近い等の強みもあり、そのような狛江市の強みを活かしたということを強調できる言葉にまとめた方が良いと思う。
- 事務局
3つの要素は7つの政策と混同しないような、端的に分かりやすくなるよう整理したいと思う。また、施策はいずれどこかの政策に位置づけるよう整理していく必要があるが、当然複数に跨るものも出てくると考えている。
- 委員長
3つの要素についても、簡潔で市民に分かりやすく、イメージしやすいようなものに整理をお願いする。
議題5 狛江市基本計画策定分科会について
-事務局より資料の説明-
- 委員長
特に意見等なければ、資料の通り分科会を設置することとし、市民委員については希望の分科会について、後日事務局まで連絡をお願いする。
議題6 その他
- 委員長
その他特に意見等なければ、次回は2月5日(火曜日)午後7時に開催することとし、第2回審議会を終了させていただく。
|
登録日: / 更新日:
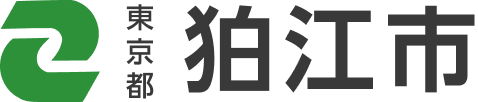
 印刷
印刷
 戻る
戻る
 ページの先頭
ページの先頭