介護保険サービス
ご覧になりたい項目をクリックしてください。
- 要介護・要支援認定
- 介護に関するご相談
- 介護保険の支給限度額
- サービスの利用者負担
- サービスの種類と概要
- 地域密着型サービスの指定
- 市独自のサービス
- 税金の申告に利用する認定証などの交付(障害者控除対象者認定書・おむつ代の医療費控除に必要な確認書)
- 介護保険の保険料
要介護・要支援認定
介護保険サービスを受けるためには、事前にサービスを受けられる対象かどうかの認定を受ける必要があります。
以下のような状態になった場合に、認定の申請が可能です。
- 65歳以上の方で、常に介護を必要とする「要介護状態」や、日常生活を営むのに支障があると見込まれる「要支援状態」になった場合
- 40歳から64歳までの方の場合は、加齢を原因とする16の特定疾病(下表)によって、心身の状態が「要介護状態」または「要支援状態」になった場合
※40歳から64歳までの方の場合は、原因が加齢によるものに限定されますので、交通事故など外傷性の打撲、骨折、脳挫傷などの原因により心身の状態が「要介護状態」または「要支援状態」になった場合は対象となりません。ただし、介護保険の対象とならない方でも、障がい福祉施策によるサービスの対象となる場合があります。
加齢を原因とする16の特定疾病
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症(脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能およびその他の認知機能が低下した状態をいう)
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
※認定の結果、非該当(自立)となった方でも、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援を行う、地域支援事業を利用することができます。
※認定を希望する方は高齢障がい課または地域包括支援センターの窓口で申請してください。
介護に関するご相談
介護保険のサービス内容や、各種申請手続きなどに関するご相談は、以下の「介護に関するご相談窓口」へご相談ください。
介護に関するご相談窓口
あいとぴあ地域包括支援センター
所在地:元和泉2-35-1
電話:03-5438-3565
相談日・時間:月曜日~土曜日、午前8時30分~午後5時30分(第三土曜日は休み)
担当地域:中和泉・西和泉・元和泉・東和泉
地域包括支援センターこまえ正吉苑
所在地:西野川2-27-23
電話:03-5438-2522
相談日・時間:月曜日~土曜日、午前8時30分~午後5時30分
担当地域:和泉本町・東野川・西野川
地域包括支援センターこまえ苑
所在地:岩戸南4-17-17
電話:03-3489-2422
相談日・時間:月曜日~土曜日、午前8時30分~午後5時30分
担当地域:岩戸南・岩戸北・猪方・駒井町
市役所福祉総合相談窓口
電話:03-3430-1111
相談日・時間:月曜日~金曜日、午前8時30分~午後5時
- 要介護(要支援)認定については
高齢障がい課介護保険係(内線2237) - 介護保険のサービスについては
高齢障がい課介護保険係(内線2234・2235・2237) - 介護保険以外の高齢者施策については
高齢障がい課高齢者支援係(内線2222・2223)
地域包括支援センターとは
高齢者が住み慣れた地域でできるだけ自立した生活が送れるように、高齢者の生活全体を継続的に支援していく中心的機関として「地域包括支援センター」が設置されています。
介護が必要になる前の方や、軽度な要介護者への介護予防マネジメント、また高齢者や家族に対する総合的な相談や支援および虐待の防止や早期発見等の権利擁護事業等を行います。
東京都国民健康保険団体連合会による苦情相談(外部リンク)
東京都国民健康保険団体連合会では、介護保険サービスの苦情相談を受け付けるとともに、東京都国民健康保険団体連合会や都内市区町村、また東京都に寄せられた苦情の事例や統計情報を取りまとめた「東京都における介護保険サービスの苦情相談白書」(外部リンク)を作成して公表しています。
介護保険苦情相談員による苦情相談
月2回、午後1時から午後4時まで、市役所福祉総合相談窓口で相談員が介護保険サービスに関する不満や苦情などの相談に応じます。
サービス提供事業者や介護支援専門員(ケアマネジャー)などに相談しても改善が見られない時や、サービス提供事業者に直接言いづらい時はご相談ください。
相談日は、広報こまえの毎月1日号の最終頁「市民相談」の欄をご確認ください。
※相談時間中であれば直接、お電話またはご来庁により相談に対応いたしますが、事前にご予約いただくことも可能です。
介護保険の支給限度額
介護の在宅サービスの利用には、要介護等状態区分別に保険から給付される上限額(月単位の支給限度額)が決められています。
※このうち1割~3割が利用者の自己負担になります。
介護保険の支給限度額 (令和元年10月1日から)
|
要介護等状態区分 |
支給限度額 |
|---|---|
|
要支援1 |
50,320円 |
|
要支援2 |
105,310円 |
|
要介護1 |
167,650円 |
|
要介護2 |
197,050円 |
|
要介護3 |
270,480円 |
|
要介護4 |
309,380円 |
|
要介護5 |
362,170円 |
※上記の額は標準地域のケースで、人件費などのサービス事業者所在地の地域差に応じて限度額加算が行われます。
サービスの利用者負担
「居宅介護サービス計画の作成」以外の介護サービスを受ける際には、原則としてサービスにかかる費用の1割~3割の自己負担があります。
サービスの種類と概要
介護給付(要介護1~5の方)のサービスは○○サービス、予防給付(要支援1・2の方)のサービスは介護予防○○サービスと呼びます。
居宅介護(予防)サービス計画の作成(このサービスだけは自己負担がありません)
- 介護保険のサービスは、サービス利用計画(ケアプラン)に基づいて提供されます。
- 介護保険のサービスは、まずサービス利用計画を作成しなければ利用することができません。
- サービス利用計画は、利用者の依頼に基づき、要介護状態(要介護1~5)のときは居宅介護支援専門員(ケアマネジャー)が、要支援状態(要支援1・2)のときは地域包括支援センターまたは介護予防支援事業者が作成します。介護サービスを利用するためにサービス利用計画の作成を依頼したときは、市に届出をしなければなりません。ただし、通常は居宅介護支援専門員、地域包括支援センターまたは介護予防支援事業者が代行して、この届出を行っています。
- 居宅介護支援専門員は、利用者や家族の方からの相談を受けて、利用者の希望に添った計画を作成した上で、利用者の了承を得るとともにサービス事業者との連絡調整も行います。
- 介護の相談やサービス内容の変更についても、担当の居宅介護支援専門員が利用者の立場に立って対応します。
訪問介護
利用者の自宅において、利用者に対する身体の介護や居室の清掃、また食事作りなどの日常生活の援助を行います。
主なサービス内容
- 身体介護中心
入浴、食事、排せつのお世話、衣類やシーツの交換 など - 生活援助中心
住居の清掃、洗濯、買い物、食事の準備、調理 など - 通院等乗降介助
通院時などの乗車、降車や移動の介助
介護保険の対象とならない主なサービス内容
下記のような、利用者本人以外のためにすることや、日常生活上の家事の範囲を超えることなどは、サービスの対象外です。
- 本人以外の家族のための家事
- ペットの世話
- 草むしりや花の手入れ
- 洗車
- 来客の対応 など
同居家族がいる場合における生活援助の利用条件
生活援助は原則として、同居家族のいらっしゃる方には提供できません。ただし、ご家族等が障がいや疾病等の理由、またその他やむを得ない理由により家事が困難な場合は、利用が可能な場合もありますので、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)にご相談ください。
詳細については「厚生労働省老健局 同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助の取り扱いについて(外部リンク)」をご参照ください。
(介護予防)訪問看護
医師の指示に基づき、利用者の自宅において看護師が療養上の世話や診療の補助を行います。
(介護予防)訪問リハビリテーション
医師の指示に基づき、理学療法士や作業療法士、または言語聴覚士などが、利用者の自宅において歩行訓練などのリハビリテーションを行います。
(介護予防)訪間入浴介護
利用者の自宅に浴槽を持ち込んで、介護士と看護師が入浴のサービスを行います。
(介護予防)居宅療養管理指導
自宅で療養していて、病院へ行くのが難しい方のところに、医師や歯科医師、または薬剤師などが訪問して療養上の管理や指導を行います。
通所介護(デイサービス)
利用者が送迎バスなどでデイサービスセンターなどに通い、入浴や食事などのサービスまたは生活行為向上のためのサービスを日帰りで利用することができます。
(介護予防)通所リハビリテーション(デイケア)
利用者が送迎バスなどで介護老人保健施設などに通い、心身の機能の維持回復に必要なリハビリテーションや入浴、また食事などのサービスなどを利用することができます。
(介護予防)短期入所生活介護(ショートステイ)
介護老人福祉施設などに短期間入所し、入浴や排泄、または食事など日常生活上の世話や、機能訓練などのサービスを利用することができます。
(介護予防)短期入所療養介護
介護老人保健施設や、介護医療院に短期間入所し、機能訓練を重視したサービスを利用することができます。
(介護予防)福祉用具の貸与
日常生活の自立を助けるための福祉用具を借りることができます。用具は車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトなどが対象となります。ただし、軽度者(要支援1・要支援2・要介護1の方)には一部利用制限があります。
※平成19年4月から、軽度者(要支援1・要支援2・要介護1の方)への車椅子や特殊寝台等の貸与を認める条件が緩和されました。
適切なアセスメントを経て、医師の医学的な所見とケアマネジャーの居宅支援計画から、福祉用具貸与が特に必要であると判断できる場合で、市町村が書面で確認することで貸与が認められることになります。細かな条件に該当するかについては、詳しい審査が必要になりますのでケアマネジャーに相談してください。
※令和6年度から、一部の福祉用具(固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、歩行補助つえ(松葉づえを除く単点つえおよび多点つえ))について、貸与と購入のいずれかを選択できるようになりました。
(介護予防)福祉用具の購入費の支給
貸与になじまない福祉用具を購入した際、いったん全額を支払ったあとに支給申請していただきます。限度額は100,000円までで、そのうち9割から7割が支給対象となります。腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、排せつ予測支援機器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分などが対象となります。
また、令和6年度からは、新たに固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、歩行補助つえ(松葉づえを除く単点つえおよび多点つえ)について、貸与と購入のいずれかを選択できるようになりました。
支給を希望する方は、事前にケアマネジャーまたは地域包括支援センターに相談してください。
(介護予防)住宅改修費の支給
利用者の自宅を改修した際、いったん全額を支払ったあと、または1割分から3割分を支払ったあとに、事業所が利用者の委任を受けて残り9割分から7割分を申請していただきます。限度額は200,000円までで、そのうち9割から7割が支給対象となります。
手すりの取り付け、床段差の解消、滑り防止などの床材の変更、引き戸などへの扉の取り替え、洋式便器への便器の取り替えなどが対象となります。
支給を希望する方は、事前にケアマネジャーまたは地域包括支援センターに相談してください。
(介護予防)特定施設入所者生活介護
有料老人ホーム等に入居して、施設の職員から入浴、排泄、食事、機能訓練などのサービスを利用することができます。
利用者と施設の個別契約に基づいて入居することになりますので、申し込みや利用料金などのお問い合わせは直接施設に行ってください。
施設サービス
- 介護老人福祉施設
介護老人福祉施設に入所して、入浴、排泄、食事、機能訓練などのサービスを利用することができます。 - 介護老人保健施設
病状の安定している利用者が、介護老人保健施設に入所して、医学的管理下において日常生活上のサービスを利用することができます。 - 介護医療院
主に長期療養が必要な利用者が、介護医療院に入所して、医学的管理下において介護や医療、また日常生活上のサービスを一体的に利用することができます。
※施設サービスは、「要介護者と認定された方」が利用できます。また、施設サービスを利用している間は、施設以外のサービスを利用することはできません。
※利用者と施設の個別契約に基づいて入居することになりますので、申し込みや利用料金などのお問合せは直接施設に行ってください。
地域密着型サービス
平成18年4月の制度改正により、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で生活を継続するようにするため、身近な市町村で提供されるのが適当なサービス類型として創設されました。狛江市の地域密着型サービスは、原則として市内の被保険者のみが利用できます。
地域密着型サービスの種類
現在狛江市では以下の5種類のサービスを提供しています。
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(休止中)
高齢者が、ご自宅で日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護を組合せて、定期巡回や随時の対応などのサービスを利用することができます。 - 夜間対応型訪問介護(休止中)
高齢者が、ご自宅で夜間帯に、排泄介助などのサービスを利用することができます。 - 地域密着型通所介護
利用定員が、18人以下の小規模な通所介護事業所です。
平成28年4月1日から、地域密着型サービスに移行することになりました。 - (介護予防)認知症対応型通所介護
認知症の高齢者が、デイサービスを行う施設などに通い、日常生活上の世話や機能訓練などのサービスを利用することができます。 - (介護予防)認知症対応型共同生活介護(認知症グループホーム)
認知症の高齢者が共同生活をする住居で、日常生活上の世話や機能訓練などのサービスを利用することができます。
地域密着型サービスの対象となる方
地域密着型サービスは、生活圏域に密着したサービスとして位置づけられているため、ご利用できるのは原則として以下の要件を満たす方に限られます。
- 狛江市民であること
- 要介護(予防の場合は要支援)認定を受けていること(被保険者であること)
地域密着型サービスの指定
居宅介護支援の指定権限の委譲に伴い、地域密着型サービスの指定に関する事項についても、「事業者指定について」のページに移動することになりました。
詳細は、「事業者指定について」のページでご確認ください。
高額介護(予防)サービス費
介護保険サービスを利用した方の、1か月間に支払った利用者負担額が一定の上限を超えたときは、高額介護(予防)サービス費として、超えた分が申請により払い戻されます。ただし、施設利用に伴う食費、居住費等対象にならないものもあります。
該当する可能性のある方には、お知らせと申請書をお送りします。一度申請をすれば口座が登録され、以降該当するごとに支給されます。
1カ月の負担限度額
| 所得区分 | 利用者負担上限額 |
|---|---|
|
課税所得690万円以上の方 |
世帯 140,100円 |
|
課税所得380万円以上690万円未満の方 |
世帯 93,000円 |
|
住民税課税世帯で課税所得380万円未満の方 |
世帯 44,400円 |
|
・世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者の方 ・世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額から年金収入にかかる所得金額を控除した額と課税年金収入額の合計が《80万9,000円》以下の方等 |
世帯 24,600円 |
|
生活保護受給者の方等 |
個人 15,000円 |
※《 》内の金額は、令和7年7月までは80万円となります。
特定入所者介護(予防)サービス費
介護保険の施設を利用する方のうち、低所得(世帯全員が住民税非課税)の方に対しては施設利用が困難にならないように、食費と居住費(滞在費)に負担限度額が設けられています。
助成を希望する方は、施設に入所またはショートステイを利用する際に高齢障がい課の窓口に申請してください。
対象となる方
- 次の施設へ入所する方
介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護医療院 - ショートステイを利用する方
(介護予防)短期入所生活介護…介護老人福祉施設等利用
(介護予防)短期入所療養介護…介護老人保健施設、介護医療院利用
要件
- 所得要件
住民税が非課税世帯の方 - 資産要件
第1号被保険者の方(65歳以上の方):下記表をご参照ください。
第2号被保険者の方(40歳から64歳までの方):預貯金等の資産が単身1,000万円、夫婦2,000万円以下の方
1日あたりの負担限度額(令和7年8月から)
| 利用者負担段階 | 預貯金等の 資産の状況 |
食費の 負担限度額 |
居住費(滞在費)の 負担限度額 |
|
|---|---|---|---|---|
|
第1段階
|
単身:1,000万円以下 ※生活保護受給者の方等の要件はありません。 |
300円 |
従来型個室 |
550円 |
|
多床室 |
0円 |
|||
|
ユニット型個室 |
880円 |
|||
|
ユニット型個室的多床室 |
550円 |
|||
|
第2段階 |
単身:650万円以下 |
390円 |
従来型個室 |
550円 |
|
多床室 |
430円 |
|||
|
ユニット型個室 |
880円 |
|||
|
ユニット型個室的多床室 |
550円 |
|||
|
第3段階1 |
単身:550万円以下 |
650円 |
従来型個室 |
1,370円 |
|
多床室 |
430円 |
|||
|
ユニット型個室 |
1,370円 |
|||
|
ユニット型個室的多床室 |
1,370円 |
|||
|
第3段階2 |
単身:500万円以下 |
1,360円 |
従来型個室 |
1,370円 |
|
多床室 |
430円 |
|||
|
ユニット型個室 |
1,370円 |
|||
|
ユニット型個室的多床室 |
1,370円 |
|||
※( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
※【 】内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の額です。
※《 》内の金額は、令和7年7月までは80万円となります。
※住民票上世帯が異なる(世帯分離している)配偶者(婚姻届を提出していない事実婚も含む。DV防止法における配偶者からの暴力を受けた場合や行方不明の場合等は対象外)の所得も判断材料とします。
※【預貯金等に含まれるもの】資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なもの。
※適用対象外となった場合でも、世帯員の転出や資産の変更などにより状況が変わった場合は、その時点で高齢障がい課の窓口に申請してください。
※住民税課税世帯における食費・居住費(滞在費)の特例減免措置について
住民税が課税されている世帯の方で、次の要件のすべてに該当する方は、食費または居住費(滞在費)のいずれか、あるいは両方について利用者負担第3段階2の負担軽減を受けることができますので、該当する方は高齢障がい課窓口にご相談ください。
- 住民税課税者がいる世帯で、その属する世帯の構成員の数が2人以上であること(別世帯の配偶者がいる場合を含む)。
- 世帯員が介護保険施設に入所し、利用者負担段階の第4段階の「居住費(滞在費)」または「食費」の負担を行うこと(ショートステイは本制度の対象外です)。
- 世帯の年間収入から、施設の利用者負担(介護サービス費の自己負担+居住費(滞在費)+食費の年額合計)を除いた額が、年80万9,000円以下となること。
- 世帯の預貯金など(有価証券を含む)の額が、450万円以下であること。
- 日常生活に供する資産(自宅の土地・家屋など)以外の活用できる資産がないこと。
- 介護保険料を滞納していないこと。
市独自のサービス
社会福祉法人による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度
市内の社会福祉法人(狛江市社会福祉協議会(あいとぴあ)、こまえ正吉苑、こまえ正吉苑二番館、こまえ苑)が提供している介護保険サービスを利用していて、次に該当する方は、サービス利用料(利用者負担分)の減額が受けられます。
対象となる方で軽減制度の利用を希望する方は、高齢障がい課の窓口に申請してください。
対象者
次のいずれにも該当する方
- 世帯の年間収入が基準の収入額(ひとり世帯の場合は150万円、世帯構成員が1人増えるごとに50万円を加えた額)以下であること
- 世帯の預貯金額が基準預貯金額(ひとり世帯の場合は350万円、世帯構成員が1人増えるごとに100万円を加えた額)以下であること
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
- 介護保険料を滞納していないこと
サービス提供事業所 軽減対象サービス
| サービス提供事業所 | 軽減対象サービス |
|---|---|
|
こまえ正吉苑 |
訪問介護・通所介護・認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護・ |
|
こまえ正吉苑二番館 |
短期入所生活介護・介護福祉施設サービス |
|
あいとぴあ |
訪問介護 |
|
こまえ苑 |
訪問介護・通所介護・認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護・ |
軽減額:介護保険サービス自己負担額のうち25%
事業所の皆様へのお願い
狛江市では、社会福祉法人による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度のほか、介護保険サービス事業者と市が介護保険サービスの利用者負担額を軽減する制度を利用することができます。
この制度は、介護保険サービスの提供を行う介護保険サービス事業者が、その社会的な役割に鑑み、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的としており、軽減額の半額は事業者様にご負担いただく制度となっています。
制度の趣旨に賛同いただける事業者様は、ぜひ当事業へのご協力をお願いいたします。本事業にご協力いただける場合は、事前に「申出書」を東京都と狛江市にご提出ください。
詳細については、「東京都福祉保健局 生計困難者等に対する負担軽減事業」(外部リンク)をご参照ください。
税金の申告に利用する認定書などの交付
障害者控除対象者認定書の交付
確定申告で所得税および住民税(市民税・都民税)の障害者控除を受ける場合、身体障害者手帳などの提示が必要となりますが、身体障害者手帳などの交付を受けていない方でも障害者または特別障害者に準ずると認められた方は障害者控除の対象となります。
対象者には障害者控除対象者認定書を発行します。
対象者
次のいずれにも該当する方
- 65歳以上である方
- 障害者控除の対象となる年の12月31日時点で要介護1以上の認定を受けている方
- 介護保険主治医意見書に記載された障害高齢者及び認知症高齢者の日常生活自立度が判定基準を満たしている方
判定基準
要介護1以上の方
- 介護保険主治医意見書の障害高齢者の日常生活自立度がB1以上の方:障害者
- 介護保険主治医意見書の認知症高齢者の日常生活自立度がIIA以上の方:障害者
要介護3以上の方
- 介護保険主治医意見書の障害高齢者の日常生活自立度がB2以上の方:特別障害者
- 介護保険主治医意見書の認知症高齢者の日常生活自立度がIIIA以上の方:特別障害者
所得金額からの控除額
| 区分 | 障害者控除 | 特別障害者控除 |
|---|---|---|
|
所得税 |
27万円 |
40万円 |
|
市民税・都民税 |
26万円 |
30万円 |
申請に必要な書類等
対象者の介護保険被保険者証
※対象者と申請者が異なる場合には、申請者のご本人とわかる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)も必要です。
※郵送での申請もできます。
〒201-8585
狛江市和泉本町1-1-5 狛江市福祉保健部高齢障がい課介護保険係
おむつ代の医療費控除に必要な確認書の交付
本人、または扶養者がおむつ代を医療費控除として申告する場合、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。
ただし、次の対象者に該当する方は、市が交付する「確認書」でも申告することができます。
対象者
医療費控除の対象となる年の12月31日時点で要介護1以上の認定を受けている方で、介護認定の審査にあたり作成された主治医意見書において次のすべてのことが確認できる方
- 障がい高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1からC2であること
- 失禁への対応としてカテーテルを使用していること、または尿失禁が現在あるもしくは今後発生の可能性の高い状態であること
※令和5年以前分のおむつ代について、医療費控除を初めて申告する方(1年目)は、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。
※令和6年以降分のおむつ代については、申告が1年目の方は6か月以上継続して要介護認定期間が継続していること、2年目以降の方は13か月以上の要介護認定期間があること等の要件もあります。要件に該当されない方は、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。
申請に必要な書類等
対象者の介護保険被保険者証
※対象者と申請者が異なる場合には、申請者のご本人と分かる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)も必要です。
※郵送での申請もできます。
〒201-8585
狛江市和泉本町1-1-5 狛江市福祉保健部高齢障がい課介護保険係
介護保険の保険料
同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助の取り扱いについて(外部リンク)
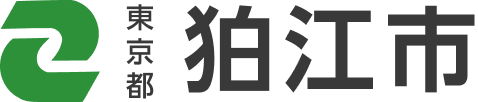
 印刷
印刷
 戻る
戻る
 ページの先頭
ページの先頭