介護保険に関する申請書類
介護保険に関する各種申請書などについて、ご説明します。
- (1)介護保険要介護認定・要支援認定申請書
- (2)事故報告連絡票・事故報告書
- (3)介護保険負担限度額認定申請書
- (4)過誤申立書
- (5)居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書
- (6)介護サービス提供に係る情報提供申請書兼同意書
- (7)介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
- (8)介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
- (9)軽度者に対する福祉用具貸与にかかる確認依頼書(介護保険の保険者確認書)
- (10)社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額軽減対象確認申請書
(1)介護保険要介護認定・要支援認定申請書
介護保険のサービスを利用するには、要介護(要支援)認定を受ける必要があります。申請書に必要事項を記入のうえ、介護保険被保険者証をそえて市役所または地域包括支援センターに提出してください。
申請書が提出されると、認定調査員がご自宅(入院されている方は病院)を訪問して、心身の状況などの調査を行うとともに、市がかかりつけの医師に心身の状況について意見書の作成を依頼します。この認定調査とかかりつけ医の意見書により、どの程度の介護が必要なのかについてコンピューターで推計して、医療・保健・福祉の専門職の委員で構成する介護認定審査会により要介護認定を行います。認定の区分には、要支援1・2(要支援状態)、要介護1から5(要介護状態)、自立(非該当)の8段階の区分があり、認定されると結果通知及び介護保険被保険者証が送付されます。
認定の結果が出たのちにサービスを利用するには、要支援1・2の方は地域包括支援センターまたは介護予防支援事業者へ、また要介護1から5の方はお近くの居宅介護支援事業者へ連絡をとり、介護(予防)サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。この計画に基づいて、具体的にサービスの種類や事業者、また利用する日時などが決められます。
(2)事故報告連絡票・事故報告書
介護保険指定事業者が利用者に対して提供した介護サービスにより事故が発生した場合は、事業者が保険者(狛江市)、利用者の家族、居宅介護支援事業者に対して報告を行うこととされています。具体的な提出書類や流れについては以下のとおりです。
報告手順および様式の規定
- 第一報:保険者(狛江市)、利用者の家族及び居宅介護支援事業者へ電話にて報告し、併せて「事故報告連絡票」を保険者(狛江市)に提出
- 事故終結後:保険者(狛江市)、居宅介護支援事業者、利用者が所在する市区町村(住所地特例者を含む)へ「事故報告書」にて終結までの経緯を報告
なお、長期化する場合は途中経過を適宜保険者(狛江市)へ報告してください。
(3)介護保険負担限度額認定申請書
介護保険の施設を利用する方のうち、低所得(世帯全員が市民税非課税)の方に対しては施設利用が困難にならないように、食費と居住費(滞在費)に負担限度額が設けられています。助成を希望する方は、施設に入所またはショートステイを利用する際に、高齢障がい課の窓口に申請してください。
対象となる方
1.次の施設への入所者
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 地域密着型介護老人福祉施設
2.ショートステイ利用者
- (介護予防)短期入所生活介護
介護老人福祉施設へのショートステイ - (介護予防)短期入所療養介護
介護老人保健施設、介護医療院へのショートステイ
※対象となる方の要件等の詳細は、介護保険サービスのページをご覧ください。
(4)過誤申立書
介護サービス事業者が、請求額などの誤りなどにより介護報酬の請求取消しを希望するときは、過誤申立書を提出する必要があります。毎月20から25日に東京都国民健康保険団体連合会に過誤申立をするため、原則20日までに提出していただきます。
郵送または窓口で受付します。
(5)居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書
在宅で介護サービスを利用する場合、介護支援専門員(ケアマネジャー)に介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらい、この計画に基づいてサービスを利用します。サービスを利用するには保険者(狛江市)に対する届出が必要です。
(6)介護サービス提供に係る情報提供申請書兼同意書
介護サービスを行うために、要介護認定調査票や主治医意見書に関する情報が必要なときは、ご本人の同意に基づきケアマネジャーや介護保険事業者に対して、要介護認定の情報を提供します。提供された情報は、介護サービス提供の目的以外には使用しないこと、第三者への提供および複写をしないこと、保管管理を厳格に行うことが義務付けられています。
※郵送を希望される場合は、返信用封筒(110円切手を貼ったもの)を添付してください。
※事業者向けの申請書のため、市民の方が申請することはありません。
(7)介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
入浴や排泄のために用いる、貸与になじまない福祉用具(特定福祉用具)の購入費に対して助成を行います。申請により、購入した費用の9割から7割に相当する額が支給されます。ただし、年度ごとに10万円(×9割から7割)までの支給限度額があります。
※令和6年度から、一部の福祉用具について、貸与と購入のいずれかを選択することができるようになりました。
支給対象となる用具
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 排せつ予測支援機器
- 入浴補助具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
貸与と購入のいずれかを選択することができる用具
- 固定用スロープ
- 歩行器(歩行車を除く)
- 歩行補助つえ(松葉づえを除く単点つえおよび多点つえ)
申請書類
- 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
- 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費請求書
- 領収書
- 購入した福祉用具のカタログ(コピー可)
- 特定福祉用具販売計画書(福祉用具サービス計画書)の写し
※福祉用具販売の指定を受けた事業者からの購入のみが対象になります。
(8)介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
生活しやすい環境を作るための住宅の改修費を助成します。申請により、改修した費用の9割から7割に相当する額が支給されます。ただし、同一の住宅につき一人20万円(×9割から7割)までの支給限度額があります。また、事前の申請が必要です。
支給対象となる工事
- 手すり取付け
- 段差解消
- 床または通路面の材料変更
- 引き戸などへの扉の取替え
- 便器の取替えに伴う改修
※対象になるか不明な場合は、事前にご相談ください。
申請書類
原則、事前申請
- 介護保険住宅改修費事前申請書(本人払用)
- 介護保険住宅改修費事前申請書(受領委任払用)
- 住宅改修が必要な理由書
- 住宅改修の承諾書
- 介護保険住宅改修費支給申請書(本人払用)兼完了届出書
- 介護保険住宅改修費支給申請書(受領委任払用)兼完了届出書
- 介護保険住宅改修費請求書
手続きの流れ
事前申請 → 着工許可 → 工事・改修 → 完了報告 → 支給
※現在入院中で退院後に向け改修する場合は、事前にご相談ください。
(9)軽度者に対する福祉用具貸与にかかる確認依頼書(介護保険の保険者確認書)
※この確認書は本人ではなくケアマネジャーが提出するものです。
平成18年度の介護保険制度の改正により、要支援と軽度の要介護者(要支援1から要介護1)の福祉用具のレンタルが一部できなくなりましたが、平成19年4月に基準が一部改正され、新たな判断基準により一定の身体状況にある方については、手続きを行えば福祉用具の貸与が可能になりました。
事務手続きについて
新たに軽度者に福祉用具貸与を行う場合は、次の全ての条件を満たす必要があります。
- 対象者の状態が、基準に該当することが医師の医学的な所見に基づき判断されていること
- サービス担当者会議などを通じた適切なケアマネジメントにより、福祉用具貸与が特に必要であることが判断されていること
- 市町村が書面など確実な方法で確認することにより可否を判断すること
軽度者に福祉用具貸与を行う場合は、担当ケアマネジャーの責任において医師の意見などの聴取およびサービス担当者会議の開催を行い、「軽度者に対する福祉用具貸与にかかる確認依頼書(介護保険の保険者確認書)」に必要事項を記入の上、サービスを提供する月の末日までに高齢障がい課介護保険係へ提出してください。
確認依頼書は、ケアプランを見直すごとに提出してください。確認依頼書をもとに、市で可否を判定して写しを返却しますので、ケアプランと一緒に保管してください。
判定までの流れ
アセスメント → 医師の意見書聴取及びサービス担当者会議 → 確認依頼書の提出 → 可否の判定 → 確認依頼書の写し(決定済)
(10)社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額軽減対象確認申請書
市内の(申出をした)社会福祉法人が提供している、介護保険サービスを利用していて収入などの条件に該当する方は、申請することによりサービス利用料(自己負担分)が減額されます。
申請に必要なもの
- 生計困難者に対する利用者負担軽減対象確認申請書(第2号様式)
- 収入および預貯金申告書(第3号様式)
- 収入および預貯金を証明できる書類(預金通帳、年金等の決定通知書等)
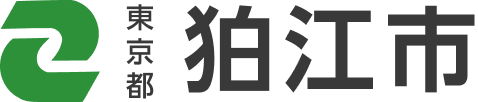
 印刷
印刷
 戻る
戻る
 ページの先頭
ページの先頭