令和7年度第1回狛江市人権尊重推進会議会議録(令和7年5月30日開催)
|
1 日時 |
令和7年5月30日(金曜日)午後6時30分から午後8時10分まで |
|
2 場所 |
狛江市防災センター301会議室 |
|
3 出席者 |
委員 東 裕 若柳 善朗 大仁田 妙子 宮内 友紀 樋口 ユミ 大澤 遥香 伊東 達夫 重国 毅 坂田 亮子 事務局:政策室長 杉田 篤哉 子ども若者政策課長 山口 敦史 政策室市民協働推進担当 白岩 亮 髙橋 健太朗 |
|
4 欠席者 |
委員 |
|
5 議事 |
(1)(仮称)子ども条例について【報告事項】 (2)今年度の進め方について【審議事項】 (3)狛江市第4次基本構想 後期基本計画について【報告事項】 (4)外国籍市民が住みやすいまちづくりに関する答申について【審議事項】 (5)法人向けアンケート調査について【審議事項】 (6)その他 |
| 6 配布資料 |
|
| 7 議事概要 | |
|
(1)(仮称)子ども条例について -資料1を基に子ども若者政策課長より説明- ・(仮称)子ども条例(案)の制定に向けて令和5年度に市長より制定に関する諮問を子ども・若者・子育て会議が受け、昨年度は骨子の検討を行った。また、骨子の検討と並行して小学生向け、中高生向け、大人向けそれぞれのリーフレット作成、配布等を行った。 ・昨年度はWebアンケートを実施し、小学生、中高生から543件、18歳以上の大人から798件の回答をいただいた。 ・アンケートでは拾いきれない子どもたちの生の声を聴くため、子どもたちの居場所にアウトリーチをかけるヒアリング事業を昨年度実施した。 ・今年度は、条例制定に当たっての論点整理や子どもの意見を聴く前の土壌づくり、意見聴取等の手法、逐条解説について審議を行っている。 ・現時点での(仮称)子ども条例(案)は、第1章から第6章まで全22条の構成となっている。施行日は令和8年4月1日を予定しており、議会への上程は令和7年第4回定例会を予定している。 ・条例制定の背景、理念、決意等を述べるところが一般的に前文となっているが、この全文に入る「子どものメッセージ」については、「ワークショップにおいて検討」としており、今後、子ども向け、大人向けのワークショップを開催し感想や意見を反映していく予定である。 ・ワークショップは全4回開催予定であり、第1回は大人向け、第2回、第3回は子ども(小、中、高校生向け)、第4回は子ども、大人合同での実施を予定している。その後、9月にパブリックコメント、フォーラム、市民説明会を開催する予定である。 ・条例制定後の次年度以降は、子どもにも参加していただき、条例の中身を紹介するリーフレットの作成や、条例について広く市民に知っていただくための啓発イベント等を行う予定である。 (副会長)資料1の8ページ1行目のみ、ですます調ではなくである調になっている。 (委員)なぜ狛江市で子ども条例を制定することになったのか。この分野は狛江市としてもまだまだ課題があるということか。 (子ども若者政策課長)資料1の前文にもあるように、子どもは大人と等しく権利の主体であるという点を重視していることや、こども基本法の中で、子ども関係の施策を進める際は子どもの意見を聴いた上で進めなさいと規定されていることもある。こども基本法制定前も各課で計画や事業の中では実践していたが、条例で規定して取り組んでいく必要があると考えている。 (会長)資料1の2ページ、第1段落に「日本国憲法」の記載があるが、第3段落では「子どもの権利条約やこども基本法の理念に基づき」とあり、日本国憲法の記載がないがこれは何か理由があるか。また、前文の下から3行目に「子どもには、まずは自分には大人と等しい権利があることを知ってほしい」とあるが、「大人と等しい権利がある」ということは言えるのかどうか。権利の性質によって違うと思うため、どういった議論がされたのか教えていただきたい。続いて第1条の1行目、「子どもの権利が大人と等しく保障されるべきもの」という部分も誤解を生む表現ではないかと思う。子どもに保障される権利と大人に保障される権利の種類は違いがあるので、その種類の違いがあった上で子どもの権利が同様に保障されるということかと思う。また、3ページ目の第3条冒頭に「子どもの権利条約及びこども基本法に基づき」とあるが、ここでも日本国憲法に言及されていないが何か理由があるか。また、それに続く条文として「子どもは権利の主体として大人と等しい権利」という表現があるが、こちらも権利の性質によって保障される権利は違うと思うため、先ほどと同様に誤解を招くのではないかと思う。次に、第3条の3行目、「子どもの権利条約で定める4つの一般原則」とあるが、条文の中で何が4つの一般原則であるか触れられていないため、この4つの一般原則を明確に言及した方がよいのではないか。読み手にとってこの4つの一般原則が不明となってしまう。続いて4ページの第8条に「子どもが大人と対等な権利の主体」とあるが、この部分も誤解を招く可能性があるのではないか。 (子ども若者政策課長)日本国憲法の表記については、前文で明記しているとおり規定されていると考えているので、その他の条文にも明記するかどうか、文言整理の中で再検討させていただく。4つの一般原則については、子ども・若者・子育て会議の中でも初めのうちは明記していたが、引用したものをそのまま条例に明記するのはどうかというところで一度削っているが、逐条解説の中では明記している。現時点では条例はシンプルにして逐条解説の内容を厚く記載しているという状況であるが、いただいた御意見も踏まえて今後修正するか検討する。権利の性質については、逐条解説の中でどのようにフォローしていくかまだまだ議論している最中のため、いただいた御意見を参考にしていきたいと思う。 (会長)小学校高学年から高校生までの子どもにもこの条文を読んでもらう想定であると思うが、その際に逐条解説まで読まないと意味が把握できないということであると少々問題があるかなと思う。4つの一般原則についても箇条書きで書けば1、2行で済むことだと思われてしまうかもしれないため、そういった点を十分御配慮いただいた方がよいと思う。 (委員)ワークショップについて、どのように子どもに募集をかけているか。 (子ども若者政策課長)各学校へのチラシ配布と広報こまえで募集をしている。もし集りが悪ければ児童館等で直接お声掛けしていただこうと考えている。 (委員)なるべく地域や年齢が偏らないように話を聴いていただければと思う。
(2)今年度の進め方について -資料2を基に事務局より説明- ・会議の所掌事項、委員構成、年間の会議スケジュール及び内容等について説明。 (委員)法人向けアンケート調査以外で、今年度、議論してみたいテーマや、来年度実施してみたい意識調査等があればという話だが、いつまでに提出すればよいか。 (事務局)2週間程度を目安に御提出いただきたい。
(3)狛江市第4次基本構想 後期基本計画について -資料3を基に事務局より説明- ・狛江市第4次基本構想後期基本計画の人権に関する部分の説明 (委員)本計画に書かれている内容はよいと思うが、この計画に書いていることと実際に行われていることが違う場合はどこに相談すればよいか。資料3の8ページに「平和に対する意識啓発」とあるが、狛江市が作成した空襲に関する紙芝居を駅前のほこみちステージで実施しようとしたところ、一般の市民団体が実施するものなので7,000円の費用が発生するということであった。本計画に「平和に対する意識啓発」とあるのであれば費用を無償とする等があってもよいと思う。 (事務局)今のお話はあくまで市民団体の方が実施する事業であり、市の後援事業ではあるが、ほこみちステージの料金体系に則り費用が発生している。
(4)外国籍市民が住みやすいまちづくりに関する答申について -資料4及び資料5を基に事務局より説明- (副会長)「やさしいにほんご」と「日本語」の表記が混ざっているが問題ないか。 (委員)「やさしいにほんご」のセオリーとして難しい感じを省くという意味で平仮名表記になっていると思う。 (委員)「やさしいにほんご」という一つのジャンルとして、漢字の「日本語」は一般的な日本語と考えればよろしいかと思う。 (委員)調査報告書では「やさしいにほんご」という表記になっている。 (会長)答申も調査報告書も「やさしいにほんご」は鍵括弧を付ける表記で統一していただきたい。 (事務局)「やさしいにほんご」に統一する。 (会長)資料4の2ページに「5ヶ国語」という表記があるが、「5言語」に統一していただきたい。 (副会長)資料4の5ページ「4 今後の課題について」の部分は、第一段落、第二段落で指摘が2つあり、第三段落で意見が1つという構成になっているが、この表記だと意見のあった部分だけ「こうした意見を真摯に受け止め」と読めてしまうことから、「こうした意見を真摯に受け止め」は改行し、「こうした指摘や意見を真摯に受け止め」として指摘2つ、意見1つすべてにかかるようにしていただきたい。 (事務局)そのように修正させていただく。 (委員)感想になるが、日本人も生活が苦しくなっている中で外国籍の方に対する風当たりはより強くなっていると感じる。その中で今回の実態調査は、不十分な点はあったとしても一定段階の外国籍の方が持つ課題を明らかにしたという点で意義があることだと思う。答申の最後の部分にあるように、実態把握の方法についての見直しや継続的な調査実施が引き続き大切だと思う。
(5)法人向けアンケート調査について -資料6及び参考資料1を基に事務局より説明- ・近年、不当な差別やハラスメント等、企業活動において発生する様々な「人権問題」が社会的に注目を集めていることから、来年度に法人向けアンケート調査の実施を検討している。 ・市ではこれまで、法人向けの人権に関するアンケート調査を実施したことがなく、法人の採用やハラスメント等に対する体制や人権意識について把握できていないのが現状。 ・調査結果を市の施策に反映することはもちろんだが、調査を実施すること自体が法人への意識付けにも繋がる。 ・概要案として、調査地域は市内全域、対象は市に法人登録のある法人、設問数は20~25問程度、調査方法は郵送配布、郵送又はWeb 回答、調査期間は令和8年6月~7月頃。 ・来年度、法人向けアンケートを実施するということは決定ではないため、今年度の会議の中で議論してみたいテーマや、来年度実施してみたい調査等あれば御意見を頂戴したい。 (会長)まず法人向けアンケートを実施する方向で考えてよいか。また、今年度中に議論してみたいテーマや来年度実施したい調査等あれば御意見を頂戴したい。 (委員)ビジネスと人権という問題は気にはなっていたが深く考えたことはなかったので、こういった機会があるのはよいと思う。樋口委員はこういった分野が専門ではなかったか。 (委員)そうである。組織のハラスメント対策が専門なので、法人向けアンケートを実施していただければ意識啓発にもなると思う。 (委員)アンケートの対象は、法人の経営側、雇われている側どちら向けのアンケートになるか。 (事務局)経営側を想定している。 (委員)法人向けだとフリーランスの方や土建の一人親方のような方が該当しない。形としては個人事業主だが、今回の法人には当てはまらない方も行政として丁寧に見て必要な支援をしなくてはいけない対象であると思う。そういった方々の意見を汲み上げていかないと十分な対応にならない。 (副会長)法人がフリーランスの方等の人材を活用しているか、正規、非正規が何人ぐらいいるか等の実態と併せて設問とすれば良いのではないか。フリーランスの方々だけにアンケートするのはかなり難しいと思う。 (委員)同じアンケートでなくても両者から意見を伺う方法を検討できればと思う。 (委員)事務局の言う「法人アンケート」という言葉と「ビジネスと人権」は中身としてそこまで違わないかもしれないが、若干ニュアンスが違うのかなと感じる。ビジネスと人権の方が対象範囲が広いと思う。それに対して法人や企業というのは組織の内部的な関係に関わってくるのかなと思う。 (副会長)ビジネスというと誰を対象にしているか分かりづらいところだが、市に登録している法人を対象にするというのは意味合いとしては同じだと思う。ビジネスというと個人事業主も入ると思うが、アンケートをしてみて問題があるということであれば個人事業主等にフォーカスしてアンケートをとることも考えていいと思う。 (会長)「法人」と「企業」という言葉だが、企業はいわゆる会社と言われるものであり、法人と言うと少し広くなり一般社団法人や財団法人も含まれる。ここで言う「法人」は「会社」いわゆる「企業」に限るという理解でよろしいか。 (事務局)今回、資料として出させていただいた資料にある約2,100社というのは、有限会社、株式会社、宗教法人、一般社団法人、医療法人等の市に登録のある法人になる。中身がどの程度の規模の法人なのかという情報まではないが、一般的にイメージするところより小規模な法人が多いと想定しているため、アンケートがそぐわない可能性もあるかもしれないと思っている。 (会長)有限会社、株式会社等のいわゆる「会社」に絞れば一定の線引きができると思う。今回の「法人アンケート」の「法人」はそういった会社を指すという共通理解でよろしいか。 (委員)社会福祉法人も法人では比較的規模が大きいので入れてはどうか。 (委員)対象を広くした方が興味深い結果が出てくると思う。社会福祉協議会も対象とするかどうするかということもある。法人登録している法人とは別に、万単位でいると思われる個人事業主向けの全数調査は難しいと思うので、無作為抽出のような形で法人と2本立てで実施できれば立場の違う視点での結果が見えてよいのではないか。 (事務局)共通の部分もあると思うが、法人と個人事業主だと設問がだいぶ変わってくると思う。 (委員)一人で経営している方にも調査するということか。 (委員)そうである。個人事業主の方が仕事をしている中で個人の人権が守られた働き方ができているのかを調査できればと思う。例えば、食事の宅配サービスの企業の話で、個人事業主ではあるが、実態は大きな企業に雇われているケースがある。ではこの個人事業主の方に何かあった際に労災が保証されているのかということや、土木、建築等で働いている方の中で一人親方として働いている方の健康保険はどうなっているのか等の問題がある。 (事務局)個人事業主の方の情報は市で保有していないため、商工会等から情報を得ることができるか確認する。 (委員)先日、電気やガスの補助金を市で出していたかと思うが、あれは個人事業主の方が多く受けているのではないか。 (事務局)確認する。 (委員)商工会や補助金の関係から情報を得ることができれば、全数調査の法人アンケートとは別に実施できると思う。 (事務局)そこで情報を得ることができれば対象にできると思う。設問をどうするかという課題はある。 (委員)経営者が答えるとなると意識付けがメインになるか。セクハラやパワハラの場合、経営者が答えるよりも働いている方が答えるものではないかと思う。 (事務局)大きな企業であれば総務の方等が答えると思うが、少人数の企業で経営者が回答するとなると仰る通り実態が返ってくるかはわからない。 (委員)せっかく実施するのであれば現状の実態を得て、結果を法人へフィードバックしていただきたい。 (副会長)先ほどお話があったが啓発という意味ではよいと思う。例えば、「ハラスメントに関する規則を定めていますか」という設問があれば、大きな企業であればあると思うが、もし規則等がない企業があれば作らなくてはいけないのかなと思っていただくだけでも意味があると思う。 (委員)参考資料1の他自治体の設問を見ると、セクハラ、パワハラ、モラハラ等あるが、その中にカスハラも入れると法人の中でのハラスメントに対する取組が見えてくるかもしれない。カスハラによって傷ついて退職される方も多いと思うので設問項目に入れるとよいのではないか。 (事務局)東京都でも今年度からカスタマー・ハラスメント防止条例を施行するなど、自治体だけでなく企業も問題意識を持っている分野だと思う。法人内部のことではないので、より実態に即した内容が返ってくると思う。 (委員)カスハラは受ける側がどう捉えるかにもよるので、法人が実際にどのように捉えているか分かると思うのでよいと思う。 (委員)カスハラに関して、どこまでが自分で対応すべきことか、どこからが上司に相談することなのか、警察に通報することなのかということを話し合っていただく研修会を先日実施した。 (委員)先ほど社会福祉法人もアンケートの対象に含めるとどうかという話をしたが、カスハラの部分が一番気になっている。民間企業であれば金銭的なことで解決できることもあり得ると思うが、社会福祉法人の場合は、利用者側が弱者で社会福祉法人が保護するという社会のセオリーに基づいて仕事をしている。その中で、職員がハラスメントを受けることもあるが、保護すべき利用者と職員の人権も守らなければいけないというバランスを法人の方がどのように考えているのか、こういったアンケートで見えてくるかもしれない。 (委員)そのように考えると、法人だけでなく労働組合のアンケートも欲しいところである。 (会長)あまり対象を拡大すると焦点がぼやけてしまう。本日の議論として法人向けアンケートを実施するということは皆さん賛成であり、法人の範囲をどこまでとするかということについては、営利を目的とする法人だけでなく、社会福祉法人等にも対象を広げた方がよさそうである。市で保有している法人の登録情報の中で法人の種別を簡単に分類していただき、その分類を基に対象とする法人を決めていければいいのではないか。また、アンケート結果から、具体的にハラスメントや不当な差別に対して法人内での制度がどのように整理されているか、どのような取組がされているか、人権に対してどのような意識を持っているか状況を見たいということなので、経営者の意識ということには限定されないと思う。企業としてどのような取組が現にあるかということを明らかにしていくということに絞ってはどうかと思う。また、現在は様々な種類のハラスメントがあるが、その種別を事務局でリストアップしていただき、各ハラスメントに対する制度的な取組が各法人等で実施されているかという設問にすることで、その中にカスハラに対する企業としての取組の有無も見えてくる。そういったことで本日、合意いただき次の具体的な設問項目や対象等の設定に進みたいと思う。 (委員)約2,100社への法人に対するアンケートは実施でよいと思う。それとは別に個人事業主の方や労働組合をどのように汲み上げていくのか。法人とは違うアプローチでビジネスと人権に関する狛江の実態を掴む方法がないのか探るべきである。 (事務局)法人向けの調査ついては今後、設問を練っていく。その他、法人以外の調査がどこまで可能かということは事務局で確認する。
3.その他 (事務局)次回会議日程について、会議室等調整し改めてメールで御連絡する。
-閉会- |
|
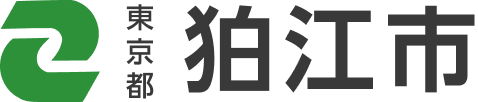
 印刷
印刷
 戻る
戻る
 ページの先頭
ページの先頭