|
(会長)
定刻となりましたので、ただいまから令和7年度第2回狛江市国民健康保険運営協議会を開会いたします。委員の皆様におかれましては、御多用中のところ本会に御出席をいただき、誠にありがとうございます。
(事務局)
では、事務局より本日の議事等について御報告いたします。本協議会は、対面とウェブ参加を併用して開催させていただきますので、あらかじめ御了承ください。
本日の会議につきましては、「狛江市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例」により、会議は原則として公開となっております。
なお、本日は傍聴の申し出はございません。
続きまして、本日の出席状況ですが、対面での出席が8名、ウェブによる出席が松岡委員、近藤委員、松浦委員、竹村委員、天野委員の5名、欠席は古市委員1名となっております。出席委員は全体の半数を上回っており、また狛江市国民健康保険条例第2条各号に定める委員のうち各1名に御出席いただいていることから、狛江市国民健康保険運営協議会規則第7条の規定を満たしており、本協議会は成立いたします。
次に、本日の会議でございますが、お手元の次第を御覧ください。
2議題(1)議題といたしましては1点でございます。
最後にその他として、本日予定している議題以外について、委員の皆様からの御質問や御要望などがございましたら、ここでのお取り扱いをお願いいたします。
最後に、当日配布資料として資料1―1、1-2をお手元の端末等に配布させていただいております。
お手元の資料に過不足はございませんでしょうか。
また、会議録作成システムの適切な運用のため、委員の皆様が発言する際には、必ず挙手のうえ会長からの指名を受けたのちに、発言するようにお願いいたします。
次に、狛江市国民健康保険運営協議会規則第12条に基づく会議録の署名委員につきましては、松岡委員と小野寺委員のお二人にお願いいたします。
それでは、議事を進めます。
2議題(1)審議事項①国民健康保険財政健全化計画の見直しについてです。
お手元の資料1―1「国保財政健全化計画の実施期間シミュレーション」及び1―2「各目標年次ごとの税率改定シミュレーション」について、事前の送付が間に合わず申し訳ございません。
資料の内容について御説明させていただきます。
資料1-1を御覧ください。
資料1-1は、現行の国保財政健全化計画において、令和14年度までに法定外繰入4.04億円を解消することとしている中、令和5年度までの進捗状況を踏まえ、「どのようにすれば法定外繰入を解消させることができるか」をグラフにて視覚的に表したものです。
表の1つ目が現行計画で想定している2か年ごとの税率改定年度に予定どおりの調定額が得られるように改定した場合の赤字解消の見込みを表したものです。令和5年度までに赤字額が2.8億円程度増加してしまっているため、現行計画通りに改定を行った場合、この増加分が最後まで残ってしまうことが懸念されます。
2つ目の表が令和5年度までの状況を踏まえ、令和14年度までに赤字解消をするためには調定額をどの程度確保しなければならないかという観点から作成したものです。
令和6年度以降の税率改定年度4回で6.85億円の赤字を解消する必要があるため、現行の3倍以上の調定額を確保する必要があり、税率の改定幅も相応に大きくなることが想定されます。
3つ目の表が1つ目の表において計画の終了年次を令和14年度としているところですが、終了年度をいったん考慮せず、現行計画どおりに進めていった場合に、いつ赤字が解消することになるのかをシミュレーションしたものです。調定額ベースでは令和29年度に解消する結果となっておりますが、国保の加入者数は年々減少しているため、国民健康保険税を納付する被保険者の総数が減少し、なお必要な調定額を得るためには、被保険者一人あたりの負担額は時間が経過するほどに増加していくことが予想されます。
4つ目の表が令和17年度までに解消することを目指した場合にどれくらいの調定額が必要となるかをシミュレーションしたものです。「令和17年度」という時期の根拠は、令和7年6月30日に開催された「東京都国民健康保険連携会議」において示された、東京都が全自治体において法定外繰入の解消を達成する目標年次として定めた年度です。
東京都国民健康保険連携会議とは、区市町村及び東京都国保連合会から成り、納付金等の算定や国民健康保険制度の運営方針等について関係団体において協議する会議体で東京都における国保運営方針について、保険者である区市町村と財政運営上の経営主体である東京都、そして審査支払機関である国保連とで年3回程度意見交換を行っているものです。令和17年度までには、5回の税率改定年度を含むこととなるため、令和14年度の赤字解消を目指す場合より、確保すべき調定額は低めとなっております。
続いて、資料1-2を御覧ください。
資料1-2は、資料1-1の各表で確保すべき調定額について、平成31年度から令和7年度の各年度の「当初賦課」の算定結果から各年度ごとの調定額の増減割合や被保険者数の減少割合、軽減対象となる低所得者の割合等を算出し、目標とする調定額に達するためには均等割額や所得割の税率をどう設定すべきなのかをシミュレーションしたものです。
御説明の前に付言させていただきますが、実際には各年度の「被保険者数」や「所得の内訳」、税制改正等による「賦課限度額や軽減判定所得の見直し」あるいは新型コロナウイルス感染症のような社会情勢の急激な変化等により、シミュレーション内容は大きく影響を受けることとなりますし、来年度から新設される「子ども子育て支援金制度」についても、全体像が明らかになっていないため考慮しておりません。あくまで、令和7年度までの実際の調定額から被保険者数や調定額等がどのような割合で推移していったか、ということを元にしたシミュレーションであることをあらかじめ御了承ください。
では改めて、資料の御説明をさせていただきます。
資料の見方についてですが、まずは「1.現行計画どおり」と記載した部分を御覧ください。この現行計画どおり、とは資料1-1でお示ししている1つ目の表のとおり、現行計画で想定している調定額を得ようとした場合の税率等を試算した結果になります。
令和6年度の部分は、実際に昨年度に改定を実施しているため、どの表においても同一ですが、医療分・支援分・介護分の各項目の均等割の金額と所得割の税率をお示ししていることに加え、「税額」という項目において、「所得300万円、40代の夫婦及び中学生・小学生の子ども2人という4人世帯」を「モデル世帯」としたときに、当該モデル世帯における年税額を表したものです。また、表の欄外に「合計」という項目を記載しておりますが、これは医療分・支援分・介護分の均等割額及び税率の合計値を表しております。
例えば、令和6年度の均等割額の合計は52,800円、合計税率は9.5%であり、同年度におけるモデル世帯の年税額は427,000円となります。
なお、税率改定を考える際に、調定額等とあわせて注視すべき要素として「標準税率」があります。標準税率とは、東京都が各市区町村に毎年示す税率や均等割額のことであり、意味するところとしては、「この税率を設定すればその年度のうちに赤字は解消しますよ」というものでございます。
従いまして、最終的に赤字を達成する年度において、均等割額や税率はどうなっているのかを考えるときに、この「標準税率」との比較という視点が一つの目安となると思いますので、それぞれの表における税率等をお話しする前に、令和6年度における標準税率とその税率を適用させた際のモデル世帯における年税額を御説明いたします。
「1.現行計画どおり」の下に「令和6年度の標準保険税率を適用させた場合」という表がございますので、そちらを御覧ください。
令和6年度の標準税率では、均等割が医療分46,918円、支援分17,008円、介護分17,170円。税率が医療分7.78%、支援分2.9%、介護分2.37%で、モデル世帯における負担額は625,300円となります。
左から2つ目「令和14年度に赤字を解消させる場合」では、最終的に表の最下段の令和14年度の均等割額医療分40,300円、支援分16,300円、介護分19,600円、税率は医療分8.13%、支援分2.82%、介護分2.64%、モデル世帯の負担額は614,700円となります。
左から3つ目「目標年次を令和28年度まで延伸させる場合」については、資料1-1では令和29年度を解消年度としておりますが、税率改定を最後に行うのが令和28年度であることからそのように表記しております。表の最下段、令和28年の均等割額で医療分42,500円、支援分17,300円、介護分20,700円、税率は医療分8.57%、支援分2.97%、介護分2.76%、モデル世帯の負担額は648,000円となります。
一番右の「目標年次を令和17年度まで延伸させる場合」も、税率改定を最後に行う令和16年を表の最後としております。
表の最下段、令和16年度の均等割額で医療分38,800円、支援分15,700円、介護分18,900円、税率は医療分7.84%、支援分2.72%、介護分2.54%、モデル世帯の負担額は592,300円となります。
いずれも、あくまで被保険者数や調定額の減少幅等からの機械的なシミュレーションではございますが、被保険者数は年々減少しており、また被用者保険の適用拡大も相まって、その傾向はより大きくなっていくことが予想されます。長期的に赤字解消を図っていこうとする場合、被保険者数そのものが減少していくことから、少なくなった被保険者で調定額を確保しようとするために、最終的な税率や納付額も大きくなることが予想される、という結果になりました。
反対に赤字解消を達成する年度が現行並みに近いほど、1回の税率改定において見込まなければならない調定額は大きくなり、税率等の上げ幅も相応に大きくなります。
また、このシミュレーションでは、あくまで歳入を増加することによって赤字解消を図ることを前提としておりますが、歳入の増加と両輪で注力しなければならないこととして、「歳出の抑制」があり、データヘルス計画に基づく保健事業の効果的・効率的な実施により中長期的に医療給付費を削減していくことが、これまで以上に重要となってまいります。
資料等の御用意はございませんが、令和6年度を初年度とする第3期データヘルス計画において、事業効果の検証を詳細に行う必要があると考えております。
さらに、東京都からの財政補助である「都繰入金2号補助金」の今後の動向や反対に東京都へ支出する「事業費納付金」が今後地域の医療費の実態による調整を段階的になくし、所得による調整額を色濃くしていく方針であることにより、狛江市がどのような影響を受けるか等を精査し、歳入と歳出のバランスの中でどのように赤字解消を果たしていくかを検討していく必要があると考えております。
事務局からの説明は以上です。
(会長)
ありがとうございました。
事務局から説明がありましたが、御意見、御質問等ございましたら挙手をお願いいたします。
(委員)
資料1-2で、結局のところ令和28年度まで延伸させたときに、赤字は解消されても加入者数は減るから一人一人の税額は上がっていくと考えられるのですが、そこはいかがでしょうか。
(事務局)
おっしゃるとおり、税率の計算をするときには前年度の実績を元に計算するのですが、最終的には税率は上がっていき、一人あたりの税額は増えていきます。
(委員)
わかりました。そうすると、この表からは各年度にどれくらいの負担があるのか、1家庭ごとにどれくらいの負担があるのかを考えるには、この資料では足らないと感じました。次回以降、もし資料を出していただけるのであれば同じ年度でどれくらいの負担になるのかを見えるようにしていただきたい。
(事務局)
今回、配布した資料は今の時点での人口減少を踏まえての金額なので、現在の想定で人口減少した場合の金額となっています。例えば、想定よりも人口が減ってしまって、負担税額が上がるという可能性もありますが、そのあたりも加味しての数字となっています。
(委員)
例えば、令和28年度に赤字を無くすとした場合に、令和28年度の税率はどうなるのか、あるいは令和14年度であれば税率はどうなるのかを同じ年度のところで比較ができないので、そこは比較できるようにしてほしい。
(会長)
それでは、次回はそのような形でよろしくお願いいたします。
他にございますでしょうか。
(委員)
資料1-1で令和27年度に解消するという話だった気がするのですが、そこが少し理解できなかったので、もう一度教えていただいてもよろしいでしょうか。
(事務局)
資料1-1の3になりますが、計画上は2年に1度の税率改定を行うタイミングでは、調定額が4,800万円程度増加するような税率を設定し、また税率改定のない年度では医療費の削減や被保険者数の増減により、1,000万円程度の赤字を解消できるだろうという計画に基づいて実施しています。この表を0になるところまで引っ張っていくと結果的に令和29年度になるということです。
(委員)
そうすると資料1-1の令和29年度と同じ税率でいっても赤字は無くなるということでよろしいでしょうか。
(事務局)
資料1-2にある現行計画通りだと赤字は解消しませんが、目標年次を令和28年度まで延伸させた上で、赤字を解消する税率はいくらかという形で出させていただきますので、現行の計画とは必ずとも一致はしません。
(委員)
細かいお話なので、また個別にお伺いできればと思います。
(会長)
他にございますでしょうか。はい、委員。
(委員)
資料1-1で令和3年度から令和5年度までの3カ年で現行の計画値と著しく数字が乖離していっていますが、先程説明にあったコロナウイルス感染症や税制改正の影響で、令和6年度以降は下降していくとなっていますが、さらに乖離していく可能性はないんでしょうか。そのあたりはきちんと分析した上での数字となっているのでしょうか。現行のものにあてはめると、今回の数字になっていくということでよろしいでしょうか。
(事務局)
令和5年度の削減予定額を大きく後退しているところにつきましては、元々税率改定の年度であることや被保険者数の減少により、保険税収が1,400万円程度減少してしまっており、被保険者数の減少以上に保険税収が減少してしまっています。1人あたり医療費は、ほぼ横這いであり、医療費が多くかかったということは考えにくく、東京都に対する納付金が前年度に対して、1億4,000万円程度増額となってしまったことが原因と考えられます。
今後どうなるかというところについても予想をたてるのが難しく、現状から机上でどのようになるかを考えていくことしかできないところでございます。
(委員)
国民健康保険税の未納率がどのようになっているか、そのあたりも含めて今後、分析をするのがいいと思いました。
(会長)
他にございますでしょうか。はい、委員。
(委員)
令和8年度が税率改定の年になるので、そのため令和7年度中に様々な意見を募りたいのか、あるいは他に意義があるのか、もう1点は赤字解消の年が令和14年度や17年度などありますが、赤字解消の年度を狛江市として決めることが可能なのか、また東京都などから何か言われたりしているのかどうか教えてほしい。
(事務局)
まず1つ目の内容について、4つのシミュレーションを実施し、延伸しても良いことがないということが如実に現れています。令和28年度でも税率がかなり上がってしまうことがわかりました。そのため、この4つのどれかと狛江市が考えているわけではなく、諸々の社会情勢などを踏まえて、委員の皆様の意見を伺えればと思っております。
また東京都からは都繰入2号分という補助金がありまして、その中で東京都が令和17年度までに赤字を解消したいという話を受けているところですので、そのあたりは情報収集し、委員の皆様と共有しながら、方向性を検討していきたいと考えております。ただ、東京都からはいつまでに赤字解消しなければならないということではなく、狛江市が決めた財政健全化計画の目標で進めて、問題ないという話でございます。
(委員)
わかりました。
(会長)
続いて、委員。
(委員)
基本的な質問で申し訳ありませんが、資料1-2で示されている標準所帯というところで所得は300万円で4人家族ということで、令和16年度の税額が約60万円になっていますが所得に対して2割というのは、被用者保険だと介護保険などを含めても1割程度になります。そこから考えると非常に高額であり、また介護分の税率は2.54%で、昨年度は1.84%となっていますが、被用者保険は1.6%です。比較すると倍とはいきませんが、相当な介護分の負担が出てくる。これは何か理由があるのでしょうか。
(事務局)
まず介護分の均等割額についてですが、40歳以上の方のみに適用されるものになります。介護分がこのような数字となっているのは、狛江市の事情というよりも納付金を支払うことが可能な税率というところから設定されている税額になります。
(委員)
令和16年度の592,300円の介護分の均等割というのは、40歳以上の方を平均したものという認識で良いでしょうか。
(事務局)
御認識のとおりです。
(会長)
最後にその他になりますが、何かありますでしょうか。
(事務局)
今回、資料が直前の配布でございましたので、質問などなかなか難しいところであったかと思いますが、次回以降は事前に資料を御確認いただけるようにしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
(会長)
1週間前には、配布いただけるとよいでしょうか。
(事務局)
了解いたしました。
(会長)
他にありますでしょうか。委員。
(委員)
何を議題とするか、何を共有するのか、何を説明するのかなど最終的なゴールを示してくれるとありがたいです。
(事務局)
最終的な答申という形ですと、改定案として4案出しましたが、最終的にはどのように実施するのがよいか、委員皆様の意見としてだしていただくことになるかと思います。
(委員)
最終的には運協委員の答申として意見を出すことになるかと思いますが、答申のイメージを示していただけると助かります。
(事務局)
加えてになりますが、財政健全化計画のあり方によって令和8年度の保険税率も影響を受けることになるかと思います。すなわち答申を賜るときには、例えばこの調定にすべきですという話が出た場合には、この調定に達するためにはどういった税率になりますねということをこちらからお示しさせていただくことになります。その答申を財政健全化計画のあり方や来年度の税率改定の根拠にもなるということですので、そこも併せて来年度どうなるかの検討が必要になります。
次回開催時には、事務局から答申イメージ案を示したいと思います。
(委員)
答申案を示していただけるということでしたが、それは一本でということでしょうか。
(事務局)
答申案ではなく、あくまでフォーマットをお示しするということです。
(委員)
わかりました。
(会長)
それでは、「国民健康保険財政健全化計画の見直しについて」は、今回の事務局からの説明や御意見を踏まえて継続審議といたします。
3 閉会
(会長)
以上で、本日予定している議事は全て終了いたしました。
次回、令和7年度第3回目の本協議会は、令和7年11 月18 日(火)13時30分からとさせていただきます。
それでは閉会いたします。ありがとうございました。
|
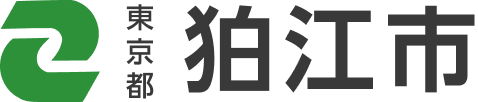
 印刷
印刷
 戻る
戻る
 ページの先頭
ページの先頭