|
(1)健康こまえ21(第3次)・食育推進計画(第3次)・いのち支える自殺対策計画(第2次)~ウェルこまヘルスプラン~について
《【資料1・2に基づき、事務局より説明》
(会長)
内容に関わることでも、専門分野で構わないので、一言ずつ感想をいただきたい。
(委員)
いろいろと苦労してやってきたものが、こうやって形になって良かったと思うとともに、これからまたしばらくしたらこれを評価してという作業がある。せっかくの計画の冊子がどのような形で、どんなところに配布されるのかが気になっている。
(会長)
配布については事務局どうなっているか。
(事務局)
ホームページに掲載し、冊子は、図書館にも置く。なるべく目に触れるような形で配架していきたい。
(会長)
どのようなところに置けばよいか、あるいはどんな方法を使えば市民の皆さんに届くのかということについても、事務局にご助言いただきたい。
(委員)
全く同じ意見である。まず色、緑というのは非常に綺麗で、目に優しいというか、作成した人のセンスが非常に良かった。非常に細かいことで言うと、11ページのところで「健診・検診は定期的に受けましょう」となっているが、「健診・検診」の違いが市民の方が見たらわからないので、間に合うのであれば「検診」は、あえて「がん検診」にした方がいい。私のクリニックでも資料を作って配布するが、金額が安い業者もあり、大量に印刷すればかなり安い額で作れる。地域の印刷業者に頼むのも一理あるが、ご検討いただきたい。印刷は8の倍数で作成できるので、14ページだったのが気になる点でもある。非常に素晴らしいものが出来上がったので、健康推進課と図書館というのはもちろんであるが、高齢障がい課や社会教育課とか他の部署のところにも置いてあるようにして欲しい。経済的に余裕があるのであれば、シルバー人材センターにポスティングという形で仕事があるとシルバーの人達は喜ぶ。
(会長)
冊子は、有料配布になるのか。
(事務局)
本体を買いたい場合、この値段になる。基本的にホームページやデータを見ていただき、なるべく紙で配らないのが内部のルールになっている。
(委員)
高齢者はネットで見るわけではない。これにかける労力や人件費も当然あるわけですから、1人でも多くの人に見てもらいたい。例えば、あいとぴあセンターの1階にあって、ふと気になったら持って帰れる、そういう人が1人でも多い方がいい。
(会長)
過去には何千部も印刷してばら撒く、といった配布スタイルが基本だったが、時代の流れとともにこういった資源、紙資源の考え方が多様化していて、情報を伝えなければいけない部分と環境の部分とか、なかなか庁内でもいい答えが見つかっていないと感じる。最終的には行政におまかせするになるが、今ご助言いただいたように、必要な人には必要な形で情報が届くように、ぜひ配慮いただき、情報提供を行ってほしい。
(委員)
本当に素晴らしい本ができた。市民全員の方にぜひ目を通していただきたい。我々歯科としても、小中学生のむし歯のない子供の割合を上げる努力しくべきだし、市民に対しても啓発していきたい。「8020」というのは、80歳で20本以上自分の歯があるようにってことだが、30年前は本当に5、6%の人しか達成できていなかったが、今は50%以上になっており、歯科医師会も努力していきたい。歯は体の入口であり、がんの予防に一番効果的なのは口腔衛生であり、ブラッシングだと思っている。市民の方にはこういうことをしっかり見ていただいて、ブラッシングをやっていただきたい
(会長)
先生には、口腔ケアが全ての病の予防に繋がるといったことや治療の観点も含めて色々とご指導いただいた。前回の委員会の翌日、そのことを取り上げた番組が流れていた。糖尿病にかかった患者の人が真っ先に行けと言われたのが歯科だったというストーリーだったが、先生からずっと言われたことが映像から出てきて、すごい情報をいただいていたと思った。市民の方が口腔ケアを単純にむし歯予防といった観点だけじゃなく、全ての病に繋がるとか、治療にも役立つということを知っていただくのは重要だと思った。またこの計画を動かす上で、先生には啓発にもご協力いただきたい。
(委員)
概要版は美しく、すごく綺麗でいいな、見たいなと思ったが、計画書はモノクロで、例えば計画書76ページのこま丼の写真があるが、カラーであったら良かった。予算の関係だとは思うが、有料だし、この辺がカラーでないのは残念であった。
(会長)
皆さんもご存知の通り、世の中全てが高騰している状況で、行政的にも限られた予算で作成しなくてはいけない中、このような決断をしなければいけなかったのだと思う。私も経験があるが、綺麗なツルツルの紙を使って全部カラーで作ればそれなりのものになるが、印刷だけでとんでもないお金がかかってしまう事実がある。また、そうすると、環境系の団体からクレームが入って、一筋縄ではいかない所がある。再生紙やフォントの使い方等様々な工夫もできるが、一つの意見でまとまらないところが苦しい。そういう中でも概要版も含めて、バランスを取り、非常に綺麗な概要版が出来たので、まずは多くの人たちに興味を持ってもらい、中身をご覧いただく流れになると本当にいいと思う。とりあえずこの概要版だけでも、多くの人たちの手に取れるような体制をとっていただくのが大事だと思う。
(委員)
冊子は、こんなのができたんだ、すごく綺麗でいいなと思った。私も30年も市民だが、多分こういうものは健康だけでなくて、色々なものが作られてきたと思うが、他は参加したことがなくて、知らなかった。せっかくこういったものができたのだから、何とか多くの方に見ていただきたいと思った。計画書の値段が1000円で、これを売るとなった時に、市民が買ったり使うのかなとも思うが、概要版は、カラーで薄く手に取りやすいし、値段のことはわからないが、なるべく多くの人に見てもらいたい。
(会長)
売るという感覚は行政にはないはずである。これを収入源にしようということではなく、ものを作った時に、その費用の一部を補填する形式に時代が変わっているのかなと思う。過去は値段がついてる計画書は世の中に、国も含めて全くなかった。今それが多くなってきているのは、逆に言うと印刷しないことがメインになっている。データで見るのが主流になって、もし印刷する場合、その費用補填をここに入れ、なるべく数を抑えて環境に配慮して、という流れになっていると想定している。おそらく狛江市全体の環境とか、印刷物に関するルールみたいのが多分内規があって、それに則って作っているはずなので、多分この計画だけでなく、全ての計画書が同じ形に変わってきてるのかと想像する。そんな中で、いかに計画を見ていただくのかが、重要になってくるので、この辺の工夫を考えていく必要がある。また30年住まわれていても、なかなか計画書が手に届かないのは、本当に正直な、素晴らしいご意見だと思う。行政政策と市民の距離感をどういうふうに構築していくのかというのは、ここの部署だけじゃなく、庁舎全体の課題であり、まず健康の分野から、ちょっとでも近づけていけたらいい。
(委員)
この2年の間に、皆さんのご尽力でこれができあがったことに、感謝の気持ちでいっぱいである。一市民としてここに居られるっていうだけでも幸せだと思うし、いかに自分の健康を全く具体的に考えていなかったっということもわかった。狛江市民がこれを冊子で見るのかホームページで見るのかはわからないが、気付くこと1か所でもあれば、ずいぶん健康に繋がるんじゃないかと思う。
(会長)
計画には、子供からだんだん歳を重ねて大人になっていく中での、健康の体系図が今回入っているが、その時々で感じる健康や不健康は変わってくると思う。計画をしっかり把握している人達と全く無関心な人達では、その5年後10年後は、割と大きな差が出てくると思うので、今おっしゃったことお伝えいただきたい。特に市民委員の皆さんには、隣近所にこんなのできたよっという一言をいただけるとありがたい。
(委員)
私は何年かこの会議に参加させていただいているが、今回出来上がって、私はそれに関わらせていただいたんだな、出来上がったんだなっていう実感が初めてあった。この出来上がった冊子を見ると、「ウェルこまヘルスプラン」という副題の方がとても目立つデザインになっている。「ウェルこまヘルスプラン」が副題になったとご連絡がきた時には、ちょっと残念だと思ったが、副題の方が目立つデザインになっており、副題の上に漢字のものがあるが、あれは何なんだろう、よく読まないと読めないので、みんなで「ウェルこま、ウェルこま」って言い続けないといけないと思った。会議に参加させていただいき、いろんな支援がなされているとを知った。この間のサッカーの試合で、東京都の歯科医師会だと思うが、一般ブースがあり、若い人向けに歯科相談っていうコーナーがあって、若い人は歯科コーナーに行くのかなって思って見ていたら、FC東京のデザインが入った歯ブラシもらえるせいか、結構並んでいた。試合の前半と後半の間には、若い人向けに子宮頸がんの啓発動画を流していて、こういうところでも啓発活動をしてるのだとに感じるようになった。狛江市の子供や高齢者の方と話をする機会があり、「野菜を食べようね」とか「狛江の農業を応援しよう」といったことを話すが、計画の表紙の宝船の写真を見て、何年か前に撮った宝船の写真を使って啓発することができ、ちょっと関われることができたのはよかった。
(会長)
今いろんな視点をいただいた。特にご自分がご覧になったサッカーの試合とかで、様々な啓発が行われており、それがこの計画書にも関連する内容であったということだ。言い換えると、世代を超えた人たちに、どう情報を伝えていくのかというところで、サッカーも一つのツールになるし、市内だったらどんなところで伝えることができるんだろうかということを考える貴重な視点だったと思う。また、お子さんへの情報提供というところも非常に重要になってくるので、引き続きご協力をお願いしたい。
(委員)
計画策定にか係わったのは初めてで、こうやって作られてていくことがわかり、本当に勉強になった。私は大学で教育をしているので、若い世代に食育や自殺対策等の情報が届いて欲しいと考えていて、今の若い世代は、インスタグラムや動画を見て情報を得ているので、伝えるためのツールになるかと思う。狛江市の情報アプリ等と連動するのもいいと思う。ちょっと素朴な疑問だが、概要版の11ページのがん検診の産婦人科は1か所だけか。
(委員)
そうだ。狛江市ではないが、東京都予防医学協会に行けば、女医さんが乳がんも子宮頸がんも見てくれる。
(会長)
貴重な意見をいただいた。ライフコースで考えたときに、世代別に情報提供のアプローチの方法を変えていくというご提案は、重要だと思う。デジタル化した情報を受け取りやすい世代と、アナログなものが受け取りやすい世代が確実にいると思うし、必要な情報も違ってくる。若い人たちに届いてほしい情報と、シニア世代に一番読んでほしい部分っていうのがあり、情報全部となると、多分誰も受け付けないと思う。例えば、季節とか、時期を変えて伝えたり、少しずつ伝えていったり、大事な部分を伝えていったりして、情報の提供の仕方を工夫することが必要である。この計画書を順々に網羅していくような伝え方でも十分である。計画書を紙ベースで配布する時代ではなくなったからこそ、割とお金をかけずに、工夫できることもあるかと思うので、来年度以降、この委員会でも提案できたらいいと思う。
(委員)
初めにこういった政策に関われたことを非常に光栄に思う。私自身研究活動をしており、運動に近い領域での政策を見るということを続けてきたが、今回これだけ幅広い範囲を見させていただいたことで、一つのものに対して、直接的に改善をするのではなくて、関連要因等突き詰めていくと非常に面白いんじゃないかなという目線を持った。そして、健康増進室を運営する立場としては、今、会長からもあったが、例えば月ごとに、このプランの中から、重点的に話す内容を決めて、発表していくといったことを行いたいと思う。現在はスポーツをする場所においても、運動の話だけを聞きにくる方はほとんどいなくて、どうしたら健康になれるのか、それこそ運動との関連要因でお伝えしていきたい。
(会長)
狛江の健康増進室は唯一って言ったら変だが、直営の健康メディアである。その場がメディアなので、いろんな工夫をしていただいて、情報提供していただきたい。また、その増進室に通っている市民さんから、隣近所までちょっとずつ広がっていくと、効果が高いと思う。またこの計画書とは違う話になるが、私が聞いてる限り、健康増進室の稼働も結構フル状態、だと聞いているので、もう少し広い増進室や第2増進室であったり、何か公民館とか集まれる場所で地域展開できるような出張型でもいいので、そういった場を広げるという政策がなかなか実現しないので、そろそろ動いていただけるとすごくいい。これもお金をかけて何か箱を作るっていう発想じゃなくて、今あるところの隙間をうまくデザインを変えながらできるといい。
(委員)
私も同じ意見で、今度は体育館が補修工事になるので、体育館を利用してた人はどこに行けばいいんだっていった時に、やはり健康増進室の役割がでてくると思う。現在10時から5時までしかないので、少なくとも9時から5時までにしてほしい。
(会長)
ぜひともそういった場所の確保や広がりお願いいたしたい。
(専門家)
冊子が緑というのは、実は緑っていうのが頭痛予防の色なので、非常にいいと思った。概要版が秀逸だと思い、若い世代に広げることに関しては、中学生と大学生で結構離れていると思うが、実はYoutubeとかTikTokとかの情報をみんな知っている。施策が好きな若手もいると思うので、委員会に入れて、インフルエンサーになってもらう広め方が一番コストもかからないし、よいかと思っている。私の分野から言うと、脳卒中基本法というのが制定されてだいぶ経つが、当院も来年1月から新しくなるので、少なくとも狛江市民の方々の脳血管疾患は、減らしていくっていう気概でやっていくので、一緒にできたらと思う。それから、慈恵医大は4病院あるが、その中で第3病院だけが健康推進センターがあり、それが狛江にあるので、市民の方々の健康推進に還元出来たらと考えている。
(会長)
ご専門分野の立場からご助言いただき、また、情報提供に関しても、この委員の中に若者を入れることによって、その子達が直接どういうふうに情報を伝えたらいいのか、あるいは内容まで作成してもらって、流していただくところまでお願いできるんじゃないかということは、非常に面白いと思った。他の自治体の健康の分野だけじゃなくて、地元の若者を巻き込んで、その若者が作ったコンテンツを様々なところに渡していくってやり方は結構主流になってきてるのと思う。先生にはコラムもご執筆いただいていて、脳血管疾患を含めた様々な予防の観点から記述いただいたので、そういった内容も伝えていただきたい。
(委員)
それが理想的ではあるが、公募して、応募があれば一番いいが、応募がない時はどうすればいいかということも考えなければいけない。市の小・中学校のがん教育の講義をしてるが、その時に慈恵医大の看護専門学校の方が2人と、副校長の先生が来て話をしてくださったことがあった。慈恵医大の看護学科がインフルエンサーになるといったことも可能ではないのか。
(専門家)
私が考えたのは、もうちょっと狛江市独特というか、狛江市で育った青年会や商工会議所のメンバー等がいいのかと思う。
(委員)
そういった形もいいと思うが、例えば青年会議所で狛江を何とかしようと思うような人がいたら先生に呼び掛けていただくのはいかがか。ただ普通に公募しただけでは来ない。
(会長)
狛江市にも大学生がたくさん住んでいて、その中でも公務員を目指している大学生もいるはずなので、意識高い系の大学生に、何か情報が届くような公募の仕方をやってみるのはいいかと思う。委員手当も出るし、無償でやってくださいというお願いではないので、就活等でプラスに考える人達、狛江市役所を受験する人もいるので、アピールをしたいと思う学生がいないとは限らないので、前向きに検討いただきたい。
(専門家)
私も最初にこの表紙を見て、これは読んでもらえるなというふうに思ったが、目次を見て更にそう思った。こういう目次はあまりなく、本当に読んでもらいたい、いや、読みたいっていう気持ちを引き出すようなことを考えられて、あえてこういうレイアウトにされたのだと思った。コラムを読んだが、2次元コード等の工夫もあり、そこを読んでから周辺を読んでみるという方はかなりいるんじゃないかと思う。自殺対策についてだが、102ページにこれも大きなパートを作っていただき、私の方でも提案した、行政だけではなく、市民がいくつかのそれぞれの領域の中で、命を大切にすることに取り組むことが一番大事だということを反映してくださったのだと思う。自殺予防というほぼ遠く感じるような領域が、意外と身近な自分の活動と関係するんだっていう気づきも起きてくると思われる。そうすると、今まで行政目標として、自殺予防のエビデンスっていうものをアウトカムっていう指標で出すのは難しいことだが、どういう工夫ができるんだろうなっていう議論がこれから沸き起こってきて、今後の議論は、より豊かなものになり、学びの一つのきっかけになると思った。
(会長)
今回自殺対策計画の第2次ということで、一体的に入れていくっていうところで、結構行政も苦労され、少しテイストの違う内容をどういうふうに一体的に見せるのかっていうところでも、様々な工夫が必要だったが、先生からお話があった通り、特にコラムを初め、様々に順序よく並んでいたところもあって、一体的にできたのだと思う。特に自殺対策に関しては、市民1人1人の様々な協力が今後必要になってくるというところはもう言うまでもなく、意識して行動するのがいいのか、あの無意識的な行動がそれに繋がっていくっていうふうに捉えるのがいいのか、難しいとは思うが、様々な繋がりというところが、きっと大きな役割を果たしているところは変わらないと思う。そういったことが直接的に、自殺対策に今後貢献していくような結果が出てくるとすごくよい。
ちょうど先週にかけて、私はインドネシアのバリ島に調査を兼ねて行ってきた。皆様もバリ島って言葉を聞いたことがあるかと思うし、何となくリゾート地というか遊びに行くイメージの場所だが、実はバリは、ゴミ処理施設がない。それなのにたくさんの観光客が来る。簡単に言うと、観光客が出してしまったゴミとともに暮らすのが島の人々、っていう悲しい構図になっている。また、貧富の差が激しいということもあって、ゴミの中から再生可能なものを選別して、それを売って生計を立て、観光客が出したゴミが彼らの収入源になっているっていう言い方をしてもおかしくない形になっている。ごみ処理施設がないので、埋め立てていくしかなく、埋め立てるとガスが発生して、自然発火して火災が発生する。集落の中に煙として入ってきて、それに暮らす人たちは煙とともに生活をしなくてはいけなくなり、健康被害が想定されるような地域もある。健康をトータルで考えた時に、楽しみを求めて島に遊びに行く人、ゴミによって日常生活を苦しめられる人っていう構図を見ると、我々のトータルの健康っていうのは、本当にみんなで意識しないとみんなで健康ということは難しいということを改めて思った。ただ、島の中には、日本にもない素晴らしいシステムがある。「ブミセハット」という妊婦さんが無償で出産ができる施設があり、これは、貧しい方々もお金はいらないのでどうぞ来てくださいっていう仕組みでやっている。面白いのは、その施設だから私は産みたいといって、日本からも意識的に行く人が最近多く、意識的に行く人は、お金を払うのだが、その1人当たりのお金が、地元の無償の人の3人分ぐらいを賄えるお金になるようである。それが今循環し始めて、それに気づいた世界のファンドや一流企業、日本でいうとユニクロ等がお金を支援して、その施設が大きくなっている。このことは計画書のどこに繋がるかのかというと、安心とか安全っていうとことで、お金がないから駄目だではなくて、お金がなくてもあそこに行けば助かるんだというような安心があるだけでずいぶん心的ストレスは少ないはずである。心的ストレスが少ないと、体全体に悪い影響が少なくなるというデータがあるので、このように繋がっていくのだと思った。私達は、狛江の計画を作ったが、市内だけで生活してるわけではなく、様々なところと繋がりながら生活をしており、市内にも世界中の方が生活していると思う。次の5年とか10年を考えた時に、今回初めてのウェルビーイングという内容が計画に入ってきた訳だが、トータルに健康を考えていくというのが大事なことになる。また一方で、トータルな考え方があるからこそ、部分的、一分野的な考え方にも興味が生まれるかとも思っているので、このトータルな健康の中で、それぞれの健康を考えていくっていう計画書が今回できたことは非常に嬉しいし、意味合いをみなさんにも語ってもらうことで、狛江市全体に広がっていくとよい。私も計画に携わるようになってずいぶん経ち、昔は計画書の表紙をデザインしたこともあったが、ずいぶんきれいで素晴らしいものが出来上がり、感無量である。
(事務局)
3月31日に健康教育講演会を開催し、すでに40名を超える申込みがあるが、60人を上限として募集をするので、お時間があればぜひお申込みいただきたい。次回の委員会の日程は、7月下旬から8月を予定している。
(会長)
これにて、令和6年度第5回狛江市健康づくり推進協議会を終了する。
|
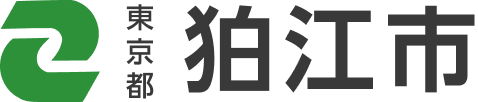
 印刷
印刷
 戻る
戻る
 ページの先頭
ページの先頭